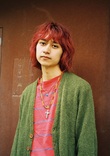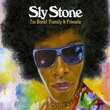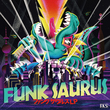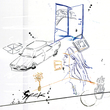後期スマッシング・パンプキンズのヘヴィネス
――そして7曲目の“Don’t Own Me”。これはいわゆるバンガーで、スマパン(スマッシング・パンプキンズ)の“Zero”や『Live Through This』の頃のホールを彷彿とするような曲ですよね。
「そうですね。僕とTamioとErikaの共通体験として、スマパン、ホールは避けて通れないんですね。マシーナリーなところも、思い起こせば90年代後半のスマパン的なものをやりたかったのかもしれないです。
あの時代のスマパンってスタジアムロックみたいになりつつあって、どんどん音が豪華になっていて。僕は初期の彼らよりも、その豪華になった音のほうが楽しいという感覚なんですね。『Adore』と『Machina』のあたりの打ち込みと生ドラムの組み合わせみたいなのはかなり参考にしました。“Don’t Own Me”も、まさにあの頃のスマパンのヘヴィさに影響を受けたものだと思います」
――『Adore』、『Machina』の頃の彼らは当時かなり叩かれていたりもして。
「そうですよね。日本でも〈初期が最高〉というか、そういう初期衝動が感じられる時代のほうがベターみたいな考え方が結構あるじゃないですか。でも、そういう価値観が変わるタイミングに今あるんじゃないですかね」
2000年代以降の新たな価値観、そしてY2Kリバイバルの先へ
――近年、名盤リスト的なものがどんどん再編されていて、リリース当時よりも評価が上がったアルバムもあれば、逆に下がったアルバムもあって。
「そうなんですよね」
――若いリスナーが先入観なく〈えっ、これ、いいじゃん!〉って言い始めているところで、〈実は我々もそう思ってたんですよ〉みたいな便乗再評価が起こっている(笑)。90年代後半のヘヴィネスは、まさにそのタイミングに来たのかなと。
「ええ。その〈これ、いいじゃん〉っていう感覚が僕もTamioやErikaの影響でわかるようになったのが今作なのかもしれません。昔はスマパンでもうるさい曲は嫌いで、飛ばしてドリーミーな曲を聴いてたタイプなんですけど(笑)。純粋にヘヴィなもののかっこよさに最近気づいたというか。だから、この曲のミックスとかプロダクションで参考にしたのもア・パーフェクト・サークルだったり」
――ああ、わかります。
「パーフェクト・サークルや、デフトーンズとか。あそこらへんもErikaやTamioはオープンなんですよ、ヘヴィなものとドリーミーなものを両方とも受け入れているんですね。
あと、Erikaは自称ゴスで、ゴス的なものを大切にしてるんですけど、彼女の言ってる〈ゴス〉っていうのは、キュアーじゃないんですよ。90年代の映画、例えば『The Crow(クロウ/飛翔伝説)』や、2000年代のマイケミとか、そっちのことなんです。そこに気づかされて、たしかに今、ゴスって〈ゼロ年代以降のゴス〉みたいなのもあるよなあと思って」
――ギターミュージックには〈2000年代フィルター〉が作動している、というのは私も常々思っていました。今の若い世代にとってゴスがキュアーではなくマイケミであるように、パンクも(セックス・)ピストルズじゃなくてエモを指すタームになっているっていう。私たちは2000年代以前を知っているから、迷うところでもありますけど。
「実は自分は96年生まれで」
――一緒にしちゃってごめんなさい(笑)。
「いやいやいや。僕はタワーレコードで働いてて、斜に構えまくってしまってたリスナーなので。
96年だと、ギリギリZ世代に入るっぽいんですけど、いちばん年上なんですよ、Z世代の。ちなみに今のY2Kリバイバルって2000年代前半が中心ですけど、僕はすでに2008年ぐらいの音楽が最近すごく好きになってるんです。聴き返したらめっちゃいいじゃないですか、ブロック・パーティとか」
――いや、ほんとに。
「ヤー・ヤー・ヤーズとか、あそこらへん、ありだなって。ありというか、今こそやったらいいんじゃないかなって思うんです」
――ヤー・ヤー・ヤーズも復活しましたし、追い風が来てますよね。かつてリバイバルは20年周期なんて言われてましたけど、今やどんどんそのサイクルが短くなっている。リバイバルやノスタルジアを感じるタイミングがショートサイクル化しているという話は海外メディアでも語られていて、例えば17歳の女の子が16歳のときの失恋をセピア色の思い出として歌うオリヴィア・ロドリゴだったり。ノスタルジアを醸し出すには早すぎる、若すぎると思うわけですが(笑)。
「たぶん今の子とか、もうちょっと年下になってくると、記憶を残すメディアがいっぱいあるというのも大きいかもしれませんよね。写真にしてもSNSにしても」
――ほんとそうですね。
「僕が今覚えている17歳の時の記憶よりも、今17歳の子が僕の年齢になったときに思い出す17歳の記憶のほうがより鮮明だと思います」