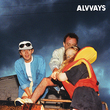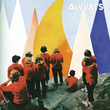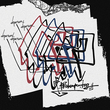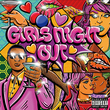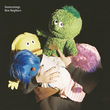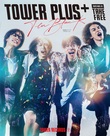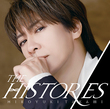キュンとするうれしい変化
──曲も短いですよね。2分とか3分の曲がいっぱいあって、全14曲なのに40分もない。
福富「でも、ファストなイメージはあんまりないのがすごいですよね。普通にやってて途中でいきなり転調したり、違う展開になったり、要所要所が面白い。曲の良さはちゃんとキープしながら面白いことをしてる。僕はそういう意味でも、今まででいちばん好きかも」
畳野「確かに」
──変化に戸惑うのではなく、むしろいいと思えたんですね。
福富「そうですね。その変化がむしろうれしかった。前の2枚のアルバムの胸キュンな良さとは違うところで、またキュンとしてました。シンセのフレーズとかにある、OPN的な80sサンプリング感というか」
畳野「“Pressed”のギターの音やフレーズは、めっちゃスミスみたいだった」
福富「でも、スミスのモノマネで終わってない。アルバム全体として言いたいことがめっちゃあるなかのピースのひとつという気がする」
──最初から完成された個性を持っているバンドだと、あんまり変化せずにいくパターンもありますけど、彼らは変化を選択したんですね。前作から5年も空いてるし、パンデミックもあったし、いろいろ考えるところもあったのかな。
福富「コロナの時期は家で作ることが多かったから、そこから新しいアイデアが出てきたところはあるかも。僕らもそうだったんですけど、普段〈せーの〉でスタジオでやってた時とは違う突拍子もないアイデアが生まれやすい。そういうのが反映されているのかも」

ブリティッシュパブのパンクスピリット
畳野「歌詞も気になります。何を歌ってるのかなって」
福富「セカンドアルバムの歌詞は結構調べて読み込みましたね。自分たちがインディーから出てきたという気持ちを忘れずにいる意思表明みたいな感じが強かった気がします」
──セカンドは、アルバムタイトルも〈反社交主義〉みたいな意味でしたもんね。
福富「パンクスピリッツみたいなものはサウンドにも現れてましたよね。日本では〈ネオアコっぽい〉と言われることもあったけど、向こうでは〈ポストパンク〉じゃないですか。そういうスピリットをオールウェイズから感じられることはうれしいです」
──〈ネオアコ(ネオアコースティック)〉という言葉は日本では影響力が強いけど、海外ではほとんど使われないですからね。
福富「スミスも感じるし、ポップパンクよりも前のパンクっぽさも感じる。ポストパンクっていうのは今回のアルバムへのタグ付けとしては出てくるワードなのかもしれない。プロデューサーともそういう意図が組み合ったんだろうし」
──元テレヴィジョンのリーダーであるトム・ヴァーレインに捧げたのかわからないけど、“Tom Verlaine”って曲名があったりしますしね。そういう人や70sパンク前後の時代へのシンパシーがあるのかなと思ったりしますよね。
福富「今、ポップパンクのリバイバルが来てるなか、それより前のスタイルにいったというのがね。面白いですよね」

畳野「ライブが観たいなあ」
福富「ね。オールウェイズの新作を聴いてると、僕らがイギリスツアーへ行ったときのパブを思い出すんですよ。ウェールズだったっけ、ライブが終わるとDJパーティーが始まって、スージー&ザ・バンシーズとかがかかる。そしたら、みんな盛り上がって、輪になって踊るんですよ。〈(セックス・)ピストルズとかはかからないんですか?〉って訊いたら、〈あれはパンクじゃない。バズコックスからがパンクだ〉って言われて(笑)。それってたぶん、日本に入ってきてないパンク観なんですよ。ニュー・オーダーの曲とかもその文脈でウケてました。そういう身体的な感覚でのポストパンクをこの新作にも感じます」