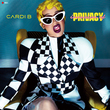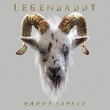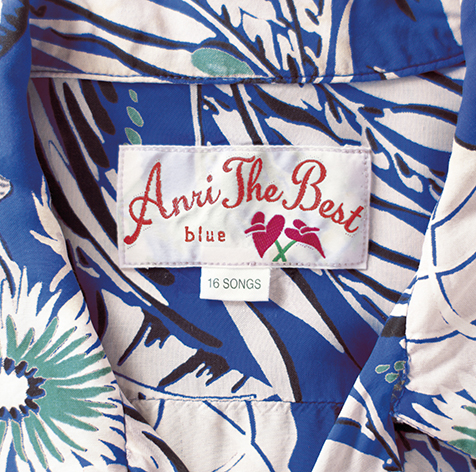ラテン音楽の伝説的アーティストが軽視されるのはクソ
バッド・バニーは、「プエルトリコ人だけに聴いてもらうつもりで曲を作っています」とGQのインタビューで語っていた。プエルトリコを飛び越えて、ラテンアメリカを、いや、世界を代表するスターになっているにもかかわらず。また、ローリング・ストーン誌の〈歴史上最も偉大な100人のシンガー〉について、「『アメリカの歴史にあるものを列挙しました』って感じで、クソっ、胸糞悪かった」、「ラテンアメリカ音楽界には伝説的なアーティストがたくさんいるのに、その人たちを偉大な存在として取り上げていない」とも言っている。それらの発言を踏まえると、〈コーチェラ〉でのパフォーマンスは、ラテン文化が軽視されるアメリカ中心主義的な価値観に反旗を翻すプエルトリコ人アーティストとしてのバッド・バニーの素顔が思いっきり反映されたものだったと言える。
今、ポップミュージックの世界で存在感を増しているラテンポップについては、ルーツよりも最新のアーティストや作品に注目がどうしても集まりがちだ。また、最新のヒップホップやR&Bからの影響、それらとの相互作用も大きく、そのことばかりが語られがちでもある。しかし、ポップミュージックとは、歴史のダイナミズムから生まれてきたもの、そしてこれからも生まれてくるものなのではないだろうか。
バッド・バニーのステージは、そんな状況のなかで〈みんな、昔のラテン音楽のことを忘れていない?〉と、アメリカや世界に向けて問いかけるものだった。そして、ラテン音楽のシーンで成功を収めた者として、その歴史や文化を背負う覚悟や情熱を表したものだった。それに、ラテンミュージックが、アフリカンアメリカの音楽と同様に、遠いアフリカやヨーロッパにルーツを持つ者たち、場合によっては生まれた土地から強制的に引き剥がされた者たち、彼らが歌い奏でる音の混交が生んだものである、ということをも示していた。
バッド・バニーのパフォーマンスについては、否定的な見方をする者もいるかもしれない。たとえば、〈持つ者〉である成功者が文化や歴史全体を代表していいのか、というような。そこには、搾取や、複雑さと曖昧さの捨象、単純化などの問題がはらまれる。それでも私は、この〈Bunnychella〉を言祝ぎたいと思う。ベニートが、〈中心〉であるアメリカの周縁にいた者が、自身が根ざす文化や歴史を大きなステージでレプリゼントしたことに、素直に感銘を受けたから。
以上、バッド・バニーの〈コーチェラ〉でのパフォーマンスについて、2つのインタールードに主に注目して書いた。ただ、私はラテン音楽について専門的な知識を持ち合わせているわけではないので、もし誤りがあれば、SNSなどで指摘していただければと思う。