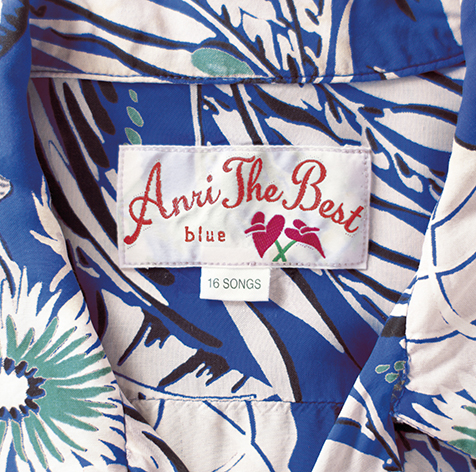〈絶対大丈夫〉と思える外部アレンジャーの貢献
――外部のアレンジャーさんに入ってもらうというアイデア自体はいつごろ出てきたのでしょうか?
Ichika「『CASTLE』の頃からそういう人が欲しいとは思ってたんです」
ササノ「3人の中で自分が一応アレンジャーみたいな立ち位置だから、最初は〈自分でどうにかしたい〉っていう感じもあったことはあったんですけどね」
Ichika「そんな話してたわ。〈アレンジャー入れよう〉って言ったら、ササマリが〈俺の役割がなくなるから〉みたいな」
ササノ「そうだったんですけど……いやあ、よかったですね、アレンジャーさん呼んで(笑)。めっちゃ楽しかった。
一番最初にお世話になったのが川口さんとTAKU INOUEさんだったのが個人的にはでかかったと思ってて。っていうのも、僕が本当に大好きな方たちだったので、〈このお2人なら絶対大丈夫じゃん〉っていう。これがあんまりよく知らない人だったりすると、同業者のライバルみたいな感じがしちゃうけど、尊敬してる人なら大丈夫だなって。
実際出来上がってきたアレンジが本当に素晴らしかったので、こんなにありがたいことはないなって」
――たなかくんも外部の人と組むというアイデアは最初から頭にあった?
たなか「僕はなんなら〈歌詞もメロもくじらくんとかに作ってもらった方がよくね?〉みたいなことをずっと言ってたんで。結局今回も歌詞は全部自分でやることになりましたけど……自分が本当に秀でてるところはどこなんだろう、みたいなことを考えることって大事だなと思ってて。
僕は〈メロディーを作る人〉という意識がそもそもあんまりなくて、ラップしてたらいつの間にかメロの比率が大きくなって、気づいたら歌の人になっていた、みたいな意識が強いんです。だからあんまりメロディーへの……こだわりがないわけでもないんですけど、〈自分が作らなきゃ〉みたいな気持ちはそんなになくて。
曲の届きやすさ、広がり方みたいなことで言うと、歌の表現とか声そのものの方が自分のストロングポイントだと思うんですよね。歌詞は難解になりがちだし、テーマ選びもいわゆるポップスの範疇から外れがちなので、〈他の人にお願いしちゃった方が楽じゃない?〉ぐらいのことをずっと言ってたんですけど、今回は自分が言いたいことをいかにポップスのフォーマットで表現しきるか、みたいな方向に挑戦の種類をずらすことで、楽しく書くことができました」

トレンドはガン無視、アートコア経由のドラムンベース
――最初に作ったのが“ラブレス”ということで、“Virtual Castle”にも通じるジプシージャズ感はササノくんのテイストだと思うんですけど。
ササノ「そう言っていただけると大変嬉しくありつつ、僕の中に本来このテイストはなかったんですよ。ただジャンルとして好きだし、ネット系でも流行ってて、そういう曲を作れて人気な人たちが羨ましかったから、自分も作れるぞっていうのを出してみたくなって。それで挑戦してみたのが“Virtual Castle”で、もうちょい上手くできるなっていうので“ラブレス”になった感じです」
Ichika「ササマリの自己顕示欲から生まれた曲です(笑)」
ササノ「でも“ラブレス”に関してはIchikaも〈この音はもうちょっとこうした方がいいかな〉っていうのを返してくれて、2人のやり取りでまとまったものを投げて、川口さんがブラスセクションを考えて、TAKU INOUEさんがキックとベースのトリートメントをしてくれたことで、洗練された上でちゃんと尖ってる、みたいな形になったと思います」
――アレンジそのものはササノくんとIchikaくんの作ったものが基になってるけど、川口さんとTAKUさんが入ったことでよりブラッシュアップされたと。
ササノ「人にお願いすることのありがたさを教えてもらうというか、レッスン1みたいな感じ」
たなか「で、その後にレッスン2で“アンダーグラウンド”を作ったんですけど、この曲もまだトータルアレンジをやってもらう段階じゃないよね。これも“ラブレス”と似たような感じで、ブラッシュアップしてもらうっていう」
――“アンダーグラウンド”はIchikaくんのギターから作った曲ですか?
Ichika「いや、これは(ササノと)2人で遊びでドラムン(ベース)みたいなのを作りたいっていう話から作った曲で、最初Diosのアルバムに入れようとも考えてなかったもんね。でも1コーラス作ったらそれが楽しくなって、フル尺ができて、たなかに〈歌ってみてよ〉って送ったら、意外といいなって。楽しくなれるジャンルでやるのがいいよね」
――近年はピンクパンサレスやNewJeansをはじめ、ドラムンベースなどのクラブミュージックをベースとするポップスがトレンドになってたりもするけど、そこへの関心もあったわけですか?
Ichika「いや、トレンドはガン無視です。僕らは古の音ゲー界隈のドラムンのオタクで、だからアートコアをやりたかったんだよね。音ゲーの界隈にアートコアっていうジャンルがあるんですよ。Feryquitousっていう方がいて、この曲のサビはかなりまんまなんですけど」
ササノ「Feryquitousだったり、昔で言うとonokenさん」
Ichika「そう、onokenさんがアートコアの元祖の人で。構成は様式美にのっとって、“アンダーグラウンド”もサビの後半でキメを入れてて」
ササノ「この曲が一番趣味性が強いよね」
――アートコアとハイパーポップって文脈的に近いのかな?
ササノ「アートコアはもっと昔の、本当にオタクのカルチャー、音ゲーのカルチャーから出てきたもので」
Ichika「具体的に言うと、サビがこの曲みたいなリズムで、きれいなピアノが入ってて、コード進行は絶対に456(IV→V→VI)か436(IV→III→VI)、サビの真ん中で1回落ちて、マイナーに行って」
ササノ「一瞬転調したり」
Ichika「そういうのが様式美としてあって、みんなそれをこねくり回していく、みたいな。でもたなかの歌が入ってガラッと変わりましたね」
たなか「僕はその……アートコア? それも今〈そんなのがあるんだ〉って知ったぐらいなので」
ササノ「文脈を知らないから、そのメロディーにのっとることがないので、それが良かった」
Ichika「オタク3人集まってたらマジでそのまんまになってた(笑)」
たなか「“アンダーグラウンド”は自分のことを愛せない人が、世界の美しさを憎んでしまうことをテーマに書いていて。これって現在の自分とはまた違うんですけど……。
今は日々が満たされているので、もう自分のために音楽を作って表現をする必要がなくなったんです。自分の満たされなさを掬い上げて、消化するために音楽を作るっていうのが最初の……」
――ぼくりり(ぼくのりりっくのぼうよみ)時代はそうだった?
たなか「ぼくりりにもなる前ぐらい、一番最初に曲を作ったときはそういうところから始まってたんですけど、もう完全にそれがなくなったんで、じゃあ自分が何のために音楽をするのかなと思ったときに、本当の意味でやっとリスナーのために音楽をやろうという気持ちが出てきたんです。
今までは〈それってフェイクだよね〉みたいに思ってるところがかなりあったんですけど、それが自分の中で腑に落ちて。なので、“アンダーグラウンド”は思春期のひねくれた子供たちに向けて歌詞を書きました」