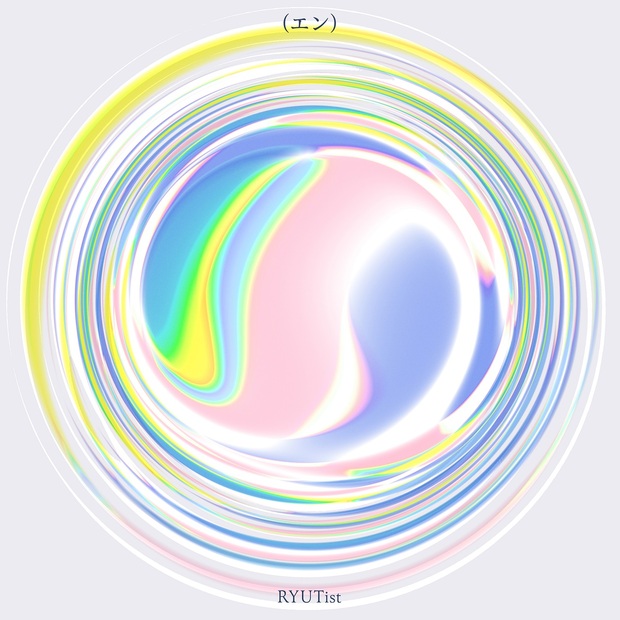RYUTistがCDシングル“春風烈歌”を本日4月3日にリリースした。絶賛された傑作『(エン)』を経て新体制となった3人の待望の新作だが、表題曲は今までにない新しい姿を力強く見せる、驚きの鮮烈なナンバーだ。そんな“春風烈歌”の背景や音楽的な魅力について、メンバーがインタビューで語った言葉を交えつつ、ライターのimdkmが綴った。 *Mikiki編集部
新たなスタートを切る3人を刻んだ転換点
「RYUTistって声のトーンをあわせて歌うことが多いんです。でも“春風烈歌”は、それぞれがエネルギッシュに歌った1曲。ひとりひとりの曲に対する想いも含めて、ここからはじまる新しいRYUTistの姿も楽曲にしっかり込められたんじゃないかなと思っています」(横山)。
“春風烈歌”はRYUTistには珍しいほど生身の感情があふれでた1曲だ。曽我部恵一が楽曲提供したこの曲には春を迎えて新たなスタートを切る3人の現在がなまなましく、みずみずしく刻み込まれている。また、そんなフレッシュさと同じくらい、これから長く愛されてゆくだろう代表曲の風格すら湛えてもいる。攻めた楽曲が多かったここ数年の流れから一転、親しみやすさに満ちているけれど、RYUTistにとってはひとつのターニングポイントになりそうな一歩だ。
妥協しない〈攻めのRYUTist〉は到達点へ
もともとRYUTistは、ギターポップを軸とした楽曲を通じてその音楽性が支持されてきた。2020年のアルバム『ファルセット』以降は、蓮沼執太や柴田聡子、パソコン音楽クラブといったアーティストたちのサポートを得て、より先鋭的な表現へと果敢に足を踏み出していた。2022年にリリースした『(エン)』にはさらに君島大空、ウ山あまね、ermhoiらが楽曲提供で参加。サウンド面のみならず、構成や展開も大胆な楽曲が並び、〈攻めのRYUTist〉のひとつの到達点に至ったように思う。
その後、2023年春にメンバーの佐藤乃々子が卒業を発表。五十嵐夢羽、宇野友恵、横山実郁の3人体制となって、新しいRYUTistの歩みが始まった。2024年2月にリリースされた3人体制になって初のシングル“君の胸に、Gunshot”は、D.A.N.の櫻木大悟が作詞から作編曲までを担当した曲で、『(エン)』のエレクトロニック路線をさらにストイックに突き詰めたようなダンスナンバー。RYUTist、妥協する気がない!と驚かされる第一歩だった。
ストレートで力強い生身の歌、歌いたくなる豊かなメロディ
しかし、その次に届けられた“春風烈歌”には、別の意味で驚いた。それまでのクールさから一転して、思いきりエネルギッシュで、熱く、エモーショナルなサウンドと歌唱。ガッツのあるバンドのサウンドは、かねてから得意としてきたギターポップの爽やかなポップさともまた違う。むしろ、こうしたロック的なアツさからは距離をとったスタイリッシュさがこのグループの特徴だっただろう。ドラムやギターの鳴りもフレージングも、RYUTistらしからぬパワーに満ちている。とりわけ、歌メロと同じくらい雄弁なメロディを奏でるリードギターは、3人の歌声を後ろから支えるコーラスのようにも感じられる。
ロックコンボ編成の力強くストレートなアンサンブルと同じくらい、楽曲構成や歌割りも、メロディの強さを活かしたまっすぐさが印象的だ。数秒の短いイントロを経てサビからはじまり、あいだに二度、ブリッジ的なパートを挟む以外は同じメロディを繰り返す。そんなシンプルさ故に、技巧的というよりも、むしろエモーショナルなパフォーマンスが引き出されている。
「RYUTistって、あまり感情を込めすぎないでクールに歌うことも多かったんです。でも、私は感情を込めてガツンと歌う方が向いているというか、得意な方なので。この曲でRYUTistの熱い思いを込めてライブでも発揮できたらなと思います」(宇野)。
「いままでは、楽曲の強さに助けてもらっていた部分もあると思います。でも、“春風烈歌”はシンプルな曲だし、きれいなメロディに自分たちの歌をのせるからには、本当に歌唱力がめっちゃ大事だなって思って。RYUTistの歌の部分が出るような、歌で勝負する新境地だっていう感じがあります」(五十嵐)。
洗練された楽曲を完結した作品としてパフォーマンスするだけではなく、むしろ生身のRYUTistの姿を浮かびあがらせる。一聴してキャッチーで耳馴染みの良い“春風烈歌”がこのグループにとってターニングポイントとなりそうなのは、まさにそんな理由による。実際、3人の歌声を聞いた曽我部恵一の提案で、感情をより乗せやすいように、制作時にキーをデモ段階よりも少し上げたのだという。
メンバー3人にとってのみならず、リスナーやファンにとってもこの曲はある意味心をひらかせてくれるようなところがある。単純に、〈自分も声を合わせて歌いたくなる〉のだ。それは曽我部恵一の書く、繰り返しに耐えるストーリー性の豊かなメロディの力であり、またシングルに封じ込められた3人の歌声の力でもある。