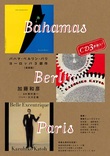2009年に亡くなるまで、生涯を通してジャンルや音楽性を軽々と変化させ、常に時代に先駆けた加藤和彦。日本のポップやロックの黎明期から活躍した彼の影響は、2024年現在も多大だ。そんな加藤の軌跡を追った初めてのドキュメンタリー映画 「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」が、ついに5月31日(金)から全国公開される。これを機に音楽ジャーナリストの柴那典が異才の全キャリアを捉え直し、その真価を再考した。 *Mikiki編集部
加藤和彦の何が革新的だったか、どう時代を変えてきたか
いま、最も再評価されるべき日本の音楽家は、加藤和彦なのではないだろうか。
いまやすっかり定着したシティポップのリバイバルにとどまらず、フォーク、ロック、アンビエント、ニューエイジなど、過去半世紀の日本のポピュラー音楽のさまざまな野心作が海外も含む若い世代の音楽リスナーから熱い視線を集め、評価を高めている。
ただ、その中で、その功績の大きさを考えると比較的見過ごされてきたと感じるのが加藤和彦だ。ザ・フォーク・クルセダーズ、サディスティック・ミカ・バンド、ソロなど様々な名義で作品を残しながら、常に時代の先を行く革新的な音楽的挑戦を見せてきた加藤和彦のキャリア。5月31日に公開される映画「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」は、そんな〈先駆者としての加藤和彦〉にフォーカスした初めてのドキュメンタリー映画となっている。
では、加藤和彦の何が革新的だったのか。どう時代を変えてきたのか。映画でとりあげられているいくつかの曲と共に紐解きたい。

ビートルズの影響下でシーンを変えたフォークル“帰って来たヨッパライ”
まず最初に挙げるべきは“帰って来たヨッパライ”だろう。1967年10月に放送を開始した「オールナイトニッポン」での度重なるオンエアをきっかけに〈社会現象〉としてのヒットになったこの曲。オープンリールのテープレコーダーを倍速にしてピッチを上げたボーカルが、コミカルな曲調とあいまってブームを起こした。当時のザ・フォーク・クルセダーズは京都の学生が組んだアマチュアのグループだ。まだインディーズレーベルという概念もない時代。レコード会社の手を借りず自宅で録音し自主制作で作った作品がここまで広まった例はそれまでなかった。間違いなくその後の日本の音楽シーンを変えた一曲だ。
影響源にはビートルズ『Revolver』がある。間奏には“Good Day Sunshine”のフレーズが引用され、ラストの読経には“A Hard Day’s Night”の一節が紛れ込む。ザ・フォーク・クルセダーズの楽曲では、他にも“何のために”が“Eleanor Rigby”と通じ合うムードだったりもする。60年代のフォーク、そしてビートルズのリアルタイムの影響下にある存在としてのザ・フォーク・クルセダーズと捉えると、“帰って来たヨッパライ”のインパクトだけじゃなく音楽シーンの系譜の中での意義深さを感じることもできる。
ただ、ビートルズの影響下にある多くのソングライターがそれを創作活動におけるある種のOSのように基盤に持ち続けるのとは違って、加藤和彦はそこを〈脱ぎ捨てる〉ようなキャリアを歩むのも興味深い。もちろんドノヴァンを筆頭にしたフォークシンガーの影響も大きかっただろうし、おそらく1969年、ヒッピームーブメント最盛期の西海岸に訪れた経験も大きかったのだろう。ソロアーティストとしてのデビュー作『ぼくのそばにおいでよ』は、アメリカンフォークと日本的な抒情が混じり合うような、おおらかで親しみやすいメロディーメイカーとしての加藤和彦の魅力を感じさせる一枚だ。