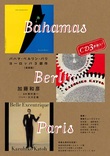2009年に突然、遠い空の向こうへと旅立っていってしまった加藤和彦。ザ・フォーク・クルセダーズやサディスティック・ミカ・バンドといった名グループを率いて名作を世に送り出し、ソロに転じてからも、バハマ・ベルリン・パリで録音したヨーロッパ3部作という金字塔を打ち立て、竹内まりやの“不思議なピーチパイ”や飯島真理の“愛・おぼえていますか”といった上質なポップスをヒット・チャートに送り込むなどソングライターとしても確固たる地位を確立した彼のキャリアはなんとも多彩にして複雑な模様を浮かび上がらせているわけだが、このたび公開される初のドキュメンタリー映画「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」は、数々の貴重映像や豪華コメンテーターたちのエピソードを丹念に積み重ねながら彼の人生を紐解き、そして多くの謎を解き明かそうと試みた作品となっている。
ここでお伝えするのは、さる5月17日に催された特別試写会の模様である。この日、トーク・ゲストとして登壇したのは、デビュー35周年イヤーの只中にある高野寛。そして、ジャズ・ポップ・ユニット、sorayaで1stアルバム『soraya』をリリースしたばかりの石川紅奈というご両名。彼らは、映画のエンディングに登場するトノバンの代表曲のひとつ“あの素晴しい愛をもう一度”の新録ヴァージョンに携わったTeam Tonobanの一員だ。高野は歌唱とギターに加えて編曲も兼務、そして石川はウッド・ベースを弾きながら、坂本美雨とのデュエットを披露している。
トークは、高野がトノバンの名前を知るきっかけについてのエピソードからスタート。
「ちょうど中学、高校ぐらい、YMOの熱烈なファンだった頃ですね。YMOのピープル・ツリーを辿ってくと、高橋幸宏さんがサディスティック・ミカ・バンドをやっていた、なんてことを知るわけです。そうそう、小学生の頃は“帰って来たヨッパライ”を歌えてましたよ。僕らの世代はみんなそうじゃないかな? 僕はデビュー時から幸宏さんの近いところにいたので、加藤さんはとても身近な存在でした。彼が亡くなった後に全アルバムを聴いて、いろいろ知っているつもりだったんですけど、今回映画を観たら驚くような発見が多くあって。とにかく情報量の多さがすごい」(高野)
教科書に載るほどのスタンダード曲もあれば、サブカル史に燦然と輝く偉業の名作を残していたりもするあまり類を見ない音楽道。威風堂々にして奇々怪々。他の人と同じルートはけっして選ばず、ときには自分が歩いてきた道すら無かったことにしてしまおうという態度を示したりもする。フォーク、グラム・ロック、ボサノヴァ、レゲエ、タンゴ、シャンソン、カンツォーネなど雑多なジャンルを横断してきた彼はあらゆる面において先駆者であり、つねに一流という称号も授かっている。そんな彼の新作からたえず読み取れたのは、あまりに軽快すぎるフットワーク。いつだって枠にとらわれず、鋭敏な直感やセンスに忠実に従う様子はときに、掴みどころがない、といった印象を抱かせることもあるが、それが円滑に正当な評価を下すうえでの支障となっているとしたならば? 監督の相原裕美が映画作りの〈動機〉としたものはそういった類いの考えだったのではないかと推察する。
「フォーク・クルセダーズとミカ・バンドを同じ人がやっていたっていう事実だけでもすごいこと。時代ごとに音楽スタイルが本当にガラッと変わっていくんですけど、多面性からくる複雑さがどうしても影響してしまい、いろんな作品を熱心に聴き込んで、テキストとかも利用しないと全体像がなかなか見えてこない。でも彼のキャリアが時系列に沿って語られていくこの映画を観れば、こういうことがあったからこういうふうになったのか、と、いままで見えなかった繋がりが理解できたりして、驚きも多かったですね」(高野)
「私にとっては、とにかくサディスティック・ミカ・バンドの映像がスクリーンで観られるのがすごく贅沢な体験」と語るのは石川である。
「とにかく古さを感じさせないし、自分にとってやっぱり新しいものだったんだな、って気づかされました。音楽は耳にしていたけれど、実際の人柄とかどういう顔をしていたのかも知らなかったから、いろいろ判明して興味深かった。彼のことを何も知らない人でも、すごく興味の湧く内容になっていると感じます」(石川)
「それから音楽映画としてすごく楽しめる作品。使用された音源は、素晴らしいエンジニアであるオノセイゲンさんがリマスターしているんです。だからめちゃくちゃ音がいい」(高野)
石川がトノバンの音楽に出会ったきっかけというと?
「コロナ禍に入る前ぐらい、高校生の頃からよく出入りしていたジャズ喫茶があって、そこで行われていたセッションに歌の練習ということで参加させてもらっていたんです。ある日、日本語の曲もいいんじゃないか?って話になり、教えてもらったのがフォーク・クルセダーズの“悲しくてやりきれない”でした。YouTubeで映像を探したら、スーツを着てベースを持った方(←北山修)がヴォーカルを採っていて、これは私がやったほうがいいんじゃないかとピンときまして」(石川)