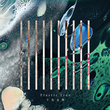全部に理由があった
仄暗いフィードバック・ギターと甘美な歌が渦巻く“痣花”を経てエンディングを飾るのは、有村による2曲。柔らかいリヴァーブ越しに切なさを募らせる“メルヘン”と、ノスタルジックな世界観で聴き手を温かく包み込む“夢落ち”が並ぶが、後者はエンドロールのように鳴り続けるオルタナ・カントリー調のギター・ソロが新鮮だ。
「ちょっとタームが空いての制作だったから感覚が鈍ってたのもあって時間がかかりましたけど、“メルヘン”はバンドのイメージのひとつ……自分の役割のうちのひとつにしっかり貢献できた曲だと思います。“夢落ち”も古い曲で、もう15年ぐらい前に作ってたものですね。バンドにフォーク要素を持ち込む曲をこれまでもたくさん作ってきましたけど、この曲はずっと処理がわからなかったんです。でも、いまだったらいい感じになるっていう予感があったから、〈バンドで作りましょう!〉ってみんなに任せたらすごいスムースに出来たんですよね。結果的に2部構成みたいになってますけど、最後のタームはプリプロ中のフラッシュ・アイデアで、感覚的にはセッションに近い作り方というか。〈10代の頃からこういう展開やってみたかったんだよね〉〈いいじゃんいいじゃん〉みたいな、ほんとにそんなノリで(笑)。ただ、それで昔を思い出したというか……このバンドって3枚目ぐらいまでは合宿で作ってて、その頃のセッション的な発想も、いまの自分たちのライヴでメインになってる楽曲の大きな要素だったりするじゃないですか。それを忘れてたわけではないけど、よりはっきりと思い出した感覚があるんですよね。いままでのバンドの歴史を、いろんな意味で。今回はそれをあちこちの楽曲にぶち込んだ、みたいな感じです。歌詞についても、これまでの人生のいちばん大きな部分ってバンド活動だったと思うんで、バンドにまつわることだったり、音楽活動を通して出会った人、いなくなっちゃった人、自分たちを好きでいてくれる人たちに対しての自分なりの気持ちも入れてるつもりっていうか、入っちゃってますね。“夢落ち”も“メルヘン”も、出来上がってから自分で読んでみたら、ああ、こういう気持ちもあったんだなって改めて思ったり」(有村)。
30年にわたるバンドのこれまでが綴られた“夢落ち”。だが、大陸的なギター・サウンドが物語の最後に描き出すのは、これからに向けてさらに歩みを進めるバンドの姿だ。
「うん、この先も続いてくれるような感じ。それは希望でもあるけど、考えてこういう締め括りにしたわけじゃなくて、すべては偶然(笑)。まあ、偶然は必然でもあるから……だから、アルバムの名付け方も含めて全部に理由があったんだろうなって。作り終えたいまはそう思います」(有村)。
Plastic Treeの近作。
左から、2020年作『十色定理』、メジャーデビュー25周年樹念ベスト盤『(Re)quest -Best of Plastic Tree-』、2023年のシングル“痣花”“ざわめき”(すべてビクター)