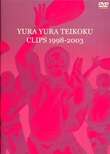「本当はこんな真面目なことばっか言いたくないんですけどね」。取材の終盤、坂本慎太郎はゆったりとした口調でこう語った。最新作『ヤッホー』の、弛緩したソウルやファンクを媒介にして忍び寄る不穏なムードは、坂本の見つめる現実世界の映し鏡として、ほのかな色気を帯びたまま発光している。
先行シングルとなった“おじいさんへ”の〈おじいさん 外は混乱してます/気にしないで 後は やっときますので〉や、“あなたの場所はありますか?”の〈声がでかい人であふれている/涙もろい客を集めている〉といった一節にギョッとした者は少なくないだろう。自分もその一人だ。例えば『幻とのつきあい方』の頃は震災、『好きっていう気持ち』の頃はパンデミックと、坂本の言葉は社会情勢と時折重なり、望外の角度から内省を促していた。『ヤッホー』をその延長線上のアルバムとしてシリアスに受け止めるかどうか……それは(先に挙げた作品たちもそうであるように)リスナーの自由だ。僕たちは『ヤッホー』を聴き、好きなように踊ることができる。まずはそのことを寿ごう。
そもそも、今の坂本慎太郎が足元のみを見つめて活動しているわけではない。パンデミック以降は毎年のようにUSツアーやアジアツアーへと繰り出し、坂本は現地の熱心なオーディエンスや同好の士とも言える音楽家と親交を深めている。事実、2026年1月現在のSpotifyにおける月間リスナー数では、サンパウロやメキシコ・シティといった都市が東京のそれを上回っているのだ。エル・マイケルズ・アフェアのアルバム『24 Hr Sports』での客演、さらに遡ればドラン・ジョーンズ&ザ・インディケーションズの東京公演への飛び入り参加など、レトロモダンなソウルの復権と坂本慎太郎のセンスが重なっている事象は興味深い。
今回はこうした〈課外活動〉を整理し、現在の坂本慎太郎が置かれているポジションにフォーカスするところから取材を始めた。千葉雄喜との遭遇やV6への作詞提供など、意外なトピックは尽きない。とはいえ、そうは言っても、『ヤッホー』だ。正常と異常が反転した世界のBGMとして、僕とあなたを取り巻くあらゆるイシューの隠喩として、ごく平易な言葉で綴られた全10曲。その周辺を歩き回りながら、坂本の立っている地点から見える景色について訊いた。
リオン・マイケルズとは好きな音が似てるのかな
――今回のアルバムはいつから制作していたんですか?
「曲自体は前の『物語のように』を出してからちょこちょこ作り溜めてて、2024年の12月になんとか10曲揃いました。そのデモをメンバーに渡してレコーディングを始めたのが去年の4月ですかね」
――『物語のように』のリリースが2022年の6月なので、そこから約2年半で『ヤッホー』の曲を書いたと。LIQUIDROOMでのワンマンではエル・マイケルズ・アフェアの新作に収録されている“Indifference”をアンコールで披露されていましたよね、こちらも同時期に制作していたのでしょうか?
「あれは2024年の10月ぐらいに〈これでなんかやって〉みたいな感じでデモが送られてきて。ただツアー中で作業ができなかったので、2025年の1月にようやく録音して送り返したんです」
――それ以前に親交はあったんですか?
「ないですね、会ったこともなかったです」
――えっ(笑)。
「もちろん事前に〈次のアルバムに参加してほしい〉っていうオファーは貰いましたよ。ただしばらく間が空いたので〈あの話は消えたのかな〉と思ってたら、忘れた頃にデモが来たって感じなんです。ビッグ・クラウン(エル・マイケルズ・アフェアーのリーダーであるリオン・マイケルズが主宰するレーベル)の作品はリスナーとしてずっと買ってましたし、彼のプロデュースするアルバムも聴いていました」
――リオン・マイケルズは売れっ子ですもんね。特に印象的なプロデュース作は何ですか?
「クレイロの『Charm』、あれをすごく気に入ってて。ただ最初はリオンがプロデュースしたとは知らなくて、よくクレジットを見たら〈あ、これもやってるんだ〉って。たまたまYouTubeとかで聴いたら好みのサウンドだったので他の曲も聴いてみたら、もう全部良い。それで慌ててアルバムを買ったっていう(笑)。なんだろう、好きな音が似てるのかな」