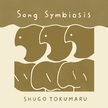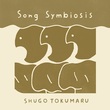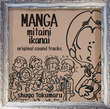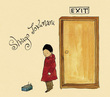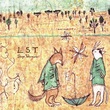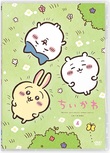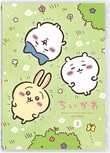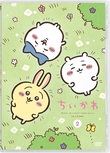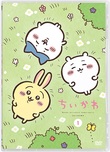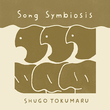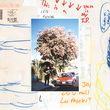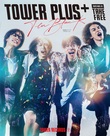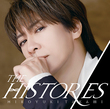僕にしか聴こえない音を
――その4曲は2020年5月から12月にかけて配信シングルとしてリリースされましたね。
「そうなんです。実は、それらの曲を作っていたのと同じタイミングで〈保育の研究に携わってみないか〉というオファーを受けました。即答でOKして、もともと好きだった哲学、心理学、脳科学、美学、音楽教育とかそういう資料をいっぱい見尽くすことをずっとしていました。(コロナ禍で)そういう勉強をする時間をいっぱい得たんです。
あらためて向かい合ってみたら今だからこそよく理解できるところもいっぱいあった。それで、〈今なら自分の音楽が聴けるかもしれない〉と思って、初めて自分の音楽がどういうものかを理解しながら聴くことができたんです。そしたら」
――そしたら?
「結構いいな、って(笑)。そして、僕がなぜ自分の音楽に感動できなくなっていったのかもだんだんわかってきた。自分が初めて曲を作ったとき、初めて音楽に触れたときに立ち返って、そういえば自分にとってこれが重要だったよなということをもう一回取り入れる。そう考え直すことができたのが、コロナ禍の時間でした。
その重要なことは、自分が受けてきた音楽や芸術教育に対して抱いていた疑問とも関係していました。その疑問を一回解きほぐしたいと思ったし、今の自分ならこう言えるというのが見えてきた部分があります。今の教育はもちろんいい方向に変わってることもあるんですけど、ぐっとアップデートできるはずで」
――そういう部分と、コロナ禍の前に取り組もうとした方向性が、この新作では合致したということですよね。
「合致したのかもしれません。それでも2020年から4年かかってるので。
ちょうどその頃から、能が好きになったんです。能って、演目によっていくつか次元があるんです。ひとつは、誰でもすぐにわかるような演目。もうひとつは、しみじみ感動させるような演目。もうひとつが、なんだかわからないけどいつの間にか心から出でて感動してしまう演目。
そのような大きな枠組みがあると知って、僕が自分の音楽でやってなかったのは、その3つ目。聴いたときになんだかわからないけど、何日後、何年後かにじわじわと感動するような、そういう音楽ってそれまで作ったことがなかったなと。そういうところを今なら目指せるんじゃないか、そういう音楽を作ってみたい、と思ったんです」
――いつかわかるものを今作るぞ、というのは、なんとなくアプリオリ的ではありますよね。
「そうなんですよ(笑)。それを作るためにはどうしたらいいのかをずっと考えてきたんです。そこでは〈驚かせてやる〉とか〈感動させてやる〉とかではなく、ただただ普遍的なものを作ろうとした。
それで考えたのは、僕にしかわからないような音を細かく細かく詰め込んでいけばできるんじゃないかと。僕にしか聴こえてない音をちょっとずつでも入れていくことによって、それが成されるんじゃないか。それにトライしました。そしたら、かなり時間がかかってしまったんです」

噪音や無音が奏でる〈共生〉の音楽
――トクマルさんの音楽は基本的にひとり多重録音だし、自分で自分の意図した音を積み重ねて、曲としての囲いを作っていく作業ですよね。「シムシティ」みたいに音楽という地図や囲いを作っていくような。でも、今聞いた話は、そこに自分にしかわからない要素を詰め込んでいって、曲に対して想定した囲いとは別の成長をするように促す、みたいなことなんでしょうか。
「僕がやった試みは、まず楽器とか歌とかの根源について考え込むことでした。まず特定の楽器や歌はなぜそれが生まれたのかを問い詰めて、その何を守って何を壊していいのかを考える。
もうひとつ、僕がこのアルバムで大事にしたのは、〈噪音〉です。口ヘンの隣に口を3つ書いて、その下に木を書いて音をつけて〈そうおん〉と読むんですけど、〈音程を持たない音〉を意味する言葉です。たとえば擬音であったり、非楽器、環境音、ノイズであったり。そういう音はもともと大好きで1stアルバム(2004年作『Night Piece』)の頃から入れていましたけど、今回、なぜその噪音を自分は入れなければいけないか、その意味を結構理解できた。
それは、噪音というものが、ある音楽がその音質でなければならない理由ともつながっています。たとえば古いレコードで聴く音質とかもそうです。そこには、音源にある音以外の環境からの音とかも加わる。そういうものをあえて重要視してみようと思ったんです。単純にフィールドレコーディングの音を入れてみましたというだけじゃなく、こだわった音を細かくひとつひとつの楽曲の端々に眠らせてみる。わかりやすい例としては、1曲目の“Toloope”でフィールドレコーディングした〈無音の音〉を入れているんです」
――〈無音の音〉というのは?
「外に行って、山に近い場所で音を録るんですが、草木の音も聴こえない場所で、車の音も聴こえない環境で、虫も鳴いてない時期。これって結構難しいんですけど、そこを探して深夜の2時くらいに録音しました。すごくかすかに入れてるので、これは僕が説明しなくちゃ誰にもわからない音なんです。そういう音は、絶対にAIには作れない。その〈無音の音〉に感動できるのは人間だけですし。あとは自分の耳鳴りの音程の傾向を調べてみたり……。
それはジョン・ケージや、アンビエント音楽の考え方ともちょっと似てるんですけどね。息遣いの〈すー〉って音とかもそう。波形にすればわかるけど人間の耳には聴こえにくいような、14キロヘルツくらいの犬笛の音とか。そういう音をいっぱい散りばめて作り上げた感じですね」
――自分の意図で入れてはいるけど、それをわかってもらうことは求めていない。面白いですね。
「自分の意図で入れるんですけど、無意識下に訴える、もしくは音自体の意思で動きだしてほしいなと思っていて(笑)。僕にはまだそこまではできてないけど、できたら理想的ですね。聴くたびに音が勝手に動き出すようなミックスができたら本当に理想通りだと思うし、それを目指してはいました。先ほどの『シムシティ』の例えでいうと、街のなかにいろんなものを自分で配置するけど、そのあとで勝手に発展していくじゃないですか。そういうことも音楽でやりたいですよね」
――今、トクマルさんが言ったような要素は、このアルバムを聴いていてなんとなく感じてました。聴こえない音が聴こえるわけではないんですけど、植物から採取した電磁波をもとに音楽を作る人にも近い、音自体が音楽のなかで動き出す要素を持つような。
「アルバムタイトルにも〈共生〉という意味を持つ〈Symbiosis〉という言葉を入れているんですけど、人間が音楽を作ることは、自分の暮らしと音楽と社会と世界と動物と虫とすべてが関係性を持ってできている。それを自然なかたちで出していくことで、僕自身も感動できるんだろうなと気づいたからです。日常の気持ちを表現するようなフォークミュージックとも違って、日常との関係性のなかで生まれてくる新しく湧き出てしまう表現を入れたかったんです。
今回、歩いているときに鳥の声が聴こえてきて、珍しく鳥がドレミを歌ってるように聴こえたのでふと録音して、それを作品に入れちゃったりしてるんですけど、そういうふうに今という瞬間を切り取ることはできるなという感覚ですね。〈鳥の声を曲にしてすごいでしょ〉と言いたいわけじゃなく、単純に湧き起こったものを素直に表現するだけでいいんじゃないか。そういう要素がかなり今回のアルバムには埋め込まれている」