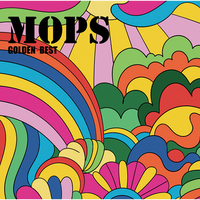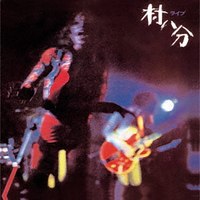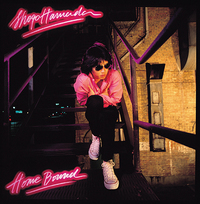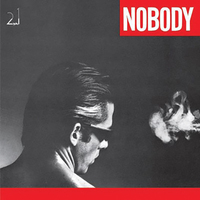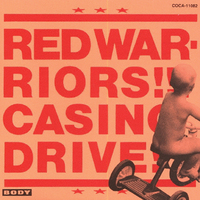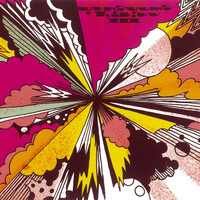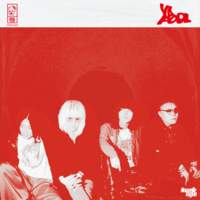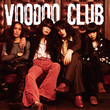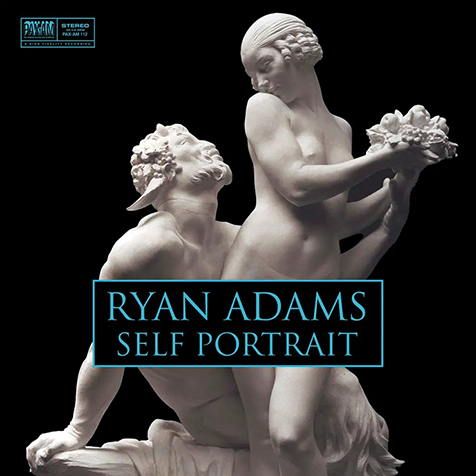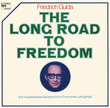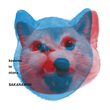50年の歴史の突端にいる暴動クラブと共鳴する日本のロックンロール盤!!
ザ・ダイナマイツなどガレージ系GSに影響を受けている暴動クラブ。鈴木ヒロミツや星勝が所属、〈サイケデリック・サウンド・イン・ジャパン〉に挑んだ先駆的GSバンドの軌跡を辿るシングル集がこちら。 *天野
ローリング・ストーンズめいた不埒なサウンドに独創的な詞とアクの強いヴォーカルを衝突させた、日本語ロックンロールの先駆者による唯一の公式盤。暴動クラブはその猥雑な音楽性と佇まいを見事に継承している。 *北爪
浜省のこの6作目に収録された“あばずれセブンティーン”を暴動クラブはEPでカヴァー。父親の影響で幼少期から聴いていたという釘谷の選曲だが、浜省の真価を〈とっぽいロックンロール〉に見い出したのは慧眼と言う以外ない。 *北爪
矢沢永吉を支えた相沢行夫と木原敏雄の2人組バンドによる初作。作編曲チームとしてヒットを生みつつ、自作では英国志向のロックンロールを80年代に刻んだ。時流を意識せず、真ん中をめざす姿勢は暴動クラブと共振? *天野
今年6月の東名阪ツアーをツーマンで共にした大先輩の2作目。外連味に満ちたダーティーなロックンロールに世代差なんて関係なし。表題曲や“FOOLISH GAMBLER”など、暴動クラブが演奏しても違和感はない。 *北爪
トップ10シングル“太陽が燃えている”を収録し、初のオリコン1位を獲得した5作目。UK録音でのシャープな音作りがポップさを引き立てた点は、暴動クラブの新作に通じる。となると次に控えるは“JAM”級のアンセム……? *田中
2000年代の和製サイケを塗り替えていった3人組の3作目は、GS~ガレージなグルーヴをさらに磨き上げたうえで、多様な音楽性をポップに開花。カルトな魅力と人懐っこい歌心の両立は坂本慎太郎ソロでさらに深化した。 *田中
英語詞によるタイトで黒いノリのロックンロールを信条とするバンドの4作目。そのスタイルは暴動クラブとは異なって見えるが、両者の根っこは60sのガレージ・パンクで繋がっている。その解釈の相違を比べてみるのも一興。 *北爪
みずからを〈ロックンロール・バンド〉とは決して呼ばない3ピースの2作目。彼らの曲はブリル・ビルディング産ポップスや渋谷系を咀嚼したもので、ディープなリスナー気質を多面的な音に落とし込む点は暴動クラブも同様。 *天野
佐々木亮介は常に己の資質を疑ってきたが、ザラついた声で葛藤を切り裂く最新作は、歪さや野暮ったさを内包する〈日本のロックンロール〉の王道に彼らが立つ証だ。その歩みはいつか暴動クラブとも交差するだろう。 *田中
暴動クラブやフーテン族と並んで東京新世代ロックンロール・シーンを象徴する4人組。ガレージやパンクを継承するハードな演奏、チバユウスケの如き迫力の石川蓮の歌が鮮烈で、嵐を呼ぶに足る名刺代わりの初作だ。 *天野