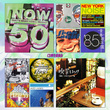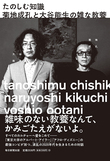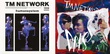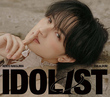さらに広角な作曲技法を展開する、岸辺露伴シリーズ・待望の第二弾
前作との意匠的な異同をもとに、愛好家のあいだでははやくも赤盤と呼びならわされているという本作、「岸辺露伴は動かない」第9話「密漁海岸」および映画「岸辺露伴は動かない 懺悔室」を収める2枚組サウンドトラックは初作となる黒盤のリリースから2年ぶり、高橋一生演じる岸辺露伴が世にあらわれた2020年から数えるとすでに5年の月日がすぎている。
テクノロジーはむろんのこと、社会情勢から政治、経済、倫理、道徳にいたるまで、昨晩のことが今朝方には反故になりかねない昨今において、岸辺露伴シリーズがかくも長きにわたり視聴者の支持を集めて離さないのはひとえに作品の質によるもの。演出、衣装、ロケーション、なんといっても脚本ですよね、それが日本のドラマの水準をふまえると抜きん出ている──と、菊地成孔は本作の音楽もまたなまなかのものであってはならないと言外ににおわせつつ、上のようにふりかえる。そのうえで岸辺露伴とは、読者諸兄姉はよもやお忘れではあるまいが、国民的人気マンガのスピンオフの実写版といういわば「合わせ技」なのである。
「原作には膨大なファンがいて実写化にさいして、おそらくいろんな意見をもっている。現代は彼らに忖度しようと思えば、無限にできてしまう時代なんだけど、今回それをやってしまうと倒れていたと思うんですよ。そう考えたときに、岸辺ではいっさい忖度しない、目の前の作品に対して音楽をつくるんだとハラを括ったんです」
制作にあたってもうけたのが「『岸辺露伴は動かない』は怪奇ものなのだ」という公準。それにより20世紀音楽の無調や不協和な響きを参照項のひとつに定めるとともに、ホラーの付帯物ともいえるラブロマンスや文芸作品の含意を書法で詳らかにするという戦略を菊地はとっている。それとともに本シリーズの劃期となったのが〈菊地成孔/新音楽制作工房〉のクレジットである。黒盤につづき赤盤でも作者クレジットは両名の併記だが、自身の私塾の生徒を房員にみたてたギルド体制はco-writeが主流の昨今のあり方を先駆けていた、というよりむしろ、菊地によれば、はるか昔の工房制作体制に先祖返りしたのだということになろうが、長短、硬軟おりまぜ曲数も要る劇伴仕事が、その数年前より伏在していた菊地の思考を顕在化させた点でも本シリーズは有意義なものであった。体制の変化が制作の方法の変化を促し、方法の変化はテクノロジーの進展と無縁ではない。菊地成孔はいささか牽強付会ですが、と前置きをしたのち、本シリーズが最新技術の導入にいかに貪欲であったか述懐する。
「いまではコントラバス数台が入って重厚になったテーマ曲の“大空位時代”も最初のバージョンは弦楽四重奏とピアノとハープだけでしたから。そこにボカロが乗るだけで、聴いた人全員、人間が歌っていると思うような時代だったんですね。それが音声ファイルのMIDI変換やMax MSPなどのAI前夜のテクノロジーから現行の生成AIまで最先端のテクノロジーを軒並み使用するなかで体制も変わってきた。そして最新作『懺悔室』最大のトピックは全曲が工房メンバーの制作により僕が1曲も書いていないということなんです」
ヴェネツィアを舞台に、ヴェルディ中期の代表作“リゴレット”が物語の鍵となる「懺悔室」には作中でこの3幕もののオペラを露伴とバディ役の編集者京香が鑑賞するシーンがあり、劇中の枢要な実在の曲との距離感をはかるべく、菊地はその対極を志向するのではなく併走する方法をとっている。すなわち独唱の場面が主となる“リゴレット”に合唱によるサウンドトラックを対置するという考え方である。むろん“リゴレット”自体は映画内でこそ鑑賞可能だが、OSTには不在のため、私たちはその空位の周囲を旋回するほかないが、そのことが本作のマニエリスティックな佇まいを下支えするのはいうまでもない。他方の「密漁海岸」も海ないし水、能声楽家青木涼子の謡(うたい)による声の側面で「懺悔室」とパスを交わしながら、黒盤の“都鳥”しかり、往時の大作曲家たちの手になる邦楽モチーフの現代曲という怪奇もののゴールへと決め球を運んでいく。もっとも「阿漕」や「法華経」など、本編の筋書きにも通じる能の演目の採用は青木涼子の示唆によるものだというが、青木との縁をとりもった能へのアプローチも中学時代に鑑賞した「サテリコン」(1969年)に由来するのだと菊地はいう。公準たる怪奇ものの、公式のひとつでもあるフェリーニ × ニーノ・ロータの「世にも怪奇な物語」(1967年)に次ぐこの映画の異教的な場面に不意にながれる読経の声の記憶こそ「密漁海岸」へのロングパスなのだと種明かしをしつつ、「整合性は調性と同じで、ポップだからみんなよろこぶんですよ」と述べる菊地成孔の融通無碍さこそ、いよいよ多義的に散開はじめたAI時代の作曲行為の最先端というべきであろう。