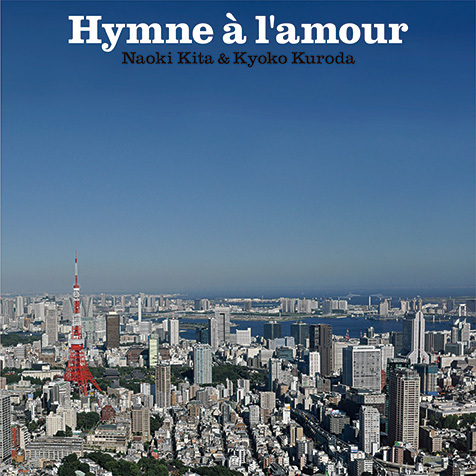北のヴィジョンとタンゴ的情念が一体化した喜多直毅の世界
ヴァイオリン奏者の喜多直毅がこの秋2枚の新作を発表する。1枚は、喜多直毅クァルテットによるライヴ盤『Winter in a Vision』。もう1枚は、ピアニストの黒田京子とのデュオによる『愛の讃歌』。前者で演奏しているのはタンゴ・マナーのオリジナル作品群であり、後者は“シェルブールの雨傘”など映画音楽を中心にしたメロウなスタンダード曲カヴァー集。作品としてはかなり毛色が異なるが、両方ともまぎれもなく喜多の世界である。
そもそも喜多直毅ほど、ありとあらゆるスタイルの音楽を並行して演奏してきたヴァイオリン奏者は、少なくとも日本ではほとんどいない。あえて言えば、太田惠資ぐらいか。クラシックから始め(国立音大卒)、英国留学でジャズ理論などを学び、更にアルゼンチンではタンゴを勉強(ピアソラの共演者フェルナンド・スアレス・パス他に師事)。帰国後も、プログレ系バンド〈サルガヴォ〉や、翠川敬基のフリー・ジャズ・バンド〈緑化計画〉、ウード奏者・常味裕司のアラブ音楽楽団〈ファルハ〉等で腕を磨く一方、齋藤徹や千野秀一などとの出会いを入り口に、内外で即興演奏の経験も積んできた。
そんなヴァーサタイル・プレイヤーとしての喜多の表現の核になっているのは、やはりタンゴである。しかし、タンゴに盲従、耽溺しているわけではない。彼が奏でるのは、常にタンゴと自分の距離を測りながら自分は何者なのかを自問している、そんな複雑というかややこしいタンゴ、愛憎まみれタンゴなのだ。新作『Winter in a Vision』が何よりもそれを明快に語っている。今年頭に岐阜の美術館で行われたライヴを記録した本作中、明確にタンゴのリズムを使った曲はごく一部しかないのだが、どこを切っても、タンゴが本質的に孕む苦悩や葛藤、エロス、パッション、郷愁といったものが爆発的に噴き上げてくる。
「僕は、タンゴも持つそういった複雑な情念を抽出したものを、自分の音楽として形にしたいんです。それも、僕の頭の中を常に占めてきた北国的/東北的ヴィジョンと一体化したものとして」(喜多)
岩手出身の喜多にとって、北国的/東北的ヴィジョンというのは極めて重要なものなのだ。だからこそ、『Winter in a Vision』のジャケットとして、青森を拠点に東北の影と風を撮り続けた伝説的写真家、故・小島一郎の作品を喜多は選んだのである。雪の積もった北国の海辺を走る黒い馬。北国でしか生まれない荒々しい抒情と孤独を切り取ったこの写真が、喜多たちの奏でる音と見事に一体化し、我々の耳を撃つ。
「ようやく、自分そのもの、何の混じりけもない自分の世界ができたと思う」(喜多)