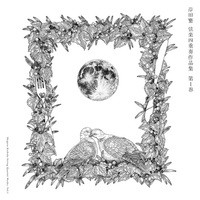テーマは〈多ジャンル音楽の融合〉、バンド的な感覚が生きる初の弦楽四重奏作品集
「クラシックの演奏家の方々は、子どもの頃から練習を沢山して、ときには押さえつけられたりしたかもしれません。でも、そういう人たちが音を捕まえて演奏する時、音楽に救われた瞬間が数多くある。それが、ぱん!と、生きる瞬間が。それに出会うのが作曲家としてはいちばん興奮するんです。演奏家のパーソナルなところ、ああ、いい顔してるなあ、とか、この人ブラームス大好きだけど、このまえオアシスのコンサートに来てたな、とかもあわせて。たとえ所帯が大きなオーケストラであっても、パートパートでそういうのが見える。(対して)ソロでやっているソナタとかはその人次第、その人自身ですが、アンサンブルは、色々な気遣いや特性のようなものとのせめぎ合いみたいな中で、個人が浮かびあがるところがある。その感覚が好きです。ヴィオラっていいよな、とか、フレンチ・ホルンでもセカンドとかの方がいいな、とか」
〈作曲家〉岸田繁の新しいアルバムは弦楽四重奏のフォーマット。ろくにジャケットもみず、先入観なしに聴くと、それぞれの楽章はスタイルがかなり異なっている。あれ?とおもう。それは、でも、〈弦楽四重奏曲〉だという緊密なかたまりを意識しすぎている、いわばフォーマリスティックな先入観をどこかに持っていたから、とおもいなおす。
「意図的に変えたところもあるし、まとめて聴いてもらう時には〈組曲〉の感じかな、と。“1番”は抒情詩的なところがあり、“2番”よりまとまった感じがあります。“2番”は、コンセプトとしては、後づけではあるけれど、これらを並べるんだったら、何を食べさせられるかわからない、なんか困った料理屋だろうな、と(笑)、そこからタイトル“変な料理”がつきまして。そもそも、色んなものが好きですから」
バンドのように、メンバーとともにつくっていくものに対し、オーケストラや弦楽四重奏は、基本、ひとりで練りあげてゆく。
「クラシカルな曲でもそれ以外でも、ここだけは思いどおりにしたいという部分と、まあ、食べられたらよくない?が、私のなかで同居しているんです。これから曲を作っていく中で、これはどうしても、ということはあるかもしれないけど、基本は、もっと肝心なところが、思い描いているものがしっかり落とし込まれていれば、それで問題はなくて、厳しいこだわりのようなものはない――どちらかというとなさすぎるかもしれません。その時気持ちよかったらいい(笑)」
「完成度の高いものは素晴らしいと、私がわかるようなものでしかないのかもしれないけれど、思いますね。本当にクラシカルなもの、そういうのをしっかりやろうとおもったらまた違うのでしょうけど、ただ自分のやっているのは混じりものが多いんですよ。演奏記号、発想記号がそうだと思うんですが、dolceとあったときに、今2025年で、私は49歳ですけど、どこかにいる18歳と(dolceの感じ方は)違う。その音楽のdolceがどう演奏されるかというのは意識している。今回の作品は編成が小さいこと、演奏家が若いということで、意思疎通がしやすかったというのはありますね」
録音で聴くだけでなく、ライヴで聴いてみたい。
「楽譜を出版していただいたのですが、クラシックの世界と、ポピュラーの世界と、いちばん大きな違いは、スコアがすべて。録音芸術とこれは大きく違うことだと思っているんですね。ポピュラー・ミュージックの世界に若いころ飛び込んで、当時はCDが発売されたとか、録音ができるというのがコンサートよりステータスだった。それはいまだに自分の中にあって、だから、どうしても(弦楽四重奏も)録音しておきたかったし、クラシック好きではなくても、つくった曲を聴いてほしいと思いました。今は少しおじさんになったけど、若い演奏家と一緒にやっていると、話が早い。クラシック以外の音楽に詳しかったりしますよね。そういう人たちに演奏していただく機会が他にもあるといいなあ、と思っているのです」
バンドがライヴで演奏する。そのとき、1曲1曲かなり違っていてもおかしいとかんじない。編成こそ弦楽四重奏だが、ひとりひとりの演奏家の楽曲とのかかわり方、姿勢にはバンド的な感覚が生きている。
「条件反射的なもの、場の空気みたいなのが、生かせているといいですよね」
今年2月にはくるりの15thオリジナル・アルバム『儚くも美しき12の変奏』もリリースされる。マスタリングも終わったばかり。岸田繁から生まれる2つのバンド形態――ロックバンドと弦楽四重奏――を聴きくらべるたのしみへ!
岸田繁(Shigeru Kishida)
1976年4月、京都生まれ。音楽家。
ロック・バンドくるりのフロントマンを務める傍ら、作編曲家として管弦楽曲や映像のための音楽を数多く手掛ける。