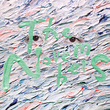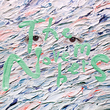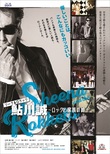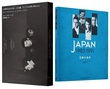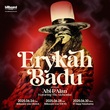こんな時代だからこそ、ロックは品格と作法を持たないと(土屋)
――今回のEPを作るに至った順序としては、土屋さんにプロデュースをお願いするのと、EPでリリースするのを決めるのとでは、どちらが先だったのでしょう?
小林「EPにするかアルバムにするかは決めてなかったんですけど、なにかしら作品を作ろうとは思っていたんです。『Rhapsody in beauty』を作り終えたあとに、今作に繋がるような考え方というか、意図してデザインされた美しさ、洗練された美しさとか。透明感のあるポップなものを作りたいという気持ちが芽生えて。『Rhapsody in beauty』のなかに“Romancé”という曲があるんですけど、あれをもう一歩進めたような世界観を表現できたらいいなと思ったんですよ。そんなふうに考えていたときに、土屋さんにやってもらえたら素敵だろうなと考えていたんです」
――その時点で、すでにヴィジョンとして描いていた?
小林「そのときは、まだ夢物語みたいな感じでしたね。〈こんなことができたら素晴らしいのに〉っていう。そういうことを考えはじめて作曲に取り掛かったくらいのときに、最初のベンジーさんの話に繋がっていくんです。だから、タイミングとしてはほぼ同じくらいでしたね」
――先ほどおっしゃっていたような方向性をめざした理由を、もう少し詳しく教えてもらえますか?
小林「『Rhapsody in beauty』は美しいと感じるものであれば、整理整頓されてなくても、過激であってもエキセントリックであっても濁っていてもいい。美しいと思うことがすべての理由なので作品にしましょうと、思い切り良く作れた作品でした。それを経験したうえで、もっとデザインされたものや洗練されたものに興味が向いたのかもしれないです」
――そういうコンセプトを、土屋さんにもお伝えしたんですか?
小林「そうですね、もう少し別の言い方だったかもしれないですけど。デモを聴いてもらいながら、スミスとかキュアーとかコクトー・ツインズとか、おおまかな音像やイメージだけは伝えて」
――土屋さんもプロデュースをされる際に、THE NOVEMBERSの過去作を聴かれたと思うんですけど、どんな感想を抱かれました?
土屋「いや、もう素晴らしいなと。特に『Rhapsody in beauty』は本当に素晴らしい。正直に言うと、なんでもっと売れてなかったんだろうと不思議に思いました。そのくらい優れた作品だったし、なにかが間違えていますよ」
――ですよね。
土屋「特にいまの日本は、文化的なレヴェルがものすごく下がっちゃっているから。そのなかで、これだけのレヴェルの作品を……言葉を換えればビジネスにしなければいけない。それは至難の業ですよ。でもだからこそ価値があるというか、作っていく意味がある。無謀な挑戦かもしれないけど、それをやってみる意味は十分にあるから」
――だからこそ、〈Elegance〉という言葉をタイトルに冠して、こういう時代に掲げることには大きな意味があるように思えたんですよね。〈Elegance〉には〈優雅〉という意味があるけれど、それは裕福さとか生活水準とかの話ではなくて、例えば心を気高く持つことを言いたかったのかな……とか。
小林「そうですね。それに日本語で言うところの〈粋〉だったり、あと僕のなかでは素直さや正直さがテーマにあったんです。素直に正直に生きているのが、粋に映るような自分になれたらいいな……というか。高尚というイメージよりは、より良く生きるということ。多くを求めたり、欲深くなったりするのとはまた別の、気持ちのうえで優雅なものが作れたらいいなと思ったんですよね」
――土屋さんのキャリアにおいても、〈Elegance〉は重要なテーマの一つだと思うのですが。
土屋「もちろんです。僕の場合、〈Elegance〉といえば〈品格〉ですね。それで、〈品格〉といえば〈作法〉なんですよ。これはもう間違いない」
小林「あぁー、なるほど」
土屋「そして〈作法〉といえば、弓道ですよ。小笠原流の弓道が作法の始まりみたいです。だから、弓の矢の先に〈エッジ・オブ・エレガンス〉があるわけ」
――作法の極みが(笑)。
土屋「こんなときだからこそ、品格と作法は大事ですね。まさに、ロックはそれを持たないと。〈好きだったらいいじゃん〉じゃダメなんですよ」
――そう思いますね。THE NOVEMBERSは自分でレーベルも運営して、アートワークや写真などヴィジュアル面でも独自のこだわりを見せていて。そういう活動姿勢には〈品格〉と〈作法〉が感じられます。
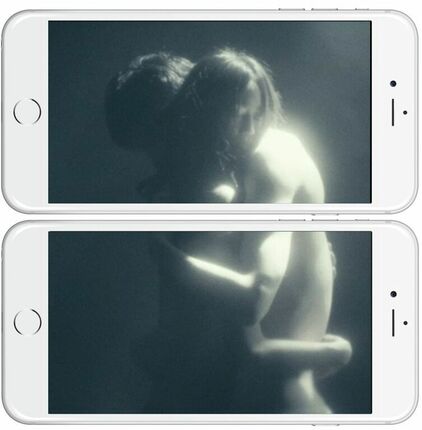
2台のスマートフォンで並べて再生すると、より世界観を楽しめる内容になっている
土屋「バンドを維持していくために、すごく大変なことをしているのに、何事もないように振舞っているわけですよ。祐介くんも他のメンバーも、音楽に対して誠意がありますよね。このあいだTHE NOVEMBERSのライヴを初めて観たんだけど、みんなスッと立っていて。その姿勢こそが〈Elegance〉だよね。でも休みになると、実家に帰って税務署に行ったりしているの。そういうこともちゃんとやっている」
――EPのサウンド・プロダクションについては、先ほどスミスやキュアー、コクトー・ツインズの名前が挙がっていましたが、具体的にどんなサウンドをめざしていたのでしょう。
小林「僕は最初、そういう先に挙げた80年代のニューウェイヴやポスト・パンクだったりを、当時の音で再現してくれるかもしれないというか、そういうのができたらおもしろそうだと思ってたんです」
――僕も土屋さんのプロデュース作だと聞いて、あるいはそういう音になるのかなと少し思ってました。
小林「でも結局のところ、当時の音をめざすのではなく、いまの音をちゃんと鳴らすことができました。そこが一番気に入ってるポイントです。何かを再現するというよりは、『Elegance』という作品の収録曲が求めている音を作れた。もっと言えば、自分たちと昌巳さんが関わったことに相応しい音ができたかなと。あんまり気負ったことをしないというか、それよりも綺麗な音、いい音で録ることにこだわって。シンプルなところに立ち返った気がします」
土屋「いまの祐介くんの話に付け足すとしたら、〈空気〉なんですよね。2015年の空気。例えば4ADにせよラフ・トレードにせよ、サウンドを近付けようと思えば近付けられるんですよ。どういう機材を使っていたのかも把握していますし。それよりも決定的なのは、78年だったり80年だったりの空気。それはもう絶対に再現なんて無理なわけで。60年代や70年代でも同じ話で、歴史に刻まれた名盤とされるレコードが、その他の忘れ去られた99.9%と何が違うのかというと、その時代の空気を記録しているかどうかなんですよ。メンバーやエンジニアには言わなかったんだけど、僕が一番気にしていたのはそこなんです」
――ニューウェイヴの時代も、マーティン・ハネットのようなプロデューサーが時代の空気を閉じ込めていた。それと同じ試みを、2015年に実践しようとしたわけですね。
土屋「それより前の世代のジョージ・マーティンと直接話をしたこともありますけど、やはり最後に言うのはそこなんです。だから彼は、自分のスタジオを〈AIRスタジオ〉と名付けてたでしょう。メチャクチャ深いですよね。今回のレコーディングでも、ソフト・シンセの音だけを使ったところとかは最後の最後まで〈空気〉が出てこなくて」
小林「そうなんです」
土屋「説明しようもないし、あたりまえの現象なんですよ。空気を通して振動を録音するのがどれだけ大事なのかって話ですよね。やっぱり力がある。いまは音楽を始めようと思ったら(機材などが)なんでもある時代だから、そのなかで一番自分に都合がいい、便利なものを使っちゃう。昔は僕らもそうやってきた。デジタルが出てきてからは毎日が実験でしたよ。だから、そこはもう自分で経験してもらえればいい。それも誠意だよね。ひと手間かけるのも、便利さの恩恵に被るのも、僕らの誠意の問題だと思う」