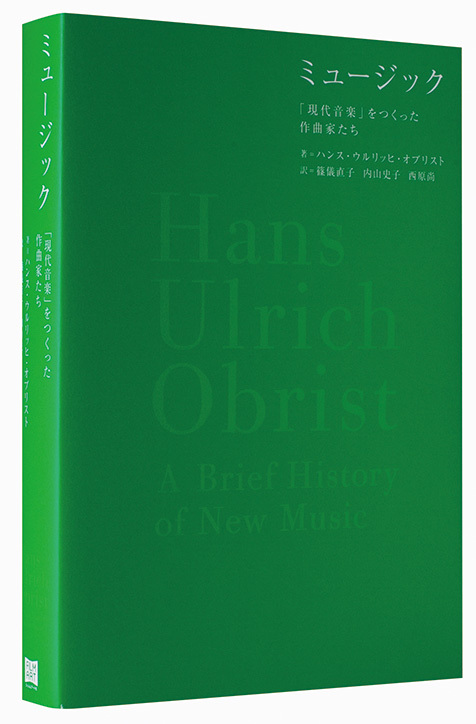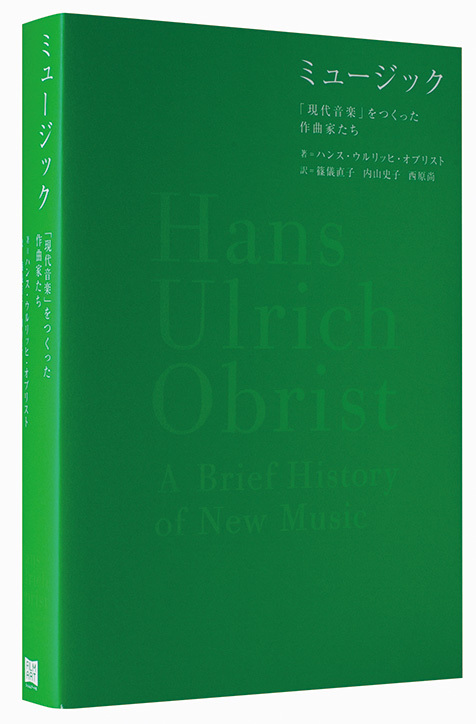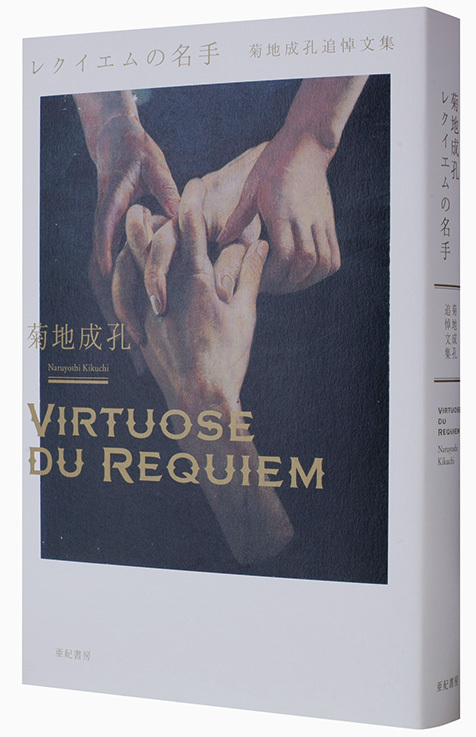消尽される声/響き合う他者の声に
「A Brief History of New Music」との原題を持ち、たぶんものすごく悩んだ末に削りに削ってこれだと決めて、意外にも編集・営業会議を通過してしまった『ミュージック』なるタイトルの本と、やたらと持って回ったプレ=テクスト――文字どおりテクストの「前」におかれているもの、の意と、口実、の意と――を持つ追悼文集を集めた 『レクイエムの名手 菊地成孔追悼文集』と、およそ隔たった二冊の本がひとつところで扱われるのは、おそらく刊行された時期がほぼおなじであることと、本誌の編集者の気分、もしくは茶目っ気、もしくは意地悪によっている(はずだ)。
『ミュージック』の副題は「「現代音楽」をつくった作曲家たち」。17人の音楽家へのインタヴュー集。集められた音楽家たるや、いわゆる「現代音楽」の範囲から微妙に逸脱する名を加えている。シュトックハウゼン、ブーレーズ、クセナキスはど真ん中。アシュリー、オリヴェロス、ライリー、ライヒも問題なし。ちょっと微妙なのがイーノ、コンラッド、ニブロック。じゃ、これはどうだ。アート・リンゼイ、クラフトワーク、カエターノ・ヴェローゾ、オノ・ヨーコ(折しも東京都現代美術館ではYOKO ONO:FROM MY WINDOWが開催されている)。これらの名をひっくるめて 「現代音楽」「作曲家」というのはムリがある。
そうだ、ムリがある。だが、だ。じゃあ何と呼ぶ? 編集会議であがったのはこんなところかもしれない(邪推?)。いや、もっとひねって、みんな「現代音楽」じゃないっすか?と誰かが発言したかもしれない。何年か前、試験答案に「浜崎あゆみのような現代音楽」と書いてあったのにのけぞったわたしは、ここにユーモアなのかイロニーなのか 「天然」なのかわからないが、一種の挑戦をみる。暗黙の了解でなりたっていた 「現代音楽/コンテンポラリー・ミュージック」をこうやってつかってしまうことの(暴)力を。さらに、こうした「現代音楽」本を手にとる人たちに、アート・リンゼイやらカエターノ・ヴェローゾやらを注入してしまう戦略というのもアリ。おそらく逆をする(カエターノのファンにカーターやベイルを聴かせる)よりは広がるんじゃなかろうか、との音楽への善意からか。もともとそうしたジャンル的発想がないものに仮想敵のような線引きをせざるをえないところが、ちょっと悲しかったりもしないではない。
他方、菊地成孔の『レクイエム』は、有名無名の人びとが亡くなったとき、依頼されてもされなくても勝手に語ったり書いたりした追悼文を集めたもので、たとえば埴谷雄高『戦後の先行者たち』(影書房)、吉本隆明『追悼私記』(筑摩書房)、磯崎新『挽歌集』(白水社)とはかなりおもむきが異なっている。いい意味でも悪い意味でも。追悼文なるものではおそらく遠ざけられるであろう饒舌さや脱線が(いつものように?)紛れこんでいるし、あるテンションの高さが故意にしくまれているともみえる。そこには菊地成孔自身が抱いている死へのアンビヴァレンツが云々などと言う気はさらさらなく、ただこの音楽家にして文筆家が生/死なるものと不在となった固有名と身体をとおして、パフォーマンスをくりひろげているさまが確認しておけばいい。誰の名があがっているかは本そのものの目次をひらいていただければ良かろう。自分でみてみるたのしみもちゃんと残しておかなくては。
で、これら2冊についていえば、かたちは違うけれども、中心となる人物のまわりに他者の声が他者の影(亡霊・イメージ)が召喚されるのである。『ミュージック』は著者ハンス・ウルリッヒ・オブリストに面して音楽家たちがことばをくりだし、『レクイエム』はこの世からいなくなった人たちをめぐって菊地成孔がことばでたどる。一方は自らを消す方向にむかい、他方はむしろ自らを前景化させる。方向は逆かもしれない。それでも、ことばがひとつところでとどまるのではなく、他者の存在と他者のことばとともに、何かべつの空間=時間をたちあげてくる。そのはたらきの近さを、わたしはみていたのだが……如何か。あ、もうひとつ。両方ともかなりおもしろい。ぱらっとひらいて、ついつい何ページが読んでしまって、いかんいかんとなったりもし……。