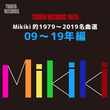〈1人の強い熱こそが物事を新しく進めるんだと思う〉
A PAGE OF PUNKに学んだこと、提示し続けた先の興奮
――ヤブさんのリスナーとしての遍歴も知りたいです。海外の音楽への入り口は?
ヤブ「たぶん最初に自分で買った洋楽のCDは……高1のときのタヒチ80のファースト『Puzzle』のような気がします。」
――へえ! じゃあパンクやロック、いわゆるうるさい音楽を聴くきっかけになったのは?
ヤブ「それ自体はもう少し前ですね。中2の時にミッシェル・ガン・エレファントの“Out Blues”という曲にワッとなったんです。いまだにミッシェルでいちばん好きな曲ですね。ちょっと自分の趣向を決めた曲のような気もします。でも、それと同時に当時好きだった女の子の影響でR・ケリーとか甘々のR&Bも聴いていたんですよ。その流れで2パックとかヒップホップも聴くようになった。日本のヒップホップも聴いてましたね。ヒップホップに飽きてきたのはカニエ・ウエストが出てきたあたりで、そこからは完全にパンクばっかりになったんです」
――ヒップホップに飽きたのはどうしてなんですか? カニエの登場はセンセーショナルだったと思うんですよ。
ヤブ「自分でバンドをやりはじめたからだと思います。それまではバンドに興味なかったし、自分がなにか音楽をやることを考えたこともなかった。ただ友達の五十嵐サブロー※という奴から〈やってみない?〉と言われて気軽に受けてみた。そいつもちょっと変な奴で、普通は高校生だったらコピーから始めると思うんですけど〈いきなりオリジナルをやろう〉と言っていたんです。だから僕はコピー・バンドをやったことがなくて。パンクに没頭したのも、自分がやりはじめたという理由だけのように思います。もし自分でバンドをやってなかったらパンク好きにはならなかったかもしれない」
※ 『FUCK FOREVER』や“恋人はアナキスト”などSEVENTEEN AGAiNの作品のエンジニアも務めている
――じゃあ、最初のバンドもパンクだったんですか?
ヤブ「なんていうんですかね。その最初のバンドは〈尾崎豊を3倍速にしたバンド〉というコンセプトがあったんです(笑)。当時、周りはコピー・バンドばかりで、オリジナルの曲をやってもまったくウケなかったんですよね。だったら曲が速ければ盛り上がるんじゃないかという理由で」
――自分の音楽を明確にパンクだと認識したのは、なにかきっかけがあったんですか?
ヤブ「それはA PAGE OF PUNKでギターを弾くようになってからだと思います。21歳のときなんで2006年くらいですかね。僕が20歳前の頃〈SET YOU FREE〉※1によく行ってたんです。2003年頃で、銀杏BOYZも出てたし、DASHBOARDやIdol Punchも出てましたね。そうしていくうちに西荻窪のWATTSに出会うんです。WATTSでDASHBOARDが毎月企画をやっていて、ちょうどその時期にSTIFFEEN※2からFruityやNuts & Milkがリイシューされたんです。それらのバンドもWATTSでやっていたらしいという情報を聞いて、WATTSに通うようになった。で、DASHBOARDの企画には毎回A PAGE OF PUNKが出てて、僕にとってA PAGE OF PUNKは物凄く新鮮だったんですよ。その頃のWATTS周辺のシーンには、Fruityのようにソウルやスカが混ざっていたり、DASHBOARDみたいにファンクやニューウェイヴが混ざっていたり、ストレンジなサウンドのパンクがたくさんいたんですが、そんななかA PAGE OF PUNKは超しょぼくてどストレートなパンク・バンドで、〈この人たちは1周回ってマジでスゴイぞ!〉となった。当時マイナー・スレットや80年代のハードコアも聴いていたうえで、A PAGE OF PUNKはハードコアではないのに、ハードコアのバンドよりも曲が速いし、複雑なことは特になにもしていないのに、いちばん変わっているというバンドで、僕にとってカリスマ的な在だったんですよ」
※1 97年からスタートし、現在も全国各地のライヴハウスで開催されているパンク・イヴェント
※2 KAKUBARHYTHMの角張渉と安孫子真哉が99年に始めたレーベル。安孫子のKiliKiliVilla設立に伴い活動終了
――そもそもヤブさんが西荻WATTSに魅力を感じたのは、その場がどういう場所だったからなんですか?
ヤブ「本当にいろんなバンドが出てたんですよね。似ているバンドがいなかったし、みんな変だった。ちょっと頭をひねって、変だったり新しいことをすればそれだけで良くて、自分にもやれるんじゃないかという気にさせてくれる場所でした。空間としてそう思わせてくれる場所はほかになかった」
――WATTSはどうして、みんなをそう思わせられる場所になったんですかね?
与田「あそこはもういい加減で、本当になんでもアリのフリー・スペースみたいになってた瞬間があったんだよね。ちゃんとした店長がいるとかじゃなくて、そのへんのバンドがみんなで運営しちゃっているようなノリになっていた」
――語り草になっている場所ですよね。いまの若いパンク・バンドへの影響も大きくて、THE FULL TEENZのメンバーも西荻WATTSでやっていたバンドにすごく憧れを持っているようです。
与田「当時を目の当たりにしてた人間からすると、集まってくる若い子が勝手にいろんなことをやってただけなんだけどね(笑)。そのなかで角張くんや安孫子が友達を集めて企画をやっているような感じだったと思うな。でもなぜかカオスにはならず、秩序立ってはいた。それが不思議な感じだったね」
――憧れだったA PAGE OF PIUNKにヤブさんが加入した経緯は?
ヤブ「同じ頃、A PAGE OF PUNKがイギリス・ツアーをすることになったんです。それで対バンがレザーフェイスというのを聞いて、〈マジか! ヤバすぎる!〉と思った。僕はレザーフェイスが大好きだったから、A PAGE OF PUNKのベースの(久保)勉さんに〈手伝いでもなんでもするから連れて行ってほしい〉とお願いしたら、〈良いよ、一緒に行こう〉と言ってくれたんです。最初はただ付いて行くだけだったんですけど、ツアーの2週間くらい前にギターの人が突然辞めてしまって。それで急遽僕がライヴでギターを弾くことになったんです。僕は1回だけ東京でライヴして、2回目がイギリスでした(笑)」
――イギリスでは何か所くらい回られたんですか?
ヤブ「リーズやロンドンなど8、9か所を回りましたね。そこでイギリスのパンク・シーンを見たり、その後もメンバーとして一緒に活動しながらA PAGE OF PUNKの歌詞の意味を考えたりしたことで、サウンドじゃなく自分の身としてパンクとはなんなのかを探求しはじめたんです」
――A PAGE OF PUNK以外で、当時ヤブさんが特に好きだった日本のパンク・バンドは?
ヤブ「あー、でもやっぱりA PAGE OF PUNKがいちばん好きだったんですよね。だからメンバーになれて一緒にイギリスにも行けて夢のようでした。僕にとっては、SMAPのファンが自分もSMAPに入れるくらいの喜びだったんですよ。それくらい特別な存在だし、めちゃくちゃ影響を与えてくれた存在です」
――A PAGE OF PUNKと並行してSEVENTEEN AGAiNも活動されいてたんですよね?
ヤブ「そうですね。SEVENTEEN AGAiNが2009年にファースト(『NEVER WANNA BE SEVENTEEN AGAiN』)を出す直前までだったので、24歳くらいまで入ってましたね。でもSEVENTEEN AGAiNは、大澤くんと遊びで始めたバンドでしたし、いまみたいな活動になったのはファーストを出して以降です」
――A PAGE OF PUNKに加入してパンクについてより深く考えるようになった結果、その後のSEVENTEEN AGAiNの活動にも変化が起きましたか?
ヤブ「歌詞というものについてすごく考えるようになって、ちゃんと筋を通したものにしようと強く思いました。それはA PAGE OF PUNKの経験を通じて構築されたものだと思います。A PAGE OF PUNKの勉さんは本当に音楽をかたっぱしから掘り下げる人で、70年代から80年代のパンク、パワー・ポップだったり、ネオアコや同時代のインディーの良いレコードをたくさん教えてくれましたね。SEVENTEEN AGAiNのサウンドは歌詞とは別のヴェクトルで構築しています。サウンドはそのときどきで好きな音楽の変換でしかない。僕らが好きなサウンドはアルバム制作の時期ごとに変わっているんですけど、それをそのまま発するんじゃなくて、ちゃんと自分のなかで消化して、それらを知らない人に響かせるには、どういう解釈をしてどう変換したうえで発すればいいのかという挑戦を毎回しています」
――では、サウンド面でもっとも影響を与えた存在は?
ヤブ「僕らの世代ではやっぱりGOING STEADYの存在は大きいです。彼らもメンバー全員、音楽的にはめちゃくちゃ雑食な人たちだったじゃないですか。自分たちがやっているサウンドは筋が通っているんだけど、各々が好きなサウンドはそれとは別にいっぱいあるという部分で、僕らの世代にとってはそれが手掛かりになった部分は大きいです」
――その面はまさにSEVENTEEN AGAiNに受け継がれていますね。
ヤブ「あと彼らはたぶんあの時代のどのバンドよりもスリリングだったんですよね。次にどう転ぶかわからない動き方をしていて、そこから目が離せなかった。想像ですけれど、リアルタイムのストーン・ローゼズやラーズ、もっと振り返るとセックス・ピストルズやクラッシュと同等のスリリングさをあの頃のGOING STEADYは持っていたんじゃないかな」
与田「そうかもしれないいね。それはたぶんハイスタがトイズファクトリーからPIZZA OF DEATHに移った瞬間、ブランキー(・ジェット・シティ)の3作目(『C.B.Jim』)から解散まで、ミッシェル(・ガン・エレファント)が『ギヤ・ブルーズ』前夜に加速しはじめた頃とか、そういう感覚がGOING STEADYにはあったと思う」

――与田さんはSEVENTEEN AGAiNにそのスリリングさを見ますか?
与田「いつスリリングな物語が点火するのだろうかと思って見ていますね」
ヤブ「ハハハ!」
与田「もちろんいまもそれがないわけじゃないし、メンバー個々のキャラクターも最高に立っている。でも、そろそろバンドが〈こうなりたい〉という方向に動いても良いんじゃないかなとも思う。いままでさんざん嘘をつかない活動をして、間違っていないと思うことはすべて受けてきて場数を踏んで、その結果いまのSEVENTEEN AGAiNの支持のされ方がある。2016年はその次のステップを考える年にすべきなんじゃないかと思っているんだよね。単純にそろそろ立場を交換したい。ヤブくんがKiliKiliVillaにいることで俺たちはものすごく前進することができたし、得たものは大きい。じゃあ次はKiliKiliVillaというチームがヤブくんとSEVENTEEN AGAiNになにができるかを考えて、返していきたいんだよ。この2016年はそういう1年にしたいし、その道筋を考えていきたいんだ」
ヤブ「いやはや、もう本当に光栄です。SEVENTEEN AGAiNとKiliKiliVillaの間には大局的に見ると共通する〈正しさ〉があると思うんです。それが合っているか間違っているかではなくて〈これが正しいんだよ〉と提示することを楽しみながらやっている。KiliKiliVillaのほかのバンドと話していても、みんな似たスタンスを持っていると思う。中心で安孫子さんが強いアティテュードを持ちつつ、みんないろいろ嗜好は違うんだけど、結果的に同じ方向を見ているというのがおもしろい。ナショナリズムにならずにコミュニティーになってますよね。リスナーとしての印象ですけど、海外のインディー・レーベルだと、クリエイションとかもそうだったんじゃないかなと思うんですよ」
与田「クリエイションはそうだよね。強力なコミュニティーを88年から91年くらいまでに作ったことで、その後の10年があり、オアシスが出てくるわけだから」
――遡れば80年代のファクトリーもそうですよね。
ヤブ「そうそう、ファクトリーがあっての現在のキャプチャード・トラックスだとも思うんですよね」
与田「バーガーも完全にそういう繋がりでやってるしね」
ヤブ「もともとはめちゃくちゃ狭いコミュニティーからスタートしてますからね」
与田「バーガーはただの音楽オタクのショーン・ボーマンがカセットを出したいというところから始まってる。それがネットワークを広げ、大きなレーベルになっていったのは、音楽を通じて話のできる信頼関係がバンドとの間にあったからだろうね」
★ヤブユウタによる、バーガーのショーン・ボーマンへのインタヴュー
ヤブ「いまの日本でそういう存在がいくつかあるかわからないですけど、KiliKiliVillaはコミュニティーとしての面も鮮明に打ち出せているから注目されているのかなと思うんですよ」
与田「安孫子が出す/出さないを決めているだけなんだけどね」
ヤブ「でも、ある1人の強い熱こそが物事を新しく進めるんだろうなと思うんですよ。たとえばアイスエイジが日本で盛り上がったのはBIG LOVEの仲(真史)さんが、まだ日本で誰も知らない段階であれだけ推しまくったからだと思うんです。NOT WONKがいまみたいに知られたのもその結晶だろうし、個々人が勝手に盛り上がった結果、彼らは広まっていった」
――ただ、NOT WONKを広めた第一人者はヤブさんですよね。NOT WONKの加藤さんが2013年の〈MATSURI〉でヤブさんに自主制作CD-Rを渡して、ヤブさんがそのCDの感想をツイートしたことがきっかけだった。
祭の時に北海道からやって来た18才の男の子にデモを頂いて今聞いてる。NOT WONKというバンド。
— ヤブソン (@yabuson) 2013, 10月 17
凄く良い!恐縮ながらジャケに僕等の写真を錚々たる面子に混じって使ってくれてます。北海道本当に凄いセンスあるバンドどんどん出てくるなぁ。 pic.twitter.com/hugVEGVghm
与田「そうだね(笑)」
ヤブ「僕は自分自身のことを、やる側よりリスナーとしての側面が強いと思っているんです。なにかを発する立場というより、いまだに受け手側のフィーリングが強いというか。ということを考えると、バンドがなにかすごく斬新なことをやっていたり、強いメッセージを発していたりしても、それに意味を付けるのは第三者にしかできないと思うんです。作ってる側は自分で自分の説明はできたとしても、それ以上の意味合いや色を付けることはできない。聴く人の答えはそれぞれにあるじゃないですか。だからSEVENTEEN AGAiNのアルバムについても、僕がアルバムのなかで出した答えを受けて、ひとりひとりがそれぞれにまた違う答えを出してもらいたいんです」
――それに対してヤブさんはテクニカルでもあると思うんです。“リプレイスメンツ”での〈代替品じゃないぜ〉という叫びは、〈どうせ代替品なんだからとっとと差し替えてくれよ〉という軽やかなニヒリズムとも捉えられる。聴き手の解釈の自由を担保するためにスキルを駆使されている気がします。
与田「ある種のリテラシーを必要とする表現だよね。だからそれをどう飛び越えていくかだよね」
ヤブ「飛び越えられる人とそうでない人の違いがなんなのかを考えると、それは〈平気で間違えられること〉という気がするんですよ。ちゃんと間違えられるかという点はすごく重要かもしれない。与田さんに近い人だと峯田(和伸)さんだったり。彼は完全に間違っていることもしますよね。加えて、合っているのか間違っているのか微妙なリテラシーも垣間見せるから、受け手はその表現を信用して良いんだか悪いんだかわからなくなる。それがスリリングさですよね。間違っている奴のほうが魅力的だし、峯田さんは打率1割のホームラン王みたいに、ほとんどは間違ってるのに、たまにめちゃくちゃ正しいことも言うんですよね。銀杏BOYZの今度リリースされるDVD(『愛地獄』)に〈どうかこの世界がひとつになれませんように〉というキャッチコピーが付いているんでけど、これはすごく正しいじゃないですか」
与田「そうだね(笑)。正しい」
ヤブ「それは『少数の脅威』のテーマとも似てる気がしてて、さまざまなことを一色に染めようとする動きや、 強要しようとする力に対しての答えになっていると思うんです。それがどれだけの規模に伝わるのかわからないけれど、それでも提示し続けなくてはならないと思うんです。わかる人にしか伝わらないことをやっていても意味がないし、きっとおもしろくもならない。結果として伝わる規模が10000人であるか100人であるかは問題じゃなくて、そこをめざし続けることだけが可能性や手掛かりになるのかもしれない。だって僕らが2009年に『NEVER WANNA BE SEVENTEEN AGAiN』を出したときは、NOT WONKの加藤くんなんて13か14歳くらいですよ。THE SLEEPING AIDES & RAZORBLADESのシラハマ(ロバスミ)くんが加藤くんにそのCDを貸して、加藤くんが聴いて特別なものを感じてくれた。そして彼らがバンドを始め、同じイヴェントやツアーで一緒にライヴができて、今度は僕が彼らを観て興奮できるという事実だけ取っても、それは僕がバンドをやりはじめたときには想像すらできないような出来事です。傍から見れば、取るに足らない出来事なのかもしれない。けれども僕にとっては何物にも代え難い、これまでに得ることのできた成果ですし、これ以上ない可能性だと思います」