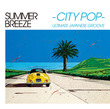人間性をさらしたバンドのドキュメンタリーを音楽に転じることで〈日常〉をレペゼン。この4人だけの温度感を持つオルタナティヴなサウンドが、いま高らかに鳴り響く!
俺たちの必殺技
The BONEZの新作は、まずそのアートワークが興味深い。JESSE(ヴォーカル/ギター)、NAKA(ギター)、T$UYO$HI(ベース)、ZAX(ドラムス)と、ジャケに初めてメンバーの顔が描かれている。The BONEZはこの4人が音楽を掻き鳴らしているんだぞ、と主張しているようだ。音楽の前に人間ありき、非日常の前に日常ありき――それを具現化した作品がこの『To a person that may save someone』(誰かを救えるであろう君へ)である。
「俺の親父(Char)は70年代を生きてきたから、ああいう音楽になるわけで。で、俺らは90年代をオンタイムで生きてきたから、スマッシング・パンプキンズの初来日公演に行けたり、リンプ・ビズキットが来日したときにBLOODY IMITATION SOCIETY(日本のミクスチャー・バンドの草分け的な存在)が前座をやったのを観てたりね。それに、俺は2000年代に(RIZEで)デビューしているから、P.O.D.と(シーンに登場した時代背景は)変わらないわけよ。今回のアルバムは、そんなふうにあたりまえに受けてきた刺激を出すこと、それと〈日常〉をレペゼンした作品にしようと。〈俺らの日常、ヤバくね?〉と言えるバンドになれたらいいなと」(JESSE)。
「レコーディングや曲作りも日常だし、歌録りも、JESSEの娘がヴォーカル・ブースに一緒にいる。それが普通なんだよね。デイヴ・グロールが初監督を務めたドキュメンタリー映画(2013年の『Sound City: Real To Reel』)を観たときに、The BONEZに近いものを感じて。メンバーが亡くなって、新しいバンドを始めたデイヴ・グロールからすごくエネルギーをもらえたし。そのドキュメンタリーで、デイヴが娘に誘われて一緒にプールで遊んでいる間に、ほかのメンバーはコーラスを録ったりしてるんですよ。その感じがカッコイイと。The BONEZの今回のアルバムの初回盤にもツアーのドキュメンタリー映像が付くんですけど、ただの人間ドラマなんですよ、そこにあるのは。ただ、観ればThe BONEZのことをよりわかってもらえると思うし、とにかく(自分たちが)楽しそうっていう(笑)」(T$UYO$HI)。
前回のミニ・アルバム『Beginning』収録の“Ray”は〈一条の光〉という曲名通り、一点に向かって猪突猛進に突き進むラウドなアレンジだった。だが、今作の冒頭を飾る表題曲は力強さと優しさを兼ね備え、リスナーを包み込むような曲調に仕上がっている。あきらかに前作とは何かが違う。
「写真ではベロを出してたりとか、JESSEはヤンチャなイメージがあるかもしれないけど、それだけじゃないから。人に頼られてるし、自分のことだけじゃなく、いつも誰かのことを世話してる。基本、JESSEは優しい。そういう、俺が知ってるメンバーの姿を音に出そうと。The BONEZの等身大というか、人間性が出てる曲を作りたくなった。表題曲はメンバー4人の色が一番出てると思う」(T$UYO$HI)。
〈日常〉に足を付け、自身の人間味をサウンドに落とし込む。今作はバンドに対する理解度がメンバー各々で深まり、加えて自分たちの個性がどこにあるのかを模索し続けた結果の産物なのかもしれない。
「俺たちの必殺技は何だろうと、ずっと考えてましたね。ほかのアーティストと対バンすることで、あいつらにはない部分が俺たちにはあるぞ、ってだんだん見えてきて。JESSEのポジティヴさ、ZAXの動物的なリズム、そこに若干、俺とNAKAのウジウジしたエモさが乗るみたいな(笑)。今回はこの4人が活きる曲作りを意識しました」(T$UYO$HI)。
前作のインタヴューの際、T$UYO$HIは〈RIZEとの差別化を図るため、JESSEの歌をもっと聴かせたい〉と発言していたが、今作ではJESSEがラップを解禁したことも大きなトピックだ。ラップと歌メロを自在に往来するヴォーカルのアプローチは、彼特有の必殺技と言っていい。
「いまの俺のラップや歌い方が一番ナチュラルだし、アコギを渡されても同じように歌えるからね。そういうものが作れたことで、ものすごく自信に繋がった。“1905”のグランジっぽさなんて、そういう曲は昔から好きなんだけど、ちゃんとやれたことがなくて。今回フッとやってみたら、自分でも大好きな曲が出来ちゃった」(JESSE)。
〈日常〉というものの凄さ
また、“Paper crane”は和的なギター・フレーズがおもしろく、従来のバンド・カラーとはちょっと異なるキャッチーな魅力を放っている。歌詞では〈KAMIDANOMI〉〈OMOTENASHI〉と日本語を入れた遊び心もいいフックになっている。
「その曲は、バンドで合宿に行ったときに、NAKAが最初にベースで弾き出したんですよ。それからパート・チェンジして作ったものですね。歌詞が入ったことで、さらに〈和〉っぽさに拍車をかけたと思う。俺の解釈だと、NAKAのレッド・ホット・チリ・ペッパーズ好きが出た印象ですね」(T$UYO$HI)。
砂煙を撒き散らして突っ走るような、Hiro Fujitaをフィーチャーした熱きロック・チューン“Revolution”から、静かに腰を据えてじっくり語りかけてくるような“Waking up”まで、『To a person that may save someone』には多彩な楽曲が収録されている。とはいえ、どんなアレンジであれ胸にスッと飛び込んでくるという点が共通。もっと言えば、一曲一曲から人間の体温が感じられ、その温度の違いが楽曲に豊かな表情を生んでいる。
「それは嬉しいですね。アッパーな曲も好きだし、聴かせる曲も好きなんだけど、今回は、その流れを楽しめるアルバムだと思うんですよ。The BONEZはわかりやすくカテゴライズできない人たちだと思うから、それも自然に出てるんじゃないかな。このアルバムは、音質も無機質じゃないんだよね。立体感があるし、〈こういう音質にしたい〉と思っていたものがやっと出来た。メンバーだけではなく、エンジニアを含めて、いろんな歯車が噛み合ってきた感じはありますね」(T$UYO$HI)。
新作のキーワードとなり、取材中もメンバーの口からたびたび出てきた〈日常〉という言葉。そこに意識が向いたのは、人間関係について歌った先行曲“Friends”の存在が大きい。
「この曲を書いてるときに、メンバー間がギクシャクしてたんですよ。〈こういうことを言ったら、どう思われるのかな?〉とか、お互いに気を遣ってて。だけど、それが俺たちの関係性をジャマしていたのかなと。伝えたいことがあるなら言えばいいじゃん、話せばいいじゃんって。この曲でピュアなものをブワーッと出せた気がする。だから、ほかの曲たちも背伸びせずに書けたのかなと。この曲のおかげで、〈日常〉というものの凄さに気付けたんですよね」(JESSE)。
The BONEZ TOUR 2016 「TO A PERSON THAT MAY SAVE SOMEONE」開催!
日程/会場:
5月6日(金)大阪・梅田 CLUB QUATTRO
5月7日(土)岡山・IMAGE
5月12日(木)広島・cave-be
5月13日(金)福岡・Drum Be-1
5月15日(日)香川・高松 DIME
5月20日(金)新潟・CLUB RIVERST
6月3日(金)宮城・仙台 darwin
6月5日(日)北海道・札幌 BESSIE HALL
6月10日(金)愛知・名古屋 E.L.L
7月15日(金)東京・渋谷 TSUTAYA O-EAST