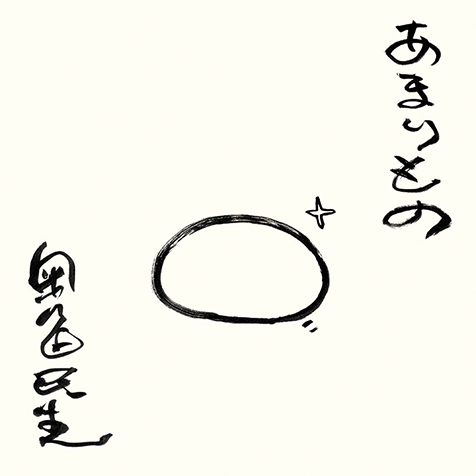トンでもないバンドが結成された。菊地成孔率いるdCprGの正式メンバーにして、2013年に傑作ソロ・アルバム『シャーマン狩り』も発表している小田朋美(ヴォーカル、キーボード)に、スケールの大きなオーケストレーションによって美しい歌世界を描くユニットであるものんくるの角田隆太(ベース)、そして鈴木勲や日野皓正らレジェンダリーなジャズ・ミュージシャンたちと若くして共演を果たし、過去に発表された2枚のリーダー・アルバムも高く評価された井上銘(ギター)。さらに、日本ジャズ界の神童として注目を集め、テイラー・マクファーリンとも手合せしている石若駿(ドラムス)に、バークリー音楽院に留学後、自身の象眠舎(旧:小西遼ラージアンサンブル)を中心に精力的な活動を展開しているリーダーの小西遼(サックスほか)――若く、有り余る才能と新時代のセンスを兼ね備えた5人による新バンド、CRCK/LCKS(クラックラックス)だ。
彼らの初音源集となるミニ・アルバム『CRCK/LCKS』には、他に似たもののない音が広がっている。ポップではあるけれどフリーキー、緻密で複雑、それでいてエモーショナル。そして、そうした形容詞をいくら並べたところで、彼らの音楽世界を完全に説明することはできない。インタヴューは2016年3月31日、六本木VARIT.で行われたライヴの話から始まった。
バンドとして継続していく意識はなかった
――2016年の5月で結成から1年になるわけですけど、これまでライヴは何回やったんですか?
小西遼「この前(3月31日のステージ)で5回目です。レコーディングが終わって初めてのライヴだったので、いい感じだったと思いますね。曲に対する理解も深まったなかでのパフォーマンスで、再現音楽に終わらないものができたんじゃないかと。(石若)駿とも話してたんですけど、どの曲にも伸びしろがあるんですよ。曲が生きているというか、レコーディングが終わってもまだ他の形で展開していく可能性がある」
――メンバーそれぞれ多忙な方たちばかりだし、ライヴのスケジュールを合わせるのも大変なんじゃないですか。
小西「めちゃくちゃ大変ですね(笑)。駿がいちばん忙しいので、彼の日程を最初に訊いて、それからみんなで合わせる感じ」
石若駿「僕、ジャズ以外でこういう形のバンドをやるのが初めてで。演奏する場所もこれまでやったことのない所ばかりで、刺激があるんですよ。それぞれ個人の活動を気にしていた人たちが集まっているので、すごく楽しくて」
――結成されたのが2015年5月で、6月には菊地成孔さん主催のイヴェント〈モダンジャズディスコティーク〉で初ライヴをやっていますよね。
小西「僕と(小田)朋美、それとベーアさん(ディレクターの阿部淳)というメンツで呑んでたんですよ。ベーアさんは角田(隆太)がやってるものんくるのファースト・アルバムや朋美の『シャーマン狩り』ではディレクターもやってたし、いまのCRCK/LCKSのメンバーの活動をすべてチェックしていて。それでベーアさんから〈菊地(成孔)さん主催のイヴェントで何かやらないか〉と声をかけてもらったんです。その時に声をかけたのがいまのメンツで、やってみたらものすごく楽しくて」
小田朋美「うん、すごく楽しかったけど、まだ継続したバンドとしてやっていこうという意識はなかった」
阿部淳「イヴェント前のリハの後、小西と角田から〈このバンド、録音したほうがいいっすよ〉という打診が来て。形になるのであればぜひ(音源を)作りたいと思っていたし、どうやって口説こうか?と思ってたんですよ(笑)。〈お、やる気だ〉と」
――角田さんと小西さんのなかではリハの段階で手応えがあったということですか。
小西「最初に出来たのが“Goodbye Girl”という曲だったんですけど、初めてみんなで(音を)合わせた時、〈やべえ曲ができた!〉という感覚があって」
――じゃあ、1回目のライヴからジャム・セッション的なものではなく、きっちり曲を組み立てていこうという方向性はあったわけですね。
小西「そうですね。それぞれリーダーでやってる人たちなので、きちんと曲をまとめてからライヴをやろうというのはありました。菊地さんのイヴェントだからヘタなことはできないということもあったし」
――それぞれ古いお付き合いなんですか? 井上さんと石若さんは高校生の頃からの知り合いだそうですけど。
小西「角田は大学の時からの知り合いで、(井上)銘はバークリーで一緒。いちばん新しいのは(小田)朋美かな」
小田「そうそう。私、ジャズじゃないですからね。銘くんとはこのバンドで初めて会ったし、角田くんは以前同じレーベルからアルバムを出したこともあったけど、いまみたいにガッツリ一緒にやったことはなかった。駿くんとは大学が1年だけ被っていて、授業が一緒だったこともありました」
石若「インプロの授業。(小田は)当時からブッ飛んでましたよ(笑)」
小西「だから、それぞれ顔見知りではあったし、噂も聞いていたけど、密にやったのはこのバンドが初めてというメンバーが多いんですよ」
――それにしてもすごいメンバーですよね。ライヴを観た時にも思ったんですけど、これだけ錚々たるメンバーが揃ったバンドはなかなかないんじゃないかと。
角田隆太「それぞれの美学というか音楽的な目の付けどころが、上手い具合に重なってたりズレてたりして、思いのほかこの5人として機能していた印象があります」
小西「そうだね。これだけのメンバーだからおもしろいことにはなるだろうけど、一発限りの企画モノになる可能性も十分あった。でも、そうはならなかった」
〈ポップスをやる〉ことに重点は置いていない
――〈この5人でやるんだったら、こういう方向性の音にしよう〉というような話はしたんですか。
小西「それが一切してないんです」
小田「話す前から音を出してましたからね」
――〈ジャズじゃないものをやろう〉というわけではなかった?
小西「そのへんを説明するのが難しいんですよね。どちらかというと、〈歌モノをやろう〉という意識。それぞれ作曲や編曲をやってるメンバーだし、おもしろいものが出来るんじゃないかと。〈ジャズ以外のものをやろう〉ということではなく、僕の場合はポップスも大好きなので、なんとなく、ポップなものにしたいという気持ちはありました」
石若「みんなが曲を持ち寄って、アレンジのアイデアを出していくなかで、それぞれが持っていたジャズ以外のバックグラウンドが自然と積み上がっていったんだと思う」
井上銘「あと、この5人でやる意味というものを考えて、こういう曲が出来たんじゃないかな。具体的に話し合わなくてもそういう意識が共有されていたというか」
小西「確かに。それと、ギターとキーボードというコード楽器が両方いるので、お互いの立ち位置をどうするかということは最初の段階で結構話しましたね。ジャズの場合、どちらかが演奏している時は休んでいることも多いので」
井上「でも、ポップスやR&Bだったらギターとキーボードがいるのはあたりまえだからね」
小西「そうそう。だから、ポップスやファンクではギターとキーボードがどういうふうに鳴っているのか、すごく研究しています」
――ただ、重要なのは〈ジャズのミュージシャンがポップスをやってみました〉というものではないということですよね。さっきの話にもありましたけど、もともとバックグラウンドにポップスを持っているメンバーということもあって。
小西「確かにそう思われがちだけど、それがすごくイヤだったんですよ」
井上「僕はあまりポップスを通ってこなかったので、最近勉強しています。ただ、子供の頃からTVやラジオから流れてくるJ-Popには自然と触れていたわけで、黒人にとってのブルースのように、意識的に聴いてこなくても身体のなかには自然に入っている」
小西「今回のアルバムを作るにあたって、ミックスの案を練るためにいろんな音源を聴き漁ったんですよ。ファンクやアンビエントなどいろいろ聴いたんですけど、ポップスに関しては日本語のものが中心でしたね」
――そうやって皆さんが話すなかで想定している〈日本語のポップス〉とはどういうものなんですか。
小西「高校生の時に聴いていたのは奥田民生、サンボマスター、椎名林檎、小田和正あたりかな」
石若「親世代が聴いていたユーミン、はっぴいえんどだとか」
――小田さんはMISIAがお好きなんですよね。
小田「そうですね。最初にCDを買ったのはユーミンだったけど、MISIAも好きでしたね。あと、親がカーペンターズ好きで」
小西「カーペンターズはヤバイよねえ」
小田「お兄ちゃんたちがBONNIE PINKとかミスチルが好きだったので私も聴いたり」
小西「浜崎あゆみも大好きだった! 中学の時には(作品は)結構買ってたもん」
小田「私も持ってたな。宇多田ヒカルも好きだったし。最初に買ったシングルって何だった?」
小西「(奥田民生をフィーチャーした東京スカパラダイスオーケストラの)“美しく燃える森”」
小田「ああ、いいよね! 私も大好き!」
石若「僕はX JAPANかな」
角田「俺はポケットビスケッツ(笑)」
全員「おおー(笑)」
――ポケットビスケッツはともかくとして(笑)、そういったさまざまなポップスの要素が無意識のうちに出てきて、こういう音になった?
井上「結果的にはそういうことだと思いますね」
小西「ものすごくわかりやすい形で滲み出てるかどうかはわからないけど、何らかの形で影響しているのは確かですね。影響を受けてるミュージシャン、出自とかはバラバラでも、〈ポップス〉というのがひとつの共通項になってたんだと思う」
角田「ポップスといっても広いですからね。だから、僕は今回のアルバムも特別ポップスっぽいとは思わないんです。このメンバーが集まって、自然に形にしてみたらこういうものになったという」
――〈ポップスをやる〉というコンセプトから始まったわけじゃないんですもんね。
小西「そうですね。そこに重点を置いてるわけではないですね」
井上「ただ、僕が書いた“簡単な気持ち”は逆に意図的に作りましたね。全体のバランスを見て、ポップなものを作ろうと」
小西「“簡単な気持ち”がいちばん最後に出来たんですよ。先にその他の5曲があったんですけど、銘が〈こういう曲があったほうがいいと思うんだよ〉って作ってきてくれて」
“Goodbye Girl”はいちばんCRCK/LCKSっぽい
――では、ここで今回のアルバム『CRCK/LCKS』の6曲を作者の方に解説していただきましょうか。まず、“Goodbye Girl”は小田さんの曲ですよね。かなり構成が複雑で、どんどん展開が変わっていくという。初めて聴いた時は驚きました。
小田「この曲に関しては複雑な構成のものを作りたかったというより、歌詞の内容に合わせてテンポが切り替わる構成をまず考えたんです。このバンドを始めるとき、小西くんと呑みながらいろいろ話していたんですけど、そのなかで彼の恋愛遍歴の話になったんですね。そこで聞いたものと、先に浮かんでいた〈街がある/光があるのにどうしちゃったんだ/Goodbye Girl〉っていう歌詞とメロディーがパッと繋がって、めっちゃ矛盾した女の子のことを書きたくなったんです。ただ、小田朋美の名義ではこういう曲は書けなかったと思う」
――どうして?
小田「自分名義でやる時は、どうしてもどこかに自分語りをしなきゃという意識があって。でもCRCK/LCKSという名義を得たことによって、そんな気負いもなく自由に書けたんです。もちろん結果的には私の思いが反映されていますが、あくまでもフィクション的なものとして、意味が通っているのか通っていないのか絶妙なもの、近くて遠いものをめざしました。それで、ひとりの女の子が持つ二面性、ある種キメラみたいなものを描きたいと思った時に、ちょこちょこテンポが変わる曲を書いてみようと」
全員「おおー(笑)」
――なるほど、だからどんどん曲の展開が変わっていくわけか。
井上「テンポ・チェンジするごとに歌の表情が変わっていくよね。陰と陽の対比になってるというか」
小西「今回の6曲は2日間でレコーディングしたんですけど、その他にヴォーカルの一部を録り直してるんですよ。12時間ぶっ通しで」
――12時間ぶっ通し?
小西「その前にミックス作業もやっていたので、言っちゃえば18時間スタジオに籠ってたんです。“Goodbye Girl”に関しては、そこで録ったテイクと2日間のレコーディングで録ったテイクをものすごく細かく切り貼りしていて。だから、細かく聴くと歌のテンションや表情がフレーズごとに違っていて、そこがすごく活きたと思う」
小田「この5人だからこそ書けた曲だと思いますね。演奏力のあるメンバーだから成立した曲だし」
――いちばん最初に出来た曲という意味では、このバンドの原型を作った曲でもありますよね。
角田「いちばんCRCK/LCKSっぽいんじゃないかな」
小西「タイトル・ソングじゃないけど、バンドの曲」
井上「俺はこの曲がいちばん好きだな」
小田「(ボソッと)嬉しい」
――他の曲でもそうですけど、ここでも小西さんのヴォコーダーが効いてますよね。CRCK/LCKSの特徴のひとつになっているんじゃないかと。
小西「ありがとうございます。自分でも“Goodbye Girl”での立ち位置を探していて、ここはヴォコーダーだろうと」
小田「最初から言ってたよね、〈サックスの入れどころがない〉って(笑)」
小西「そうそう。だから、“Goodbye Girl”の最初のほうはほぼ何もしてないんです。錚々たる面々だし、このなかでは自分がいちばん無名なので、どう立ち振る舞うか最初は迷っていたんですけど、最近ようやく自分の立ち振る舞いが身についてきた気がしますね」
井上「アジテーターになってきたよね。それはこの前のライヴの時に思った」
小西「アジテーター兼いろんな楽器の担当。ヴォコーダーにしても調味料でいいと思っています。歌モノとして多少雰囲気も変わりますしね」
――2曲目の“いらない”は小西さんの曲で。ファンク的ではあるけれど、やっぱりいろんな展開が用意されていて、CRCK/LCKSならではの1曲ですよね。
小西「僕、この曲の歌詞みたいなことを言う女の人とは付き合えないんですけど、一方でそんな女性が僕に惚れてくれるという夢がずっとあって(笑)。すごく強気なんだけど、その裏に甘い一面があるような子が、こういうことを言うんじゃないかっていう妄想です(笑)。あと、他のメロディックな曲に対して、もうちょっとリズムと曲の雰囲気で押せるものが欲しいなと思って作りました。そこに乗る言葉はあまり重すぎないほうがいいなと思って」
――皆さんが歌詞を書くうえで、ヴォーカルである小田さんのことをイメージすることはあるんですか。
小西「歌の主人公は全員女性ですもんね」
井上「いや、“簡単な気持ち”は男だよ」
小西「あっ、男なんだ!」
小田「そういえばある時、“簡単な気持ち”は〈キャバクラ嬢にフラれる阿部さんの歌なんじゃないか〉って話になったことがあったよね(笑)。以降はそうとしか思えなくなっちゃって(笑)」
阿部「あんなに爽やかなもんじゃないよ(笑)」
小西「朋美が歌うということは念頭に置いてますけど、曲の主人公としては架空の人物を想定していますね、自分の曲の場合」
――そうやって架空の人物を生み出して、その世界をバンドで広げていけるというのは歌モノを作るうえでの楽しさでもありますよね。
小田「うん、そうですね」
小西「すごくおもしろいですよね」
――あと、この“いらない”ではASA-CHANGがゲストで入っていて。
小西「レコーディングの時に焼き芋を持って突然スタジオに来てくれたんです」
――焼き芋?
小田「そうそう、差し入れだって」
小西「ライヴを観にきてくださって、すごく気に入ってくれたんですよ。そうしたらスタジオに遊びに来てくれて。冗談で〈叩いてくださいよ~〉と言ってみたら、シェケレとボンゴを叩いてくれたんです。完璧な演奏をしてくれて、あの方なしには成立しないトラックになりましたね」
――さっきも話に出ましたけど、“簡単な気持ち”は井上さんの作詞・作曲。この曲みたいにポップで爆発力のあるものが違和感なく入っているのもこのアルバムのおもしろさですよね。
井上「それぞれの曲が出揃った時に、CRCK/LCKSの世界観が見えてきたと思ったんです。ただ、みんなの歌詞にある抽象的な感覚というのは自分のなかにはなくて、だったらその世界観に混ざるかどうかわからないけど、自分らしい曲を一度出してみようと。それで、男性が女性に対して思いを伝えたいけど伝えられないという、わりとストレートかつコミカルな歌詞を書いてみました」
小西「いま、銘が〈CRCK/LCKSの世界観に混ざるかどうかわからないけど〉って言ったけど、曲を持ってきた時はみんな同じ感じだと思う。〈この曲がCRCK/LCKSにフィットするかわからないけど、とりあえず書いてみました〉という。でも、“簡単な気持ち”は結果的にすごくこのバンドにマッチしたと思いますね」
井上「小田さんの声とすごく合ったよね。曲を作ってる時は普段一緒にやってる男性ヴォーカリストのイメージがどうしても拭えなかったんだけど、小田さんに歌ってもらったら思っていた以上に声とメロディーが合っていて。だから、歌詞は男が主人公だけど、メロディー的には女の子が歌うものだと思った」
小田「あの曲が出てきた時、自分でもすごくフィットする感覚があって、〈これ、私の曲だ!〉と思いましたね。歌詞のなかの主人公は迷走ののちに瞑想するんですけど、私も最近自分が迷走しているなあと感じて、2月に千葉の瞑想合宿に行ったりしていたので、自分のいまの状況と似たところが多いんです」
小西「このバンドの曲たちは、1曲のなかでのダイナミクスの変化が大きいんですよ。テンポ・チェンジも多いし、複雑に入り組んだ曲が多い。でも、“簡単な気持ち”はイントロからすぐに歌が始まって、テンポ・チェンジもせずに最後までガッと行く。そのあたりも他の曲とは違って、銘のセンスがアルバム全体に素敵なバランスを与えてくれています」
“クラックラックスのテーマ”で感じた一体感
――“スカル”は小田さんの曲で、作詞はなんと映画監督/詩人の園子温さん。
小田「この曲は一度、弦楽クァルテットとドラム、それと角田くんというアコースティック編成でコンサートをやった時に書き下ろしたものなんです。以前から園子温さんの〈東京ガガガ〉という路上パフォーマンスがすごくおもしろいなと思っていて、そのアーカイヴをウェブサイトで見ていたんですね。そこに掲載されていた〈スカル〉という詩があって、そこに〈すべるだけの日曜日/どこへ行こうか〉という一節があって。それを目にしたらすぐメロディーが出てきたんです。そのフレーズを1年ぐらい温めていたんですけど、アコースティック編成でコンサートをやる時に初めて形にしたんですね。私の場合、リズムのアイデアと歌詞が結び付いた時に曲をまとめることが多いんですよ」
――この曲の展開もかなり複雑ですよね。ちょっとフリーキーなイントロで始まって、ジワジワと引っ張った後に後半で一気に爆発するという。
小田「この曲は大サビが1回しか出てこないんですけど、自分のなかで作曲の形式に対するいろいろな想いもあるので、〈サビまで長くてもいいじゃん〉〈サビが1回だけでもいいじゃん〉とこういう構成にしました。もともとあの詩に惚れ込んで書いた曲なので、詩の展開に合わせていったらこういうものになったというか」
――そして“坂道と電線”は小西さんの曲で。
小西「一番僕らしいといえば僕らしい曲かな。作曲を始めた高校生の頃から、曲を作る時は先に原風景が浮かんできて、その景色を基盤に曲を積み上げていくんです。この曲の時は(東京・)下北沢の歩道橋を歩いている時にアイデアが浮かんで、それを一気に書き殴ったものを後で整理しながら曲にしていきました。僕、象眠舎っていう基本12人編成のアンサンブルでも活動をしているんですけど、そこにはヴォーカルが2人いて、僕が書いた台本を元にした朗読劇が演奏の世界観を補完していくということをやっていて。そこでは〈景色と音楽と言葉の距離〉といったことを考えてるんですけど、それとほとんど同じ意識で書いた曲ですね」
――ゆったりとしたメロウな曲調で、他の曲ともまたカラーが違いますね。
小西「僕が何かを大好きになる絶対的な条件のひとつには、〈切ない〉ということがあります。音楽であろうと絵画だろうと、どこか切なさを感じられる要素があるものはすぐ好きになっちゃう。そういうところが全面に出た曲ではありますね」
小田「懐かしさみたいなものも感じますよね。(東京の)谷中っぽいというか。この曲はヴォーカル録りの時に苦戦しましたね。スタジオを真っ暗にして録ったりしました」
小西「彼女の中にないものは出てこないですからね。朋美に僕の世界観をまったくそのまま歌ってほしいわけではないんです。朋美だからこそ歌える歌、あくまでもバンドのフィルターを通したことで生まれるいちばんいいものを形にしていきたいんです」
――ラストの“クラックラックスのテーマ”は角田さんの曲で。ものすごくポップだけど、各メンバーのソロも入っていて、バンドのテーマソングに相応しい曲ではないかと。
角田「最初のライヴのリハをやった時、小田さんが持ってきた曲があまりにすごくて打ちひしがれて帰ったんです。で、何か作ろうとなった時に思い浮かんだのがこの曲で」
小西「角田の曲は別の世界のことを書いているような感じがあって、どこか寓話っぽいんですよね。ものんくるもそうだし」
角田「彼(小西)の曲がファンタジー的だとすれば、この曲はSF的かも。どんどん石ころになっていく話というか」
小田「よく聴くとちょっと気持ち悪いけど(笑)、どこか切なさがある」
角田「いわゆる歌い手に対する当て書きではなくて、このバンドに対して当て書きをしたっていう感覚です」
井上「この曲はレコーディング2日目の最後のほうに録ったんですけど、残りの時間が本当に少なくて。あの時にバンドとしての一体感をいちばん感じましたね。そういう状況と“クラックラックスのテーマ”という曲名が相まって、ジワッとくるものがあったな。終わった後の充実感もものすごくあったし、いまでも聴くといろんなことを思い出しますね」
小田「確かにレコーディングの時にいちばん感極まったのは“クラックラックスのテーマ”だったと思う。あまりに感極まりすぎて、泣きそうになってるテイクもあったし(笑)」
――というわけで、全部で6曲。皆さん、充実感もかなりあるんじゃないですか。
小西「自分たちで言うのもナンですけど、捨て曲はないと思いますね」
小田「駿くんの曲も入れたかったけど」
井上「そうそう、最高の名曲があるんですよ」
小西「譜面が届いた時、みんな〈こいつは化け物だ!〉と驚いたぐらいの名曲で」
井上「自分が作曲する時はどこかで聴いたことのあるものを元にすることが多いけど、あの曲に関してはどこでも聴いたことがない。そういうことをできる人なんですよね」
小田「どうやってあんな曲を作ったの?」
石若「天の邪鬼に音楽を作りたい性格でして……」
井上「他にはないものをやろうとすると、ヘタをすると奇を衒ったものになっちゃうし、そこにある種の責任が生じると思うんですよ。でも、彼はその責任を持てる数少ないミュージシャンのひとりだと思う」
小西「ここにいる5人は全員自分たちが聴いてきた音楽に対するリスペクトがあるし、そこから出てきたものを自分なりに構築する努力を怠ってこなかった人たちなんですよね。だから、このバンドでやりたいことも試したいアイデアもまだまだあるし、僕らは〈もっといいものを作っていこう〉っていうだけです」
CRCK/LCKS『CRCK/LCKS』レコ発ツアー
6月16日(木)東京・月見ル君想フ
6月20日(月)名古屋・TOKUZO
6月21日(火)大阪・Live Square 2nd Line