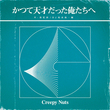敵対と(非)共存の政治学
「古いもの(貧しいもの)/新しいもの(富めるもの)」の敵対
真利子哲也の映画が(多くの場合)孕む不穏な暴力の意義を、あくまでも「政治」の次元において論じたい。彼の映画が現代日本社会をいかに現実的に批判し、その転覆を図るかを示したい。過剰な暴力を描く映画など珍しくなく、むしろ日本映画界である種の紋切型を形成している。猟奇的な連続殺人犯の狂気、喧嘩やイジメに明け暮れる不良たちの青春群像……。そうした暴力を売りにする(マッチョな?)映画群との差異を際立たせるためにも、真利子作品の政治的次元での先鋭さに注目すべきである。商業映画デビュー作である『ディストラクション・ベイビーズ』での破壊力の亢進や衝撃にしても、単に暴力描写の精度によるものではなく、政治的次元での驚嘆すべき飛躍に由来するのだ。では、真利子哲也の映画に固有の「政治」とは何か?
初期短篇『極東のマンション』(2003年)や『マリコ三十騎』(2004年)にすでに萌芽は見られた。前者の冒頭、古びた小さなアパートとその隣に立つ立派なマンションがアングルを変えつつワンカットで撮影される。真利子自身による独白は、その古いアパートの一室を一人暮らし用に借りたが、家賃は親が払い、今は家族と隣のマンションで生活していると説明する。あるいは、自分は映画をやりたいと思っているが、平凡な家庭のぬくぬくとした幸福に閉じこもっている限り、それも難しい……等々。映画中盤では、「僕は僕を壊さなくちゃいけない」との台詞が強迫観念めいて反復されるなか、真利子が自身を模した人形を破壊するシークエンスもあり、今回の新作を予告するかのようで興味深いが、ここでは次の点を強調するにとどめよう。真利子は最初の代表作の冒頭で古いアパートと新しいマンションを対比するかのように置き、自分はそのどちらにも属さないと告白するのである。『マリコ三十騎』でも似た図式が冒頭で反復され、対比されるのは、彼が通う法政大学の燦然と聳え立つ新築の高層ビルとその影のような薄汚れた学生会館である。個人的に愛着のある学館が汚い、古い、といった理由で排除されるなど許せないと真利子の独白は述べ、「ああ、どうにか共存できないものでしょうか!」との叫びで締め括られる。
こうして「古いもの/新しいもの」の対比が彼の初期2作品の構造を決定づけるが、この対比は見かけに反して自明ではない。東京において近所の古いアパートが知らぬ間に解体され、更地になった土地にかつて何が建っていたか思い出せずに終わることなど日常茶飯事である。大学構内の二つの対照的な建物の共存ならざる一時的混在にしても、映画が撮られた直後に学館が解体された以上、今や目撃不可能な光景なのだ。
その後の同作では、「気取った男女が澄ました顔で不味い飯を美味そうに食べ」る、真新しいカフェテリアを真利子自身がほぼ裸で襲撃(?)するばかりか、当時の彼にとって特別な表現メディアであった8mmフィルムの消滅が古いもの(学館)に重ね合わされてもいて、真利子の初期作品での政治は、利潤追求を第一に「気取った男女」を多幸症に導く資本主義への怒り、そうした時流にあって消滅する運命にある古いものの擁護を巡りひとまず展開される。ただし真利子作品の政治性は、古きものの大切さを訴える倫理的姿勢や懐古趣味に収まるわけではない。彼にとって重要なのは「古いもの」それ自体ではなく、あくまでも「古いもの/新しいもの」の対比(敵対)であって、だから両者の「共存」が求められる。「古いもの(貧しいもの)/新しいもの(富めるもの)」の敵対は至るところにあるが、「気取った男女」らはそれに気づかず食事にうつつを抜かす。時流はつねに後者による前者の淘汰としてあり、それが当然であるがゆえに敵対が敵対と映らない。そうした事態が現代社会で「政治」を無力にしているのではないか。
「敵対」の発見から「政治」の再開へ
真利子の最初の傑作『NINIFUNI』(2011年)では、冒頭、二人の若い男性による強盗事件が手持ちキャメラによるワンカットの長回しで撮影される。その後しばらくは犯人の一人らしき男の自動車内での孤独な生活ぶりが描かれるが、やがて彼は砂浜まで車を移動させ、練炭コンロで自殺を図る……。以上が映画の前半部分で、フェイドインされた翌朝の画面で男は死体と化して車内に座り、すぐ側に広がる砂浜では、若い女性アイドルグループのプロモーション映像(?)の撮影が開始されるだろう。前二作での「古いもの=貧しいもの/新しいもの=富めるもの」の敵対や共存(不)可能性が、ここではよりラディカルな政治性を帯びて再演される。何ら言葉を発することなく、誰にも見守られずに死ぬ一人の男と、笑顔のオジサンたちの視線を一身に浴び、過剰な明るさではしゃぎ回るアイドルたち。いずれも現代日本社会に属しながら、これら二つの領域は決して交わることがない。
そうした二つの異質な領域を何とか共存せしめ、その対比=敵対をあらわにするセンスが、真利子の映画を優れて政治的にするのだ。格差社会が問題なのは、貧者と富者が単に対立するからでなく、その対立のあいだに互いが視線を交えることさえ困難な無人の砂浜が広がるからだ。自殺者(貧者)はアイドル(富者)を視界に収めることができず、アイドルは自殺者を振り返りもしない。そのまま放置すれば「敵対」が生じる余地もなく、だから政治が空転する。逆に「敵対」を見出すことさえできれば、政治は再開されるだろう。
「暴力階級」の生成と拡張
愛媛県松山市の小さな港町で暮らす二人の兄弟が『ディストラクション~』の一応の主人公だが、兄の泰良は映画の冒頭でいきなり壮烈な喧嘩を演じたあげく繁華街に移動、しかるべき相手を見つけては問答無用で喧嘩を売り続ける。彼の行動=暴力はいかなる理由や目的も見出せないがゆえに不気味である。喧嘩に明け暮れる不良やヤクザらは、単にオスの本能(?)に基づき縄張り争いをしているだけで、彼らの暴力は良識という権力装置(コード=領土)から道を踏み外し、それを解体するかのようで別の権力装置(再領土化)の形成を目論むものでしかない。泰良によって行使される暴力はそれらと明らかに異質で、王国の領土を構築する意志など微塵もない。彼はただ至るところに「敵対」を見出すだけの(絶対的な脱領土化を推し進める)「戦争機械」である。ヤクザ、ミュージシャン、不良高校生……道を行き交う誰もが倒すべき敵となる。
こうして真利子作品は日本社会の基底に再び「敵対」を見出すのだが、その次元は暴力的に拡張されている。交わらないはずの二つの領域を強引に交差させること……それが暴力に他ならず、しかもそれ自体として暴力は感染する。「気取った男」めいた高校生が無秩序そのものであった泰良の彷徨にある種の方向性を与えようとし、なぜか泰良はそれを受け入れる。対極にあると映るその男を自分と同じ階級に属する者と見なすのだ。
『ディストラクション~』であらわになるのは、たとえば『NINIFUNI』において決定的に隔たりつつ、しかし同じ社会に(非)共存していた二つの領域、犯罪者=自殺者=(非生産的かつ悲観的な)貧者と、アイドル=快楽主義者=(生産的かつ楽観的な)富者が、実は同じ「階級」に属していたという事実ではないか。砂浜で踊るアイドルたちは、すぐ近くの自動車内で死んだ男と同様、絶望的にして暴力的、さらには貧困に喘ぐのではないか。「資本の下への社会全体の実質的な包摂」(ネグリ)の現状や帰結として、あらゆる存在が貧者かその予備軍となり、従来の階級を横断するかのような「暴力階級」(マルグリット・デュラス、廣瀬純)が台頭する。「この何ものも食い止められない暴力を生み出しているのは、まさに、現代社会に直面した子供たちの本性そのものなのよ。暴力は、それだけでひとつの階級」(岡村民夫訳『デュラス、映画を語る』)。
泰良がヤクザたちを前に無敵にして不死身なのは、彼の暴力が「現代社会に直面」するなかで生まれたものだからだろう。『極東のマンション』から何と遠くに来てしまったことか。富者でも貧者でもないと自己規定せざるを得ない一人の若者によって唱えられた呪詛の言葉、「僕は僕を壊さなくちゃいけない」が今や社会的な領野へと拡張される。社会(国家)は社会(国家)を壊さなくちゃいけない……。泰良は一匹の「戦争機械」として野に放たれ、「暴力階級」の生成と拡張、さらにはその悲惨と栄光を鮮烈なまでの強度で僕らに知らしめるのである。
真利子哲也(Tetsuya Mariko)[1981-]
1981年東京生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業。2003年『極東のマンション』2004年『マリコ三十騎』がゆうばり映画祭のほか、9映画祭で賞を獲得し国内外から高い評価を受ける。その後、冨永昌敬、松尾スズキなどの監督作品にメイキングディレクターとして参加。2007年東京藝術大学大学院映像研究科に入学。卒業制作として手がけた『イエローキッド』がバンクーバー国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭、香港国際映画祭に招待を受ける。
寄稿者プロフィール
北小路隆志(Takashi Kitakoji)
映画評論家。京都造形芸術大学准教授。著書に『王家衛的恋愛』(INFASパブリケーションズ)、共著に『映画の政治学』(青弓社)、『国境を超える現代ヨーロッパ映画250 移民・辺境・マイノリティ』(河出書房新社)など。新聞、雑誌、劇場用パンフレットなどで映画評を中心に執筆。

映画『ディストラクション・ベイビーズ』
監督・脚本:真利子哲也
脚本:喜安浩平
音楽:向井秀徳
出演:柳楽優弥/菅田将暉/小松菜奈/村上虹郎
配給:東京テアトル(2016年 日本 108分)
◎5/21(土)よりテアトル新宿ほか全国ロードショー
http://distraction-babies.com/