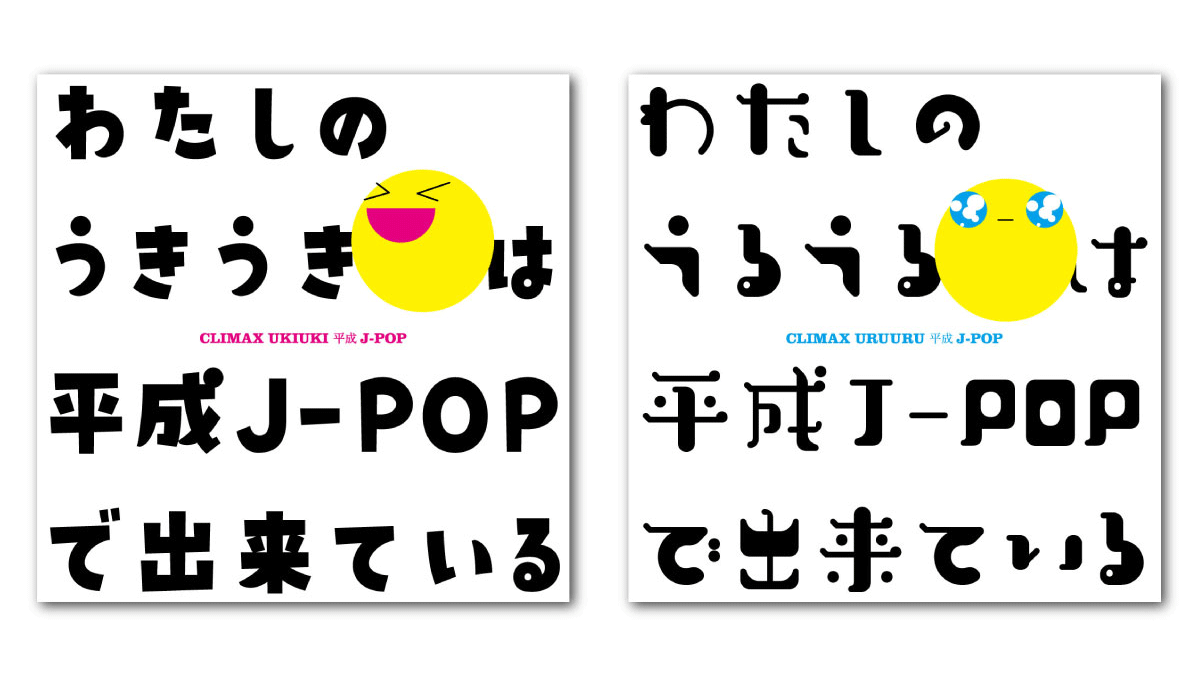家族という前提を欠いた「家族映画」の企て
いわゆる「家族についての映画」の多くが至極退屈な出来に終わるのは、それらが「家族」という前提を疑わず、その前提を担保としたうえで、そこに巻き起こる大小の波乱から崩壊、あるいはその修復や再生をドラマ化するにとどまるからだ。風来坊めいた中年女性の家族への突然の帰還が物語を始動させる辺り、往年の西部劇や『男はつらいよ』を連想させさえする、前田司郎の「ふきげんな過去」は、そんな家族映画(?)の退屈さを(ジャンルの)内側から食い破るかのような快作である。
本作にあって家族は前提ではない。(家族という)前提を破壊するのではなくて、そうした前提に頼ることなく、それでも家族の物語を紡ぐことは可能なのか……。そんな意味で、前述の中年女性が本作に持ち込む爆弾(=破壊)の主題以上に僕の関心を惹くのは、ヒロインの女子高生・果子(かこ)のかなり年齢の隔たった妹であるらしき赤ん坊(端役中の端役!)の存在である。

彼女は泣き声ひとつ立てずに母親の背中に負ぶさり続ける。「この子、大丈夫? 病気じゃないの?」と客が発した当然の疑問に対し、うちの赤ん坊は、みんなグッタリしているからね……と事も無げに応じる祖母の発言は十分笑えるものだが、これを単なるギャグと受け止めてはならない。元気に泣きわめく無邪気なもの……といった赤ん坊とその家族における役割を巡る前提が、この映画において端から存在しないのだ。部屋に寝かしつけられた妹を見守る果子の姿が固定の長回しでスリリングに捉えられる。ここでも、用事でその場を離れねばならなくなった母親に、赤ん坊なら私が見ているから、と果子が声をかけており、本来なら「面倒を見る」との意味合いを帯びるはずのその言葉が、果子にとって字義通りの「見る」となることが可笑しくもあるのだが、その永遠に続くかのような長回しがある種の戦慄へと僕らを誘う。

その赤ん坊は確実に人形か何かで、それが生きた赤ん坊であることを装おうとする演出など皆無である。顔は一瞬たりとも映されず、それは文字通りの小道具=物質に過ぎない。いまだ名前も付けられていない生まれたての赤ん坊は物言わぬモノであり、果子の眼差しも明らかにモノを見つめるそれなのだ。
名前や言語を与えられることで僕らは象徴界に参入し、晴れて人間となるが、他方でそれはモノの殺戮でもあるだろう。『ふきげんな過去』は、家族(象徴界)の根底にモノ(現実界)が無言のまま横たわり、家族とはモノの再生産と殺戮の装置であるとラディカルにも僕らに告げる。冒頭で触れた通常の家族映画の退屈さは、そんなモノの殺戮の後の世界を「前提」とするがゆえである……と今や言い換えることもできるだろう。グッタリとした不活発なモノをいつまでも凝視できる果子の眼差しだけが、本作の家族のドラマから「家族」という前提を奪い、剥き出しのドラマを出現せしめるのだ。
映画『ふきげんな過去』
監督・脚本:前田司郎 音楽:岡田徹 主題歌:佐藤奈々子「花の夜」
出演:小泉今日子/二階堂ふみ/高良健吾/兵藤公美/山田祐貴/大竹まこと/きたろう/斉木しげる/黒川芽以/梅沢昌代/板尾創路/他
配給:東京テアトル(2016年 日本 120分)
(C)2016「ふきげんな過去」製作委員会
◎6/25(土)テアトル新宿ほか全国ロードショー
http://fukigen.jp/