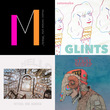NYで活動するトランぺッター、黒田卓也がコンコード移籍後初のニュー・アルバム『Zigzagger』をリリースした。ホセ・ジェイムズがプロデュースした2014年の前作『Rising Son』では、黒田が参加していた当時のホセのバンド・メンバーがそのままレコーディングに参加していたが、本作では長年活動を共にしているコーリー・キング(トロンボーン)、大林武司(フェンダー・ローズ/シンセ)、ラシャーン・カーター(ベース)、アダム・ジャクソン(ドラムス/パーカッション)から成る自身のレギュラー・バンドにチェンジ。さらに、スナーキー・パピーの一員である小川慶太(パーカッション)や、アフロビート・バンドのアンティバラス、そして日本盤ボーナス・トラックではceroも参加している。
前作にもあったネオ・ソウル色が強いビート感やエレクトリックなサウンドはそのままに、カラフルなホーンやトライバルなリズムを導入して、『Zigzagger』は黒田の最高傑作となっている。近年はDJプレミアのライヴ・バンド・プロジェクト=バッダー(THE BADDER)に参加し、〈Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2016〉ではMISIAとの共演が決定するなど、ますます注目が集まる彼に話を訊いた。
※追記
2016年12月に日本ツアーが決定!
詳細はこちら
セーフティーな曲は絶対にやりたくなかった
――前作の『Rising Son』が〈静〉だとしたら、今回の『Zigzagger』は〈動〉のアルバムという話をされてましたよね。〈動〉という意味では、今回はかなりトランペットを吹いている。
「張り切りましたね。前回は本当に時間のないなかでのレコーディングだったので、ホセが頭に立って、ホセ・バンドと手探りで作りましたから。それに比べると、今回は最初から行きたい場所や到達したい場所のイメージがあったし、メンバーもいつも演奏している仲間たちだったので、全然気持ちが違いましたね」
――前作はわりと歌ものっぽかったじゃないですか。トランペットが歌のパートのように聴こえるアルバムというか。
「確かに、インストっぽくなかったかもしれないですね」
――今回は黒田さん自身が自由に吹けるスペースを念頭に置きながら、曲を書いていった感じですか?
「メロディーに関しては、前作より主張したものを入れようと思いました。音楽をやってない人にも共有できるメロディーにして、シンプルで口ずさめるものにするというコンセプトを常に貫いてきたんですけど、今回はそれに加えて、以前よりも動いているものにするという気持ちはありました。自分がインストをやっているんだという意識もあるし、そのなかで一歩踏み込んで進化したかったというか。〈トランペットでこんなメロディーが吹けんのか!?〉という難しい動きもありましたが、自分の挑戦として入れたんです。だから、コーリー(・キング)には大変な思いをしてもらっているんですけど。トロンボーンでこんなのをよく吹けるなーって、横で見ながら思ってました(笑)」

――そういう話だと、“Little Words”と“Actors”が印象的でした。特に“Actors”はすごく吹いているじゃないですか。しかも、出している音域もかなり広い。前作はああいうのはなかったですよね。
「そうですね。ああいうガリッとした感じのサウンドは前作にはなかったです」
――今回は自分の持っている技術を、トランぺッターとしての黒田卓也を惜しみなく出している気がします。
「『Rising Son』を出してからツアーを1年間回ったことで、演奏面でも精神面でも、もう一つ上に行かなければいけないとい気持ちが前よりも強くなったんです。だから、次のアルバムでセーフティーな曲は絶対にやりたくなかった。それで、自分に課すという意味でも、メロディーをトランペットではなくキーボードで書いたんです。だから結構、(トランペットには吹きづらい箇所が多くて)大変でした。前回はトランペットで吹くことを想定しながら書いたし、実際にその範囲内で。でも今回はやりながら、〈音域的にこれは辛いな〉という部分も多かった。以前なら無理だったかもしれません」
――特にしんどかったのは?
「全部しんどいですよ(笑)。音域的には全部高いですし。“No Sign”もそうだし、ビッグバンド的な音域で吹いているところもあるから。“Actors”のサビや、“R.S.B.D”の〈タララララ~〉に、“Zigzagger”もなかなか動きが多いので。自分で書いておきながら最初はビビッてましたね。ライヴで演奏するのは無理じゃないかと思うぐらい。いまはもう大丈夫ですけど」
――インディーの頃のアルバム『Six Aces』(2013年)は、もっと普通にジャズをやってる感じでしたよね。今回は、その時よりもずっと攻めている。
「昔はただただ精一杯でした。いまは流石に、アルバムとして表現したい形があったりするので。ただ単に速くて高い音を出したいという感覚はすでにないですね。そういう意味ではインディーの頃とは様子が違うのかなと」
――なるほど。
「去年から自分で作曲をしたり、プロダクションにこだわったり、DJプレミアのバンドでツアーをやってきて。そのなかで最近思うのは、結局のところ、自分の真ん中にあるのはトランペットだということ。それを再認識した1年でしたね。そこを崩されたら黒田卓也じゃなくなるというのを、これまで以上に強く思っています」
いいミュージシャンは取り合い
――“Good Day Bad Habit”も普通に吹いているようで、よく聴くと細かいニュアンスが詰まっていますよね。
「あれは今回のアルバムで一番好きな曲です。特にピアノを入れたことで、あの曲がかなりリッチになった。ピアノと一緒にソロを録ったんですけど、(大林)武司と一緒にふわふわ動くなかで、大きい映像みたいなものをトランペットのソロで作り上げていくイメージです。その瞬間に聴こえた音に反応するという自然発生的なアドリブをやった曲なので、すごく緊張感のある演奏だったのを覚えています」
――なんとなく聴いたら緩い曲ですけど、よく聴くとテクニックが詰まっている。これはブレインフィーダーに所属しているビートメイカー、ティーブスの作品にインスパイアされたそうですね。
「そう、誰かに教えてもらって『Ardour』(ティーブスの2010年作)を買ったんですよ。キーボードやシンセをふわふわ飛ばすのが好きで、その雰囲気を伝えて人力でできるところまで持っていったのがこの曲ですね。あのふわっと消えたり出てきたりする感覚を、シンセを使うだけじゃなくて、トランペットが重なることで出せないかなと思って」
――遅いテンポの小さい音で変化を付けるのは、すごく難しいんじゃないんですか?
「いや、実は速いテンポよりもそっちのほうが得意なんですよ。落ち着いてできるから」
――へぇー。そういえば、トランペットの出音が前回と全然違いますよね。
「前作はプロダクションの段階で、わざと他の楽器よりも後ろに位置させているところもあったんですよ。トランペットの音をドライにして存在感を強めようという意図がありました。今回は、いいマイクでダークな音を録るという感じでやりましたね」
――今回の作品も、最初にプログラミングでデモを作って、それをバンド演奏に置き換えていった感じですか?
「基本は前作とまったく一緒ですね。ただ、前よりデモの完成度は高くなっていて、そろそろプロデューサーやトラックメイカーでもいけるんじゃないかと(笑)。今回は音像に関しても、どんな感じが欲しいのかのイメージがクリアにありました。デモの段階でエフェクトも乗せて、かなり凝ったものを作っていたので。メンバーからすれば、デモを聴いた段階で僕の意図がはっきり理解できたと思うんですよね」
――それをスタジオで、メンバーそれぞれに自由にやってもらったと?
「いや、わりと忠実にやってくれましたね。“R.S.B.D”の後半部分はドラムが2台になってたり、アダム(・ジャクソン)や大林くんのおもしろいアイデアをふんだんに採り入れた場面もあります」
――音を重ねたりもしてます?
「はい。プリプロもしたので、パーカッションやキーボードはスタジオに入る前に、別の小さいスタジオで入れてしまって。あとから大林くんにローズを自由に演奏してもらって、いいところを使ったりもしてます」
――曲によっては、かなりセッションしている感じもありますけど。
「(レコーディングした)日にもよりますね。アダムのドラムが動きまくっている日とまったく動かない日があって。動かない日は緻密に作ったように聴こえるけど、よく動く日はセッションしているように感じるという。彼の機嫌に翻弄されてるんですよ(笑)」
――とはいえ、前作と比べるとバンド感がすごくありますよね。
「それは確実にありますね。前作はわざとトラックっぽく仕上げて、それはそれで大成功だったんですけど、今回は全員で作り上げた感じがします。バンド・メンバーも(そういう作り方に)乗り気だったし」
――ベースとシンセ・ベースの使い分けは、どんなところを意識しています?
「音域にもよります。作った曲の音域がベースで鳴らない場合はシンセ・ベースでやってもらったり。あとはテクスチャーですね。あんまり表情を出したくないときはシンセ・ベースに頼むようにして」
――ベースも弾けるうえに、シンセ・ベースも上手い人を探すのは大変じゃないですか?
「NYだと増えてきているんですよ。20代の学生だと、両方弾けてあたりまえという感じになっている。僕らの世代だとまだ困るんですけど、少し下になるとジャズのアプローチとシンセ・ベースの両方をできる奴は結構いますよ。良くも悪くも(ロバート・)グラスパーのせいで、ジャズ・ミュージシャンでもああいうのができて当然になってますし、若い子たちもそういう音楽をやりたいと思っている。だから、両方できるベーシストが今後どんどん増えてくると思いますね」
――今回のアルバムでも、ベースのラシャーン・カーターは両方とも演奏できるし、彼のように何でもできる人が集まっているのが強みですよね。コーリー・キングもそうだし。
「気が付くとそうなりましたね。ホセのバンドにもハイブリッドな連中が多かったので、彼らとツアーを回っているうちに、〈こういう奴らが集まると、こんな景色が見えるんだ〉という感覚が癖になったというか。ローズは入るのがあたりまえ、みたいな。そういう感覚は昔の自分にはなかったと思います」
――でも、そういうメンバーを集めるのが大変ですよね。
「そうなんですよ、みんな忙しくなってきたから。でもちゃんとリクルートもしていて、若くてイイのがいるんです。最近、ザック・ミュリングスという23歳のドラマーと出会って。まだバークリーを出たばっかりだけど、これから2、3年で出てくると思いますよ。あいつはバケモノですね」
――どこで見つけたんですか?
「ジェシ・フィッシャー※が使ってたんですよ。うちの近くのレストラン・ビルに(ライヴを)観に行ったら、上手いドラマーがいるなーと。アダムは最近だとビラルのバンドに参加したりで忙しいから、(代わりに)ザックに頼んでジャズ・フェスで一緒にやってみたら、もうすごかったですね」
※NYを拠点に活動する鍵盤奏者/プロデューサー。黒田と共演する機会も多く、“Afro Blues”のリミックスも手掛けている
――いいミュージシャンは早めに押さえておかないと。
「そうそう、取り合いですよ。ホセもザックにツバつけてるらしくて。〈お前はタケシを獲ったんだから、もういいだろう〉と(笑)。コーリーはエスペランサ(・スポルディング)のツアーにも行かなくちゃだし。でも、コーリーの代わりはサックスのクレイグ・ヒルというのを見つけて、こいつがまたいいんですよ。まだソロに当たり外れはあるけど、当たった時はとんでもなくカッコイイ。あんなに太いテナーは久々ですよ」
――クレイグはどこで見つけたんですか?
「彼は友達の紹介ですね。だって、コーリーの代わりなんていないじゃないですか。別にトロンボーンが欲しいわけじゃないので」
――あ、そうなんですか?
「特にライヴでは、(自分のトランペット以外に)もう一つの声が欲しくなるんですけど、普通のトロンボーンだと大味になっちゃうから、そういうのはいらないかなと。だから、コーリー以外だと別に……」
――あんなトロンボーンは他にいないですもんね。
「黒人で上手いトロンボーン奏者は山ほどいるんですけど、やることが想像ついてしまうんですよね。ソウルフルなわかりきったフレーズをずっと吹かれて、盛り上がるとは思うけど、それだとR&Bのギグみたいになっちゃう。僕はそれより、もうちょっと深い音楽観を出してほしいんですよ。だから、それだったらギターのほうがいいですね。もう一つカラーを出せるじゃないですか、アンビエントな感じとか」
――違うカラーを出すことが重要であって、そのための楽器自体にはこだわりはないんですね。
「そうですね。もう一つのクールなヴォイスが欲しいという感じ」