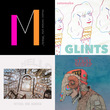トランペッターの黒田卓也がメジャーとしては3作目となるアルバム『フライ・ムーン・ダイ・スーン』をリリースする。この作品は当初4月に発売される予定だったが、新型コロナウイルスの影響で8月5日(水)に延期となったもの。前作『シグザガー』(2016年)から約4年ぶりとなるが、待った甲斐ありの最高傑作だ。
2018年2月にスタジオに入ったのをとっかかりとし、自らプログラミングしたビートに生演奏を重ねる形で2年の時間をかけて作り込んでいったこのアルバム。細部に至るまで自身で綿密に構築した曲と強力なバンド・グルーヴが表れた曲とが違和感なく混ざり合い、クールというよりはアルバム・ジャケットのようにギラギラしたところが味わえるのもこれまでと違うところだ。言うなれば、黒田卓也というアーティストの唯一無二の個性と魅力が初めて明確に立ち現れた渾身の1作。
インタビューは緊急事態宣言が発令される前の4月上旬に対面で行った。

ブルーノートからデビューして6年、順風ではなかったキャリアのその先へ
――黒田さんがアルバム『ライジング・サン』(2014年)でメジャー・デビューしてから、今年で……。
「6年ですね」
――あっという間でしたか?
「長かったですね。やっぱりブルーノートからのデビューは、自分で言うのもなんですが、けっこうな鮮烈具合だったので。あのグググっと上がって居場所とかも一気に変わったところから、いかにそれを維持するのか、いかにそれより上に行くかってことに関しての葛藤は、けっこうありました。
『ライジング・サン』はホゼ(ホセ・ジェイムス)とブルーノートに後押ししてもらえたから出せたわけですけど、自分が個人で発信していくとなったら、同じような力があるわけではないじゃないですか。そんななかでいかにモチヴェーションを保たせるか。そういう意味で長く感じましたね。決して順風ではなかった」
――とはいえ、モチヴェーションが下がるということはなかったでしょ?
「自主制作で3枚出していた頃とはやっぱり様子が違って、聴いてくれる人の数も全然違うし、いろいろ言われたりもするから、意識のレヴェルだとか到達したいクォリティーのレヴェルを上げて取り組まないと後悔に繋がる。
そのレヴェルが高くなるだけ苦労も多くなるけど、逆に言うと確かにそれがいいモチヴェーションになってましたね」
――そういう意味でまさしく今作は、意識のレヴェル、到達したいクォリティーのレヴェルを相当上げたところで作ったものだということがわかります。例えば1~2年に1作とかコンスタントに作品を発表している人だったら外しの曲を入れたりする余裕もあるんでしょうけど、黒田さんにとってこれは満を持しての作品であり、それだけに本気度の高さが伝わるというか。
「そうですね。マーケット繫ぎのアルバムではないですね」
――1作目『ライジング・サン』はモノトーンな色合いで、2作目『ジグザガー』には〈そうじゃないオレもいるよ〉というカラフルさがあった。その2作はまだ自己紹介的な側面もあったと思うんですが……。
「間違いないです。それで、今回は自己中心的な表現が終わったあとのアルバムという感覚ですね」
――だから濃いし、1曲1曲の細部にまで魂がこもっている。
「時間をかけたので。本当に細部に至るまで納得いくように作ったというか。前の2作とはコンセプトから何からまったく違う感覚でやっていました」

2年以上かけて作った、こだわりのアルバム
――3年半ぶり(当初の予定日からコロナの影響で延期となったため、実際は約4年ぶり)のアルバムですが、この3年半のいろんな経験が反映されてできたものだということがよくわかります。例えばその間にはMISIAさんやJUJUさんとの活動もありましたが、そういった仕事のなかでプロデュースやプロダクション面での感覚とスキルがアップしたというのもあるのでしょうし。
「確かにそうですね。ひとに頼まれた楽曲を自分でできる限り形にするという作業が今までの倍以上増えたことで、自ずとクォリティーが上がっていって、それが今回の自分の作品にも影響を与えることになったというのは間違いないです」
――同時にトランペッターとしても、そうした課外活動によってスタイルや見せ方の幅が広がった。
「そうですね。特に見せ方が広がりました。この料理をどの皿に乗せるかとか、そういったところにこだわるようになった。そこにとことんこだわって作れたのが、今回のアルバムの成果なのかなとも思います」
――あともうひとつ、この3年半のライブ活動のなかでバンド力といったものも以前より上がっていて、それも今作に反映されているんじゃないかと思ったんですよ。
「ジャズでは珍しいことだと思いますが、メンバーを変えずにもう何年もやってますからね。確かにそれもあるかもしれません。
ただ、このアルバムでバンド感が見える曲は半分くらいなんですよ。プロダクションが強い曲に関しては、逆にバンド感が見えないところで勝負をしていて、そのへんがミソかなと。
例えば1曲目“フェイド”はほぼ僕ひとりでやっているので、バンド感が見えない。で、2曲目“ABC”で一気にバンドをイメージできるようになる。それを行き来する感じのアルバムかなと」
――なるほど。
「だから、ビートメイカー、プロデューサーとして、自分でできてしまうことの幅が広がったってことと、バンドの司令塔として以前より思い切れるようになったってこと、その両方があって作れたアルバムという気がします。
アルバムに入れられなかったトラックもいっぱいあったんですよ。いままではある曲全部入れてギリギリ形になるって感じだったけど、今回は3年半もあったから、ほかにもすごくいい曲がいくつかあって。あと数曲足したら2枚組でもいけたくらい」
――けど、それよりも1枚のアルバムとしての強度とトータリティーにこだわった。
「そうです。そっちを強くしたかった。あと、流れを大事にしました。だから何度も聴き返して。一回まとめたものを何度か聴き返したら、ちょっと停滞感が否めなくて、少しエキサイトが足りないなと感じたので、2曲目を入れ替えたりもして」
――十分な時間があったからこそ見直しを重ね、完全に納得のいくものに仕上げた。
「はい。ジャズでは考えられないくらいの回数スタジオに行って、2年以上かけて作ったので。すごく贅沢な時間の使い方をしました。4小節に何時間もかけたり、自分でドラムのサンプリングをしたり、しかも音象にもこだわって作った。そういう作業のひとつひとつが自分を成長させたと思います」