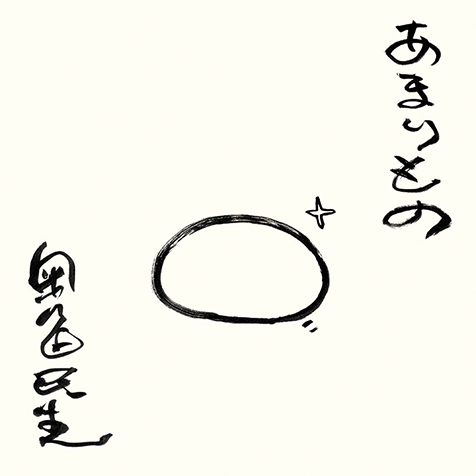力づくでもポップスにすることで、電子音の存在感が際立った
――『SONASILE』はどういった作品をめざして作られたのでしょう? アルバムの制作背景やレコーディングの経緯、テーマについて教えてください。
「日頃から、どうにかしてラディカルな音楽は作れないものかとはもちろん思っているし、同時にシンプルに聴けるポップスを作ってみたいという素朴な欲望も、作曲を始めた頃から一貫して持ち続けていたんですよね。そういった思惑がある一方で、引き出しとして西洋音楽や電子音響があることも自覚していたし、美術/サウンド・アートの世界にも僕はコミットするようになっていた。改めて自分に何ができるのかを考えたとき、アカデミックな出自の影響なんでしょうけど、〈活かす〉とか〈融合する〉しかないのかもしれないと考えたんです。でもそういうのって、音楽に限らずあらゆる文化/芸術の領域で行われているし、誰が一番早く〈いいとこ取り〉するか、みたいなゲームに参加するのはしんどいし……という感じで悩んでいたんです」
「そこで、発想の転換をしてみたんです。〈活かす〉〈融合する〉といった方法自体を相対化して、〈極限まで活かさない〉〈ほんの少しだけ融合する〉みたいにすればいいじゃんと。すべての要素を程度問題として扱うという。ポップスとして機能することが可能なストラクチャーに対して、極端にダイナミックな態度でテクスチャーを配置していったんです。徹底的にハーモニーも付けるし、テクスチャーも極端に変化させる。でも絶対にポップスという様態にしがみつく、みたいな。それで何か新しいものの片鱗が聴けるかもしれないし、別に聴けなくてもいいからとにかくやってみようと。そういう抽象的な指針を頼りに『SONASILE』を制作しました。なので、実は意外とペシミスティックというか、貧しい動機から始まった作品なんです」
――電子音楽やエレクトロニカは得てして難解になりがちですが、『SONASILE』は複雑で実験的でありながらも、親しみやすく間口が広い内容になっていると思います。そのような作品になったのはなぜだと思いますか?
「とても嬉しいご感想ですが、難解ではない理由があるとすれば、最初から電子音楽/エレクトロニカではなく〈ポップ・ミュージック〉として作ったからだと思います。僕のなかでは『SONASILE』はポップスでしかないし、最初からポップスを作るつもりでした。電子音響との関係性で言うと、これは制作途中で考えたことなのですが、力づくでもポップスにしていくことで逆説的に電子音の存在感が際立つのではないかと思ったんです。20年近く前に隆盛を極めた電子音って、訳がわからないけどなんかカッコイイものとして登場したあと、次第に多くの音楽家たちが(真っ当な)作り方を身に着けていき、〈いかにポップスに活かすか〉という視座において、電子音をアレンジ用の素材として使いこなすようになりましたよね。同時に電子音も素材として耳触りの良いものが増えたと思う。僕の興味はそれとは逆で、訳のわからなかったものとしての電子音に、いまだに興味がある。その興味を誰かとまた共有したいんです」
――なるほど。
「佐々木敦さんが『テクノイズ・マテリアリズム』で、過剰な高周波などを使って聴覚に極端な印象をもたらす電子音楽のことを〈エクストリミズム〉と呼称していて、その本を読んだ当時はカッコイイこと言うなーと思ったんですが(笑)、いま思えば僕は『SONASILE』で逆方向としての〈エクストリミズム〉を実践したのかもしれません。電子音をポップスのためのアレンジ素材として用いつつも、ある種過剰に活かしてアレンジそのものを脱臼させることで、逆にリスナーのなかの電子音への意識を復権させたかったのかなと。むしろもう一度、電子音を難解なものとして考えるべきだというか。そういう発想を徹底することによって、アレンジの範疇を超えたアクシデンタルな音色が、作品全体にバラ撒かれることになった感じです」
電子音楽史のミッシング・リンクに橋を架けることができた
――柴田聡子さんやBabiさんが『SONASILE』に参加することになった経緯や、作品における貢献について教えてください。
「お2人はまったく違うタイプのミュージシャンですが、何よりまず個人的にファンでした。ただ歌っていただいた楽曲は、2曲ともシンガー・オリエンテッドな作り方はしていません。柴田さんに歌っていただいた“Kuzira”は明らかにご本人の音楽性とは遠いし、Babiさんにも“env Reg.”で歌っていただきましたが、彼女はシンガーというより〈歌も歌う作曲家〉なので、そういう意味でお2人共どこかで僕の楽曲とは相性の合わなさがあったと思います。でもそういう矛盾を実装するのもポップスがポップスであることの原理の一つだと思いますし、お2人は声質そのものが最初からポップなので、僕が実装した矛盾はポップな声質とのバランス意識もあったのかもしれません」
――“Mare Song”では古川麦さんがギターを演奏しているばかりでなく、作詞も担当されていますよね。この起用についてはいかがでしょう?
「自分の近くにいたミュージシャンのなかで一番ギターが巧く、なおかつ音楽も大好きだと思えるミュージシャンが麦さんだった……という素っ気ない理由でアレなんですけど(笑)。麦さんは金管などいろんな楽器ができるマルチ・プレイヤーだし、もちろんシンガーでもあるのですが、僕は彼のギターが特に好きなんです。本当に巧い。ギターのレコーディング直後に〈ちょっとだけ縦ズレしちゃったから編集で直しといて〉とか言って帰っていったんですけど、聴き返したら全然ズレてないし、ほんの少しのズレがあったとしても、それによって僕が意図しなかったグルーヴと豊穣さをもたらしている。これがプロのポップ・ミュージシャンなのだなと、初めてポップスを作る立場だったので感心してしまいました。もう頭が上がりません、足を向けて寝られません」
――LASTorder『Cherish』、yuichi NAGAO『Rêverie』など昨今のリリースを見渡しても、PROGRESSIVE FOrMはエレクトロニカの先鋭性を失わずにポップ・ミュージックとして響かせる、というチャレンジを行っているレーベルだと思います。そういった姿勢は網守さんの音楽性にも通じるところがあると思うのですが、今回のアルバムをPROGRESSIVE FOrMからリリースすることになったのは、どういう経緯があったのでしょう?
「2013年に梅沢英樹さんのPawn名義の作品『Portrait Re:Sketch』に参加させていただいたのを機に、PROGRESSIVE FOrMにはコミットさせていただいてます。2014年にはレーベルの名物コンピ『Forma. 4.14』にも1曲(“rythme du rhizome”)提供させていただきました。そういう縁もあって、昨年の3月頃からレーベル・オーナーのnikさんに少しずつ『SONASILE』の音源を送らせていただき、9月頃に全曲揃ったという感じだったかと。僕自身は2000年代前半のテクノ・ミニマリズムに大きな影響を受けていて、PROGRESSIVE FOrMの当時の作品をよく聴いていたので、今回リリースさせていただけたのは間違いなく光栄だし、なんだか電子音楽史のミッシング・リンクに橋を架けることができたような気になってしまうというか(笑)、勝手ながらそういう達成感もあります」
――最後に、今後の予定を聞かせてください。
「僕にとってもっとも重要なコラボレーターであるサウンド・アーティストの大和田俊と一緒に、Cryogenic Rhythm Scienceというラップトップ・デュオでかなり難解で抽象的な音をやってるんですが、今年からリリースも視野に入れて本格的に活動しようかと思っています。あとは今年後半に、初めてオープンな形でのインスタレーション展示の予定があります。最近は現代音楽の新作はほとんど手掛けていませんが、2月21日に東京オペラシティで行われる友人のピアニスト、濱野与志男くんのリサイタルで僕が大学1年の頃に発表したピアノ・ソロ曲“M7ATION/Ver. 13”が再演されます。他には、このところ人前で鍵盤を弾いてなかったので、そろそろ弾きたくなってきているから、何か予定が入る見込みです。あとは素朴に、ストリングス・アレンジも久しぶりにやりたいし、劇伴もしっかりやっていけたらと思っているんですよ、意外かもしれないですけど(笑)。〈西洋音楽〉とか〈電子音楽〉とか関係なく、やりたい音楽は尽きないですね」