90年に東京で生まれた若きコンポーザー、網守将平は2013年に日本音楽コンクールの作曲部門で1位に輝き、NHK Eテレ「スコラ 音楽の学校」に出演したりとクラシック/現代音楽のシーンで実績を積む一方で、ラップトップを用いたライヴを行うなど電子音楽/サウンド・アートの世界でも注目を集めてきた。そんな彼が昨年発表した初作『SONASILE』は、自身が弾くピアノとエクスペリメンタルな電子音響を張り巡らせた精巧なサウンド・デザインと、歌モノのポップ・ミュージックとしての親しみやすさを両立させた、実に挑戦的な一枚だ。ヴォーカリストとして参加した柴田聡子やBabiに、ceroや小田朋美のサポートも務める音楽家の古川麦というゲスト陣も見逃せないが、この先鋭的すぎるエレクトロニック・ポップを耳にすれば、坂本龍一や渋谷慶一郎といったアカデミックな系譜に連なる新世代の台頭を実感せずにはいられないだろう。
そんな網守が『SONASILE』を制作するにあたって、自分に課したルールは〈とにかくポップ・ミュージックを作ること〉だったという。独自の音楽遍歴とアルバム・リリースに至るまでの過程、本作の制作背景について尋ねてみた。
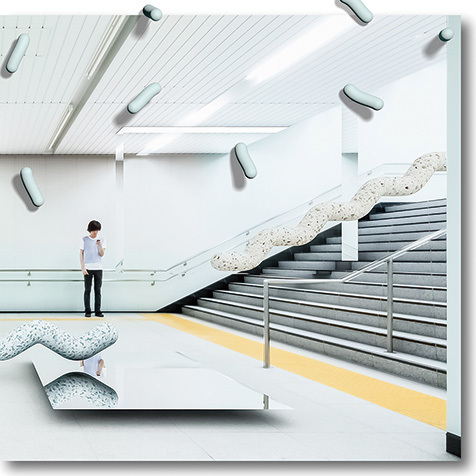
音楽からは絶対に逃れられない運命
――いつ頃から、どういった経緯でクラシック音楽を学ぶようになったのでしょうか?
「僕が4歳頃のことだと思いますが、周りの家庭の子供たちが次々に習い事を始めたことを意識した母から〈ピアノでも習う?〉と言われて、何も考えずテキトーに頷いたのがきっかけだったと思います。その後はダラダラとピアノを続けつつ、10歳くらいで作曲や、それに伴う伝統的なクラシック音楽の基礎的書法、ソルフェージュも習うようになりました。それで、師事していた先生から音楽大学の作曲科への進学を勧められるようになり、僕自身もそういった進路を意識するようになるのですが、その一方で、徐々に惰性になっている感も否めなかったんですよね。中学生くらいになると、僕と同じようになんとなくピアノを習っていた周りの男の子たちが次々と辞めていって、僕も習い事として続ける意味を半ば見失い、レッスンもよく休むようになっていたんですが、どういうわけか辞めたりはしなかった」
「最大の転機は高校受験のときで、作曲の先生と相談した結果、気になっていた音楽大学に付属高校があるので、そこの作曲科を受験してみてはどうかという話をいただいて。その高校はエリート音楽家の卵が集う、国内のクラシック英才教育の牙城みたいな場所だから、惰性でピアノをやっていた人間が合格するのは無理だと思ったんです。だから記念受験のつもりで受けてみたら、なんと合格したんですよね。僕にとっては本当にショッキングな出来事で、惰性で付き合ってきた音楽に皮肉にも救われるような形になってしまった。それを機に、自分は徹頭徹尾に音楽の人間であって、これは絶対に逃れられない運命なのだと開き直り、そこから初めて音楽と誠実に向き合うようになりました」
――クラシックを学んでいくうえで、影響を受けた作曲家を教えてください。
「ベートーヴェンやシューマン、あとはやはり近代フランスの一連の作曲家から影響は受けていると思います。とりわけドビュッシーとサティの影響が大きいかな。この並びを改めて俯瞰してみると、彼らは音楽を形式的な概念以上に、もっと広く時空間的な概念に近いものとして扱っていた作曲家だとも言えますよね。自分のこういった影響の受け方は一貫していて、そのまま後の音響系やサウンド・アートへの関心/活動に繋がっています。ちなみに僕は、フランス系の影響を受けているとはいえ、ラヴェルの影響はほぼゼロに近い。ラヴェルの音楽は形式的な完成度が極めて高い音楽なので、逆につまらなさを感じていたのかもしれません。〈すごいとは思うけど、なんかもう知ってた〉みたいな。極端に言えば、僕のなかでラヴェルを聴くのは、日本のポップスを聴く感覚とさほど変わらない。日本のポップスにおけるブロック構造的な形式美は、元を辿れば明治時代に当時のフランス音楽の輸入が積極的に行なわれていたことも一因で、僕のラヴェルに対する所感はそういった理由もあると思います」
――現代音楽だとどうでしょう? 演奏家からの影響もありますか?
「いまでも影響を受けていると思えるのはリゲティ、フェルドマン、グリゼー、近藤譲、黛敏郎などでしょうか。この並びも、やはり自分の美術やサウンド・アートとの関係性に繋がっています。一方で、ジョン・ケージの影響はあまり受けていないんですよね。これは自分でも理由がよくわからない。演奏家の影響というのもそこまでないんですけど、強いて挙げるならミケランジェリとチェリビダッケによるラヴェルのピアノ・コンチェルトは、ある意味でレガシーですが、いまでもよく聴いてます。ラヴェルの曲だけど(笑)。あとは……セロニアス・モンクの打鍵法は、学生時代に真似をしながら弾いていましたね」
テクスチャーとストラクチャーの差異、葛藤としての聴取方法
――そうやって西洋音楽を学ぶ一方で、自分で電子音楽を作るようになった経緯は?
「高校から音楽に対して急に意識的になったことで、知らなかった音楽を片っ端から聴くようになったんです。リテラルに知らなかったので、そのなかには原体験というのがやはりあって。そして結果的に、僕の無意識が原体験として選んだのは、電子音楽や電子音響と呼ばれているものが多かった。なかでも多いのは、90年代後半~2000年代前半の作品ですね。誰がなんと言おうとカッコイイとしか思えなかった。それで音楽を作る勉強をしている身としては、原体験として得たものを自分でも作ってみたくなるわけですよ。ただしばらくはテクノロジーの問題もあって、ああいう音楽をどうやって作ったらいいのかわからず、実作にまでは踏み込めなかった。それから大学に進学後、デジタル・テクノロジーやメディア・アートを司っている教育機関が学内にあったので、暇さえあればそこに入り浸るようになって。その機関を通じて、電子音楽を実際に作っている人や、そういった音楽を作るためのテクノロジーが揃った環境に出会っていきました。それでようやくエレクトロニカや実験電子音響みたいなものを作りはじめて、クラブやオルタナティヴ・スペースでラップトップを使ったライヴをやるようになったんです。そうして自分がどんな音/音楽を作りたいのか、アカデミックな作曲活動の傍らで模索していくようになりました」
――影響を受けた、あるいは好きな電子音楽系のアーティストや作品、レーベルについて教えてください。
「ジャンルや音色に特化したレーベルが多いなか、そういうものに囚われず、どんなものをリリースするのか予測できないレーベルも少なからずあって。そういうレーベルの作品は昔からチェックしています。大きいところだとエディションズ・メゴは(前身の)メゴ時代の作品から聴いていますね。昨年リリースされたピタの『Get In』は内容的にもすごく感動しましたが、あの最新作を聴いたうえで初作の『Seven Tons For Free』(96年)からメゴのリリースを振り返っていくと、すごく絶妙に抽象性を保ち続けていることに気付くわけです。メゴに近いところだと、パンも好きですね。あのレーベル(の音)もかなり抽象的だし、出版などの地味で意義深い活動にも尽力しているあたり、すごくコンセプチュアルで社会的。そういう部分に惹かれます」
――西洋音楽的に譜面を用いて作曲するのと、電子音楽のノウハウを活かしながらコンピューターで作曲するのとでは、さまざまな違いがあると思います。それらを同時に行うことで獲得できる視点もあるのではないでしょうか。
「もちろん山ほど違いはありますし、違いを活かすという道は良くも悪くも過剰に拓かれているとも思います。自分の例ですが、大学時代から学内外問わずいろいろな場所でピアノ・ソロからオーケストラまで、オーソドックスな譜面をベースにした現代音楽の作品を多数発表してきました。その多くは、それまでに聴いてきた電子音楽とか〈プロトゥールス以降〉の編集技術で作られた音楽(言ってしまえば、現代の大多数の音楽)のイディオムや過剰さを、西洋現代音楽のフォームに無理矢理詰め込んだような作品で、大抵は上手くいきました。ここで〈上手くいく〉というのは、作曲の先生方や現代音楽プロパーから評価されやすいという意味です。これはデジタル・テクノロジーをベースにした音楽イディオムを、アカデミックな領域で活かしたという話ですね」
「その逆方向の話でいうと、これは聴き方についてなんですけど、何らかの曲の何らかのフレーズがあったとして、そのフレーズを〈音響〉として聴くか〈音韻〉として聴くかを、精密にではないにしろ、ある程度コントロールできるようになるというか。アカデミックな作曲の勉強をすると、モチーフみたいなものに敏感になって、フレーズからパターンを抽出したくなる。要はストラクチャーを聴き取りたくなるんですが、電子音響はテクスチュアルな要素が強いのでそう簡単にはいかない。そういうテクスチャーとストラクチャーの差異を知覚しようとする、ある種の葛藤としての聴取方法を獲得できたのは、僕にとって本当に良い意味で、アカデミズムをその外部に活かすことができた例だと思います」
――電子音楽とクラシック/現代音楽以外で、網守さんはどのような音楽を好んで聴いているのでしょう? 『SONASILE』からも、さまざまなタイプの音楽を聴いているような痕跡が見受けられました。
「答えになっているかわからなくて恐縮ですが、とりあえず演歌以外はほぼ聴いていると思います(笑)。だから演歌も聴いていきたいんですけど、僕の耳が戦後日本の近代化の影響下でオーソドックスに機能していることもあり、どうやって聴いていったら良いのかが難しい。単に歌謡曲と日本民謡の歴史を追うとか、西洋音楽の勉強で培ったテクニックを用いて楽曲分析するとかでは〈咀嚼〉に向かえないと思うんですよね。そういう難儀さを感じるだけに、演歌については逆にもっと考えていきたいです。現代に生きる僕らが気付くことのできていない、生々しいルーツが絶対に詰まっている気がする」
――2016年リリースされた作品のなかでよく聴いたものを、いくつか挙げてみてもらえますか?
「トーマス・ブリンクマン『A 1000 Keys』、オヴァル『Popp』、ティグラン・ハマシアン、アイヴァン・オールセット、ヤン・バング、アルヴ・アンリクセン『Atmosphères』、アンディ・シャウフ『The Party』、ソフト・ヘア『Soft Hair』、コリーヌ・ベイリー・レイ『The Heart Speaks In Whispers』、アンサンブル・ラール・プール・ラール『Jo Kondo : Bonjin』、宮里千里『琉球弧の祭祀 - 久高島イザイホー』、コトリンゴ『この世界の片隅に オリジナルサウンドトラック』……などでしょうか」






























