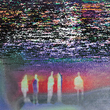欲張らないというトレンド
そんな重要な両曲にサンドイッチされる格好で、アルバムには多様な楽曲が用意されている。「全部生で、ちょっと土着感があって、ちょっと埃っぽい、ファンキーな感じで踊りたいと思って」オファーしたというSOIL &“PIMP”SESSIONSがサンバ調の“Rise Up”を仕立てていたり、珠玉のスロウ“Star”が静かに輝いていたり、楽曲ごとのテイストも、関わった制作陣の顔ぶれも実にさまざまだ。
「基本的にはレーベルのスタッフさんと相談して、自分が気になったトラックをどんどんピックアップしていく感じでした。あとは“EXCITE”などを一緒にやったKanata Okajimaさんから〈仲のいいロンドン・ノイズと一緒に大知君に書いてみようかな〉っていう話があって“Neon Dive”が出来たり」。
作品全体から伝わってくるのは、固有のトレンドに大きく舵取りを委ねていないことだ。例えばロンドン・ノイズはヒネリの利いたディスコ・ポップ“Neon Dive”とドラム・ブレイクとホーンがグルーヴィーな“Body Kills”というアルバム中でも極めてブライトな2曲を手掛けているが(いずれもKanata Okajimaが作詞)、UKや韓国で指折りのヒットメイカーとなっている彼らと組んでも、仕上がりは絶妙に大知のカラーになっているのが頼もしい。
「流行りがそのまま入ってるっていうことはないような気がしますね。まあ、いわゆるブルーノ・マーズみたいなものも、フランシス&ザ・ライツとか、もっとアンビエントなものも自分は好きでいろいろ聴くので、逆にまったく同じことをやるのは何かちょっともったいないな、みたいな。良い意味で何か違和感を感じる曲だったり、そういうものを選んでるって感じかなって思います。まあ、基本的にヒネくれてるので(笑)。だから、そのエッセンスを含みながら、何か全然違うものとか、おもしろい構成になってるとか、そういうちょっとヘンなものが好きは好きですよね。今回でいうと例えば“Darkroom”のケプラーは、他の作品を全然知らない海外のクリエイターなんですけど、デモを聴いた時にこの泣きのギターがサビにきてて、もうヘタしたら演歌みたいに日本的で。けど、サウンドはちゃんと現代的な抜けもあって、アンビエントな感じもあって、凄いおもしろいバランスだなって思って選びましたね」。
そうした発言を踏まえて各曲を聴くと、安直にトレンドとされるサウンドの定石を行かない、定型に乗りすぎないことで際立つオリジナリティーの正体も見えてくるのではないだろうか。
「今回のアルバムで自分的な〈トレンド感〉みたいなものをどこに置いたかというと、たぶん〈欲張らないこと〉かなと思っていて。例えばクリス・ブラウンがSoundCloudにアップしてる曲とか凄い好きだったんですけど、さっき話に出たブルーノとかも、どこか肩の力が抜けてて、余裕があって、楽しんでるっていうか。何かその、いわゆるEDMっぽいものがひとつ落ち着いて、トロピカルみたいな感じがきて、フューチャー・ベースっぽいのがきて、そこからまたちょっと原点回帰っぽいところもありながら……って時代の音が変わっていくなかで、いま自分が好きな音楽に共通してるのは〈欲張ってない〉ことだなと思って、何か〈ハイ、ここで盛り上がって〉みたいなお膳立てをしないというか、聴く人がそれぞれいろんな気持ちで聴けるような、自分はそこがイマっぽい気がしたので、そういうところだけ採り入れられたらいいなとは思ってました。サウンドの方向性として、あんまり欲張らないっていうのは1つのキーワードなのかなって思いながら曲を選んだりしてましたね」。