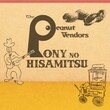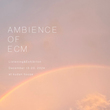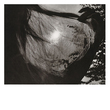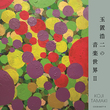細野さんのシンプルな極地にはなかなか辿り着かない(ポニー)
――そもそも、前田さんがカントリーに興味を持ったきっかけって何だったんですか?
前田「細野(晴臣)さんの『FLYING SAUCER 1947』(2007年)ですね」
岡田「ああ。僕も一緒だ」
前田「あれを聴いてカントリーに興味を持ったんです。あとは、40年代とか50年代の曲のカヴァーがたくさん入っていて、そういう音楽をどんどん掘っていくきっかけになりました」
岡田「細野さんが久し振りに歌モノを出すっていうので聴いてみたら、カントリーだったというのは大きかった。僕らの世代は、あのアルバムを聴いてカントリーを聴きだした人が多いと思いますね。バンジョーとかマンドリン、ペダルスティールを買ったりして。でも、ポニーちゃんほどカントリーに取り憑かれた人は、そんなにいないと思うけど(笑)」

――カントリーのどんなところに惹かれたんですか。
前田「なんだろうな。古い音楽だけど新鮮だったんですよね。コードも2つくらいしか使っていないのにカッコいいし、アレンジもシンプルだけどおもしろくて。あと、細野さんがライヴのMCで〈カントリーは誰でもできますよ〉みたいなことを言ってて。それを真に受けて、僕もやってみようと思ったんです」
――カントリーを自分なりに消化するにあたって、気をつけていることってあります?
前田「細野さんくらいキャリアがあって説得力があればいいけど、僕が2コードの曲を作っても、つまんなくなっちゃうような気がして。だから、コードも結構多めに使って複雑にしてしまう。本格的なカントリーというよりは、自分のできる範囲のカントリー。それを僕は〈なんちゃってカントリー〉とか〈カントリー・ポップス〉って呼んでいるんですけど」
岡田「確かに、コードの使い方や進行はカントリー的じゃないですよね。カントリーとかブルースみたいに2コードとか3コードの曲を日本語で歌うと、めちゃくちゃヤバくなるじゃないですか」
前田「そうなんだよね、野暮ったくなることが多くて。英語で歌っているからかっこいい」
岡田「そうならないためには、多彩なコードを使わないといけない。このアルバムって、一見シンプルに聴こえるけど、結構ヤラしいコードを使ってるな、と思いながら聴いてました(笑)」
前田「そこは、心配で詰め込んじゃうんだよね(笑)。〈これだとつまんないんじゃないか?〉とか思って、どんどん展開させちゃうし、コードもたくさん使っちゃう。だから、アルバムが出来上がった時、〈情報量が多いな、このアルバム〉って思った。やっぱり、細野さんのシンプルな極地にはなかなか辿り着かない」
――細野さんくらいの年齢になって、ようやく辿り着けるのかもしれないですね。
前田「まだ細野さんの年齢の半分にもなっていないですからね」
――そういえば、アルバムの1曲目“遠吠え”は、細野さんの“ろっかばいまいべいびい”(細野の73年作『HOSONO HOUSE』収録)を意識して作った曲だとか。
前田「そうなんです。ライヴの最初にやるような曲を作りたいと思って、“ろっかばいまいべいびい”とか“三時の子守唄”(細野の75年作『トロピカル・ダンディー』)を意識して作りました」
岡田「トランペットが良かったです。“ろっかばいまいべいびい”でいくのかと思ったら、トランペットを合図にバンドが入ってきてハッとしました」
前田「あれ、良い音だよね。演奏してる本人(芦田)も意図せずに出た音らしいんだけど、巧い人が枯れた音を出してるみたいに聴こえるでしょ。〈良い感じに枯れてるよね〉って本人が自画自賛してた(笑)」
岡田「すごく柔らかくて、やたら良い音でしたね。あと、全曲通してオルガンの使い方がおもしろかった。テックスメックスみたいな、ぺたっと貼り付くようなオルガン。〈これは細野さんもやってないじゃないか〉って思いました」
前田「あれ、YAMAHAのミニ・キーボードなんだよ」
岡田「オルガンじゃないんですか?」
前田「そう、オモチャみたいな大きさのやつで。弾いてくれた佐藤(洋)くんは、ちゃんと鍵盤習ったことないんだけど、レイスコ(レイモンド・スコット)とか電子音楽が好きで、昔はひとりでそういうのをやっていた人だからカントリー畑の人ではないんだよね」
岡田「確かにいわゆる鍵盤奏者っぽくなくて、それが耳に残ったんです。あと、たにぴょん(谷口雄)がアコーディオン弾いてた曲(“健忘症”)も良かった。〈ドクター・ジョンみたいに弾いて〉って言ったんでしたっけ?」
前田「それは“Walking Walking”でピアノを弾いてもらったとき。アコーディオンは自由に弾いてもらった」
岡田「あ、そうなんだ。彼はドクター・ジョンっていうより、レオン・ラッセルなんですよね。昔、ピアノの教本を持ってきて弾いてくれたことがあるんですけど」