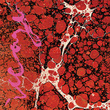常に変化と共にあり続けるアイスエイジのキャリア
〈デンマークはコペンハーゲンからやって来た恐るべき子供たち〉として十代にして衝撃のデビューを果たし、ピッチフォークをはじめ世界中のメディアから絶賛を浴びたアイスエイジ。そのキャリアは常に変化と共にある。
ハードコアやポスト・パンクからの直接的影響を強く感じさせ、猪突猛進する荒々しいファースト・アルバム『New Brigade』(2011年)。フロントマンであるエリアス・ベンダー・ロネンフェルト(ヴォーカル)のメロディーメイカーとしての才能が発露したオルタナティヴ・ロック寄りのセカンド『You're Nothing』(2013年)。そしてブルーズやカントリーといったアメリカーナへの接近と共に音楽家集団的側面を示したサード『Plowing Into The Field Of Love』。若き情熱というビッグバンのようなエネルギーと共に誕生したアイスエイジは、その熱量をほぼ毎年のように音楽性の多様な広がりへと変えていったわけだ。
しかし、2014年リリースのサード『Plowing Into The Field Of Love』をもってアイスエイジの活動は一度スローダウンしてしまう。
「『Plowing Into The Field Of Love』と『Beyondless』の間には3年くらいある。ていうか、僕ら、3年間『Beyondless』にはとりかからなかったんだ。〈いまだ〉と思えるまで待たなきゃいけなかった。アルバムを作ろう、っていうクリエイティヴな感覚が降りてくるまでね」(エリアス:以下同)
エリアスはソロ・プロジェクトであるマーチング・チャーチの2015年作品『This World Is Not Enough』リリース時にも、『Plowing Into The Field Of Love』の制作が自分自身をすり減らしたと綴っていたが、それは若き情熱とエネルギーに任せた季節が終わり、自分自身や芸術と向き合い、己の身を削り作品を生み出す新たな時期に突入したことを示しているのかもしれない。
「自分たちが素直に、誠実にやれる音楽を作りたい」
さて、そんな前作から3年以上の歳月を経てリリースされたアイスエイジの新作『Beyondless』をあなたはどう聴いただろうか?
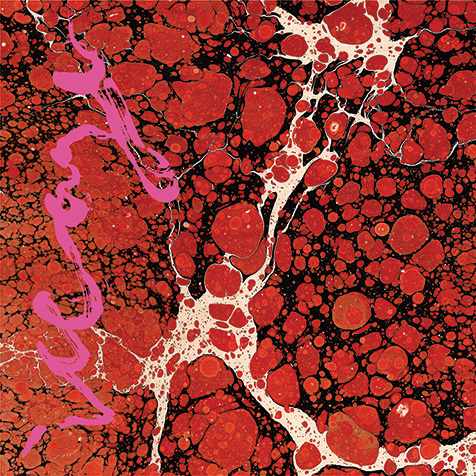
もちろんこのテキストは新作『Beyondless』について綴るものなのだが、正直『Plowing Into The Field Of Love』以降のアイスエイジの音楽は語るのが難しい。その一因としては、バンド自身が音楽的リファレンスや歌詞のテーマやモチーフについてなど、具体的な解説に繋がる話を嫌うことが挙げられるだろう。これは、英国のホラーズにも通じるものがある。
つまり、彼らの音楽は〈機能〉ではなく〈表現〉であり、それは無意識の領域や、非言語的な感覚、曖昧なフィーリングを作品とすることである。それについて多くを語ることは意味をなさない。彼らの音楽は、具体的なメッセージや目的を持った、扇動したり啓蒙したりするような音楽ではないのだ。これについてはエリアス本人もはっきりと認めている。
「うん、そうだと思う。僕らはそうした形式を気にした音楽には興味がない。自分たちが素直に、誠実にやれる音楽を作りたいんだ」
これは芸術のあり方として極めて正しい態度だろう。しかし、そのスタンスを前にして、こうした音楽メディアが彼らにオファーできるものは何だろうか。下手すれば、ひたすらに曖昧なやりとりが繰り返される〈なんとなく〉なインタヴューに終わってしまうだろう。
あるいは妄想なども含めた解釈や断定によって何かしらのとっかかりを作ることも一つのやり方だ。筆者も普段はそんな原稿を書くことが少なくない。しかし、本作においては、そうした解釈によって失われてしまうような繊細な魅力があるように感じられるのだ。
ただし〈考えるな、感じろ〉なんて言うつもりはない。芸術の鑑賞には直感だけでなく、知識がいる。歴史的文脈や同時代性なども含め、多角的にいかなるプレゼンテーションが行われているのかをつぶさに観察し、解釈し、それと同時に自らの内側の深いところに湧き上がるものを感じることが重要だ。
というわけで、ここでは彼ら自身の言葉と、作品の特徴を二つのポイントに分けて紹介することで、本作がオファーするものをある程度まで具体化できればと思う。