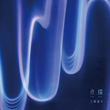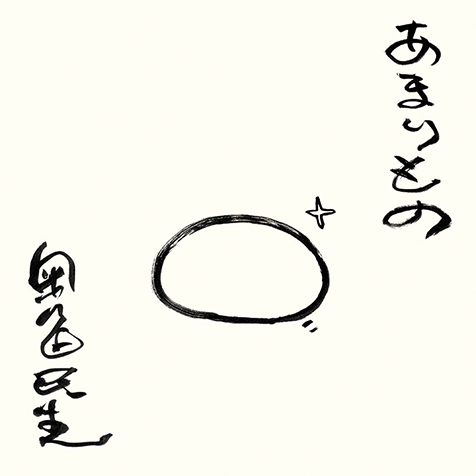大切な人と自分との境がなくなってしまうような感覚があって
――アルバムの話に戻りますが、“someday”以降の後半は雰囲気がガラッと変わりますよね。
「そうですね。なかでも“あかね空の彼方”は完璧な形にできたと思っていて。これを完成させたときは〈永遠〉を閉じ込められたような気がしましたね。今回はこの曲の歌詞にある〈愛情のベース〉というものがどこにあるのかっていうのを探っていくような作品だと思います。
それぞれがすれ違っていくけれど、個々人の愛情の根底に流れるものがもしあるとしたら……いや、あるんじゃないかという感じです。それを期待するというか、祈るしかないんです」
――なるほど。では、〈愛情のベースを流れる 恐らく低い音が〉という歌詞は、〈通奏低音〉ということでしょうか。
「そうですね。“抱きしめて”の〈同じ顔をした 私がいま〉というのは、家族の血脈や血筋から受けた愛や、そこで培われた思想について言っているんです。それと、僕は大切な人と自分との境がなくなってしまうような感覚があって――それは僕だけじゃないのかもしれないけど」
――よくわかります。
「そういった経験で何かを受け取ったし、相手に何かを渡したような気持ちになる。その喩えとして〈同じ顔をした〉という言葉を使ったんです。そこで受け取ったものが自分の奥深くを流れていって、どこかへ向かっていく。それは即効性があるものじゃなくて、どこへ行き着くかはわからない。〈何かがあるんじゃないかな〉という予感にすぎないんです」
――作品を発表するということは、いつ、誰に聴かれるかわからないということなんですよね。それがレコードとして残すということなのかなと思っています。
「僕もそう思います。だから、耐久性について突き詰めて考えていくほかないかなって。普遍性と耐久性というか」
――そういうものを備えている音楽が、butajiさんにとってのポップスですか?
「うーん……それはわからないんです。まだまだわからない。ポップスを構成する要素って、僕が考えている以上にあると思う」
――もちろん、答えがないことではありますよね。
「いろいろな人がポップスを目指して作っていますもんね。だけれども、〈僕にとってこれは違うかな〉っていうものもあったり。それぞれが普遍性や耐久性を考えているんじゃないかな」

共通認識というのは〈ポップス〉なんじゃないかなって
――butajiさんはすべての演奏をご自身でやっていらっしゃるとのことですが、ミックスもそうですか?
「今回は自分でやってしまいましたね」
――『告白』は歌が中心にあって、歌と言葉が直接的に飛び込んでくるように聴こえます。それは意識してミックスされたんですか?
「前作はヴォーカルのレイヤーがもっと奥にあったと思うんです。でも、『告白』ではヴォーカルを真ん中にして、(音量を)けっこう上げましたね。やっぱり、このアルバムの魅力はヴォーカルだったから――それは制作の終盤に気付いて、バッと変えました」
――それは『告白』が歌や歌詞にフォーカスしている作品だからですか?
「そうですね。前作を作った後に〈今後、何を作っていくんだろう?〉と考えて、ひとつの結論が〈ソングライティング〉だったんですよ。ギターと歌だけで成立するような、スコアだけで完結するような音楽にチャレンジをするっていう。それは、この先ずっとテーマとして抱えていくと思う。それを目標としたとき、やっぱりヴォーカルが前に出ることが相応しいんじゃないかなと思ったんですね」
――でも、今回butajiさんが歌っていることって、痛みとか苦しみ、悩みといったことですよね。それをこうやって聴かせることへの不安はないんですか?
「制作中にアノーニのアルバム(2016年作『Hopelessness』)が出て聴いていたんですけど、ああいう不安ってみんな共有しているんじゃないかなって思ったんです。そういう共有していること、共通認識というのは〈ポップス〉なんじゃないかなって。
逆に、何が不安なんだろう? 漠然とした不安なムードを共有していて、みんなが悩んで、大変な思いをしているのに。〈未来は絶対に楽しい!〉みたいな歌のほうが不誠実だと思うんです(笑)」
――ハハハ(笑)。わかります。
「そっちのほうが、僕は不安になる。何か答えを出してしまうこと――〈幸せ〉とか〈愛〉とか、未来の方向性を容易に、ひとつ形作ってしまうことのほうが不安なんです。本当はいろいろな形があるって、それぞれで考えていかなきゃいけないのに。だから、悩みや痛み、孤独について歌うことは、なんの不安もなかったですね、思い返してみると」