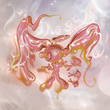多彩なアイデアと試行錯誤に溢れた『AINOU』の制作過程
――みなさんから特に好きな曲を挙げてもらって、そこからサウンドについて掘り下げていこうかと。
西田「全曲好きだけど、自分がレコーディングに参加した最初の曲でもあって“GUM”は、特に思い入れが強いですね。あとは“SHE'S GONE”。あの曲の録音には参加してないですけど、アルバムのなかでも特に近づけないような強い魅力を感じるというか。自分では作れる気がまったくしないです」
――“GUM”のギターはおもしろいですよね。ギターだと気づかなかった人もいるかもしれないけど、どう考えてもギターでしか弾けないフレーズだなと。
KITAGAWA「西田くんは普段から、ギターっぽくない音をよく出してるもんね」
西田「もちろんそこへの興味がもともと強いのもあるんですが、佳穂BANDと一緒にライヴをしていると、みんな自分の担当楽器からユニークな音を引き出しているんですよ。そういうスタンスにかなり影響を受けましたね。フレーズは荒木さんから指定があって」
――あの独特の音色はどうやって生まれたんですか?
荒木「全部で12テイクくらいギターを録ったんですけど、どれを選ぶか面倒くさくて、全部重ねてしまいました(笑)。そこにシンセを重ねて、ああなったんです」
――あと、“GUM”はイントロのドラムも最高ですよね。
荒木「スタジオが体育館みたいなところだったので、スネアは天然のリヴァーブを使っています。そこにプラグインのリヴァーブも少し混ぜて」
深谷「あとは曲によって、演奏した音を貼り直したりもしています。“GUM”は特にそう。キックとスネアを録ったスタジオが違うんですよ」
KITAGAWA「ドラムは“きっとね!”がめっちゃ時間かかってたよね」
荒木「本番のレコーディング前に、プリプロを何回もやったんです。ミックスして様子を見て、アレンジを直して、もう一回ドラム・セットを変えて……って作業を3回はしたかな。音を決めるのにとにかく時間がかかった。この曲はスネアが普通に馴染むチューニングにしてあると、全然要素が足りないんですよ。特殊に聴こえないから、結果的に歌がおもしろくなくなっちゃう。だからこだわって」
深谷「荒木さんはいわゆるドラマー的にいい音よりも、ちょっと引っかかりのある音を好むんですよ。それによって演奏も難しくなったりするので、そういう意味では苦労しました」

KITAGAWA「雄一くんは佳穂BANDに入って、ドラムの音がすごく変わったと思いますね」
荒木「彼が一回、なんかの手違いでライヴに出れなくなって。小西(遼)くんに代わりが務まるドラムがいないか相談したときに、〈雄一さんみたいに音色にこだわっているバランス型のドラマーっていうと……〉と言ってて、ニヤッとしましたもん。そういうふうに見られるようになったんだって。もともと雄一くんはジャズやブラック・ミュージックが好きで、求められるプレイと好きな音楽がちょっとズレてる感じもあったんですけど、今回のアルバム制作を通じて好きなことを素直にやるスタイルに変わったと思います」
――そんな深谷さんの好きな曲は?
深谷「そのときどきで変わりそうだけど、いま思いついたのは“そのいのち”かな。曲としての強さがあるし、景色も見えるから好き。ただ、自分の思い入れでいうと“アイアム主人公”。直前のプリプロでは、変わったパーカッションを主体としたドラムレスの曲にする予定だったんです。KITAGAWAさんのスタジオに傘立てとして使われていた、40万円くらいする壺を叩いて、その音を録音したりして。でも、そのあとに送られてきた曲にはドラムが入っていました(笑)」
荒木「“SHE'S GONE”のアウトテイクにあったドラムを、150%くらいの速さにしたらハマったんですよ。佳穂ちゃんもウキウキしていたから、じゃあこれでって」
深谷「(“アイアム主人公”は)レコーディング当日も曲が出来てない状態で。歌詞も未完成だったんですよね。それをしっかり今の形にまとめたのはすごいなって」
荒木「洗濯に行くときも、パンを買いに行くときもずっとノートで書いてたもんね」
KITAGAWA「この曲はラップしてる感じも面白いですよね。シンガーでああいう感じって難しいと思うけど、彼女は本気を出したらどっちもできると思う」
荒木「“アイアム主人公”のサビは、原型だけもともと作ってあったんですよ。〈AppleのCMに使えそうな8小節を作ろう〉ってビートを鳴らして、そこで佳穂ちゃんが口ずさんでたメロディーを引っ張り出してきたんです。“そのいのち”のサビもそうですね。4小節や8小節のトラックを夜中までループさせて、そこで生まれたアイデアを全然違う曲に採用したという」
中村佳穂が音楽家同士の良き出会いをもたらす
――KITAGAWAさんはどうでしょう?
KITAGAWA「自分がシングル・カットを選ぶなら“SHE'S GONE”。この曲は荒木さんっぽいし、僕にはビート・ミュージックに聴こえるんですよ。壮大だしポップセンスにも溢れている」
荒木「僕もすごく好きですね、決定的な感じがします。声フェチなので、ちょっと癖になるというか。シンプルで中毒性がある感じ」
KITAGAWA「荒木さんはヴォーカルのディレクションをするとき、〈色をつけないで歌ってほしい〉っていうんですよ。僕はブラック・ミュージック上がりだから発想が逆なんですけど、それで歌うのって難しくて。“SHE'S GONE”はそれでいて、佳穂ちゃんの魅力もしっかり出ている。ハットの入り方もいいツボを押さえているし」
荒木「キックは太鼓っぽく聴こえるようにして、実際の太鼓の音も混ぜたりしました。“そのいのち”もドラムの音を引っかかるようにする必要があったので、ゴミ箱とかスタジオにあった机や椅子とかいろんなものを叩いてみて。音のチョイスは本当に大事。普通の曲になっちゃうかどうかの分水領だと思う」
――KITAGAWAさんが手掛けた“get back”はどんな曲にしようと?
KITAGAWA「トラック自体は僕のスタイルなんですけど、歌が目立つように普段よりはシンプルにして。R&Bっぽい感じだけど、荒木さんにプロフェットを弾いてもらったのでトラップの匂いもするというか。あとはたぶん、誰もやっていないアプローチをしていて。雄一くんに揺れたビートを生で叩いてもらいつつ、キックの後ろに生では鳴らない音を入れて、それをリヴァービーにしているんです」
荒木「普通だったらズレた演奏を2小節くらい叩いてもらって、それをサンプリングしてループさせるんですけど、この曲はそうじゃないんですよね。だから、ビートが一定ではない転び方をしている。この曲はもっと凝ってるんですよね」
KITAGAWA「途中でわざと3連譜にしているんですけど、なるべく雄一くんの演奏を活かそうと。それにハットの音をシンセで足したり、波形を切ってシンセで揺らしたり、数ミリ単位のエディットを細かくやっています。特にドラムに関しては、あらためてファイルを開くと面倒くさいことをしてるなって思う(笑)。でも、雄一くんに何回も叩き直してもらううちに、僕の意図を汲み取ってくれて、そのアンサーに刺激を受けたんですよね。せっかくバンドなんだし、皮鳴りとか生っぽい感じは絶対に残したかった」
荒木「日本語の響きが暗いから、こういう曲を順当にアレンジすると、シンセ・パットや鈴とかキラキラした音色が必要になるんですよ。でも、それは好きじゃないし、ボトムのテクスチャーに特徴がないと起伏のない音像になっちゃう。トラックとかエレクトロニックの部分だけでいうとそこまで目新しいことはしてないと思うんですけど、歌と音のバランスで華やかに聴こえるようにしたかった」
――最後に、荒木さんは?
荒木「僕は神経が細かいので、“アイアム主人公”“きっとね!”のサビみたいに、奇妙な電子音と上質な歌、センスのいいリズムが細かい音までキッチリ合わさっていると快感ですね。あと、おもしろい話がもう一つあって」
――というと?
荒木「“アイアム主人公”のサビみたいに、10トラック以上もいろんな音をミックスしていると、カオスな状態でよくわからなくなってくるんですよ。でも、そこで佳穂ちゃんは〈この音をカットしてください〉〈ここをフィルターかけてこもった音にしてほしい〉とか言ってくるんです。それで直してみると、実際にビート・ミュージックとしてのクオリティーが上がるんですよ。オルガンっぽい音色のローをカットするとグルーヴが増す、みたいなのをズバッと言い当てられるんです」
KITAGAWA「僕らと一緒にサウンド・デザインしていたから、この2年間の間に彼女もどんどん進化していったのかもしれないですね。僕らも究極的に言ったら、的確なところを引き算しながらバランスをとっているだけなので。それこそジェイムス・ブレイクは引き算が上手だし、彼女もそういう感覚を身につけているのかな」
荒木「しかも、僕みたいに2時間くらいかけて到達するんじゃなくて、一発でまっすぐ辿り着くんですよ。そんなの大袈裟じゃなくてプロでもできっこない。DTMをやってないはずなのに、どうしてそんなことができるんだろう」

――みなさんも中村さんとの出会いや『AINOU』の制作によって成長した部分があるんじゃないですか?
荒木「たしかに。自分の3年前のトラックとか聴くと、すごく幼稚でヘタクソで。いまはゴールを考えながら作れるようになりましたね。あと、彼女と行動しているとすごくいいミュージシャンとばっかり出会うんですよ。自分もそういう人たちと出会いを重ねながら、視野が広くなったと思います。僕や雄一くんは穴倉にこもるようなタイプの人間だったから、だいぶ明るくなったんじゃないかな。彼女と出会うまで、人とか全然興味なかったもん」
KITAGAWA「みんな彼女の人間性に引き寄せられるんだよね。ミュージシャンもそうだし、お客さんも素敵な人ばかり集まってくる」
西田「自分もそういうミュージシャンでありたいし、いつも刺激をもらっています」