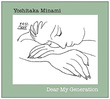東京のインディー・ポップと70年代のシティ・ポップの交差点。まさにその絶妙な場所で生まれたバンドが、1983だ。
大学の先輩後輩であった新間功人(ベース/ヴォーカル)と関信洋(ギター/ヴォーカル)を中心に結成されたこのバンドは、彼らを囲むように谷口雄(キーボード)、松村拓海(フルート)、高橋三太(トランペット)、イトケン(ドラムス)と、近年のインディー・シーンを支える腕のいいミュージシャンたちが集っている。高橋のトランペット、松村のフルートがアンサンブルの要所を担うことから生まれるラテン感や海洋的なフィーリングも、彼らのサウンドにひと味違う何かを感じさせるポイントだろう。
その1983が、5月に3年ぶりとなるサード・アルバム『渚にきこえて』をリリース。そしてなんと、そのタイミングで彼らにとっては大先輩にあたる日本のシティ・ポップの草分け的存在である南佳孝との対談が実現した。
73年に『摩天楼のヒロイン』でデビュー。松本隆、矢野誠とともに映画的でノスタルジックな世界観を作り出した。そして、76年にCBSソニーに移籍後は、いち早くアーバンなサウンドに移行。当時最高のセッション・ミュージシャンを従えた『忘れられた夏』(76年)、坂本龍一をアレンジャーに迎え“プールサイド”などいまも愛される名曲を収録した『SOUTH OF THE BORDER』(78年)、のちに郷ひろみがカヴァーした“モンロー・ウォーク”を収録する『SPEAK LOW』(79年)などをリリース。作曲家としてもシンガーとしても、いまなお精力的な活動を続けている。
1983からのラヴコールを南はどう受け止めたのか? そして若い世代の1983が求める〈70年代を新しく更新したサウンド〉は、南にはどう聴こえるのか? 世代を超えたシティ・ポップ対談は、70年代のエピソードだけでなく、アーティストとして貫くべき姿勢、新たなテクノロジーへの関心など、穏やかな雰囲気ながらもさまざまな場面で話題が交錯する刺激的な時間になった。
あの頃は先しか見ていなかった
――まさかこの顔合わせが実現するとは思っていませんでした。南さんは1983のどこに興味を持たれたんですか?
南佳孝「僕は若い人たちのことはあんまりよく知らないんですけど、金澤(寿和)さんから〈こういうグループがいるんだけど、どう?〉って言われて。聴いてみたらちょっと昔のサウンドだったから、〈えっ、いまこういうのアリなの?〉って(笑)」
一同「(笑)」
南「通り過ぎてきたサウンドだなあって。それが、逆におもしろかったですね」
――それは70年代に〈シティ・ポップ/ミュージック〉と呼ばれていた音楽ですか?
南「うん。あの頃はみんな、先しか見ていなかったから。〈ひととは絶対に違うものを〉って、それぞれやっていたんだけど。そのまんまずっと同じ姿勢でいままで来ちゃっているから、全然振り返ってないんだよね。っていうのは、ちょっとかっこよすぎるけど。だから、〈なんで僕なんだろう?〉とも思った(笑)。
この間(ライヴ後にあいさつをしたとき)、子どもの頃に僕の音楽を聴いていたって言っていたよね?」

新間功人(1983)「そうです。とんねるずの番組で“モンロー・ウォーク”が使われていて※、子どもながらに〈胸躍るサウンドだなあ〉って思いました。その後、大学生の頃に、はっぴいえんどの松本隆さんが関わっている作品っていうことで、南さんの『摩天楼のヒロイン』(73年)を聴いたんです」
1983と南佳孝の音楽との出会い
――1983の2人は、南さんの音楽をどう聴いていったんですか?
新間「〈はっぴいえんどやYMOと同世代の人たちはどんなことをやっていたんだろう?〉って思ったのがきっかけですね。
アレンジャーとしての坂本龍一ワークスを聴くことにハマったんですが、そんななかで南さんの『SOUTH OF THE BORDER』(78年)と大貫妙子さんの『SUNSHOWER』(77年)が、自分的には70年代の最高峰なんです。海外のAORを東京流にアレンジする、みたいなサウンドが当時はすごく新鮮に響きました」

南「コピーとか、それっぽい曲を書くこととかはしていたの?」
関信洋(1983)「はっぴいえんどはコピーしました。“花いちもんめ”(71年)とか」
新間「鈴木茂さんの“砂の女”(75年)とか、小坂忠さんの“どろんこまつり”(71年、作詞作曲は細野晴臣)とか。
僕らがいたのは大学のロック・サークルで、キーボーディストやパーカッショニストがいなかったんです。だから、南さんや大貫さんのサウンドはできないなあって思って、コピーはしていませんでした」
関「南さんの曲は、コードも難しい印象がありましたね(笑)」
南、お前はクルーナーの世界を追求しろ
――2人が観たライヴ(〈南佳孝&杉山清貴 JOINT LIVE「Half & Half」2019〉)では、カヴァーの選曲がおもしろかったそうです。
関「ビートルズの“If I Fell”(64年)を選ぶところとか、自分たちとも共通するオルタナティヴなセンスでうれしかったです。MCで南さんもおっしゃっていましたが、出だしが不思議な曲だなあって学生時代に新間と話していたんですよね」
南「MCでも言ったけど、僕はいまのいままでコーラスってやったことなかったんですよ。それで、2、3年前に清ちゃん(杉山清貴)と一緒にやり始めたら、〈うわっ、めっちゃおもしろい!〉ってなって。
これは言い訳だけど、(山下)達郎なんかが出て来た頃に〈あいつはコーラスをやるから、俺は違うことをやろう〉って思ったんです。ソニーのディレクターの高久(光雄)さんからも〈お前は歌を本気でやれ。ナット・キング・コールやフランク・シナトラみたいなクルーナーの世界を追求しろ〉って言われて、僕もジャズとかボサノヴァとかが好きだったので、まんまとそっちに行ったんです」
――南さんは、1983の関くんの歌声についてどう思われました?
南「響くよね。抜ける声しているっていうか」
関「(小声で)ありがとうございます……」
レジェンドしかいない70年代
――僕は“スローなブギにしてくれ(I want you)”(81年)世代なんですが(笑)、南さんのような声で歌うシンガーはそれまで聴いたことがありませんでした。
南「これも何回も言っているんだけど、僕は前に出るつもりはなかったんですよ。ずっとメロディーメイカーになりたいと思っていたから。
どこかで読んだかもしれないけど、75年に25(歳)でアルファレコードと作曲家契約をして、〈これでやっと食える!〉ってすっごくうれしかったの。それで親元を離れて、駒場東大前にアパートを借りて……いまから考えれば、カツカツだったんだけどさ(笑)。
その次の年に、『忘れられた夏』(76年)を作ったんです」

新間「『忘れられた夏』は全曲編曲が〈バンド〉って書いてありました」
南「あっ、ほんと?」
新間「はい(笑)」
南「あれはね、箱根のロックウェル(スタジオ)っていうところで合宿をしたんですよ。佐藤博に(鈴木)茂、モツ(浜口茂外也)、ミッチ(林立夫)、ベースは小原礼だよね? それで、みんなで作っていったんです」
新間「レジェンドしかいない(笑)! あのアルバム以降は編曲者がクレジットされていますが、そういう作り方はしなくなったんですか?」
南「やっぱり、才能があるやつに任せたほうがいいからね。矢野(誠)さんはうちの近所に住んでいたので、子どもの頃から知っていて、こうやって(見上げるように)見ていたからさ。
僕は久が原に住んでいて、矢野さんは洗足池に住んでいて、自転車で行ける距離だったから遊びに行っていました。後から聞いたんだけど、矢野さんちには達郎も大貫妙子も遊びに来ていて、サロン化していたらしいんだよね。
坂本(龍一)は、ディレクターが〈良いやつがいるから〉って、そういう感じで一緒にやったんだったと思う」
天才・坂本龍一と作った『SOUTH OF THE BORDER』
新間「アレンジャーとしての坂本さんって、どうですか?」
南「最初は〈アブ〉って呼ばれていて……きったねえ格好していたよ(笑)」
一同「(笑)」
南「坂本と〈アルバムを一枚やろうぜ〉ってなったのが『SOUTH OF THE BORDER』で。スタジオで(デモを録音した)カセットテープを聴かせながら打ち合わせをしたんです。そのとき〈資料に全部貸すから〉ってボサノヴァとかのLPを(手を広げて)これぐらい持って行ったのかな。それで荷物になるから、坂本が当時住んでいた笹塚に車で送っていったんだよね。
坂本はそのとき、松武(秀樹)さんとやっていた自分のアルバム――『千のナイフ』(78年)だっけ? あのサウンドの感じもあって。後から聞いたんだけど、『SOUTH OF THE BORDER』はすごく気に入ってるらしいんだよね。一緒にやった人間としては、そういうのもうれしいよね」
新間「本当にすごいアルバムだと思います」
南「最初の打ち合わせで俺が坂本に〈この曲はこういう感じで〉ってざっくり言うんだけどさ、そうするとね、いまでも覚えてる。〈こんな感じで上がってくるんだろうなあ〉って予想していると、(手を高く上げて)こーんなに良いんだよ! それで〈すげえやつもいるんだなあ〉って本当に思った。
この世界に入って、〈天才だなあ、すごいやつがいるなあ〉って思ったのは3人いて、それが矢野誠、細野晴臣、坂本龍一」
新間&関「へ~!」

南「細野さんなんてさ、〈レコーディングしたものを一回聴いてみよう〉ってときに一人でピアノのブースに行って、なんかやっているんだよね。そうしたら、メロディーとベースラインがぶつからないかをチェックしているの。〈すごいなこの人は〉って思ったよ。なのに、自分は全然練習していない、みたいな顔してさ(笑)」
1983の2人は70年代の音楽をどう考えているの?
――なるほど。では、編曲者がいる一方で、南さんのレコーディングにおける役割は?
南「歌うたいです。メロディーを書いて、歌を歌う。でも、(アレンジについて)言うときは言いますよ、もちろん。だから、朝までやるのはしょっちゅうだったし。ずっとそうやってきたから、それがおもしろいんだけど。
最近のレコーディングではさ、ステム(・データ)でヴォーカルを送ったら、こっちが歌ったテンポとぜーんぶ同じになっちゃうんだよね。あれはちょっと悲しいな。スタジオでああだこうだ言えないっていうのが」

――では、1983のスタジオではどういう作業が行われているんですか?
新間「70年代のやり方に即した……」
関「(譜面によらない)ヘッド・アレンジで(笑)」
南「逆に訊くと、君たちが思っている70年代の音楽って、どういうふうに考えているの?」
関「演奏も含めて、非常に豊かな音楽だと思います」
新間「めちゃくちゃ上手い。たぶん、上手い人しかレコーディングに臨めなかったんだろうなって」
関「プレイのそこかしこにひらめきが感じられますね」

南「(レコーディングに)むっちゃくちゃ時間かかったけどね。〈茂くん、いつまでやるの~?〉みたいな(笑)」
関「〈天才小僧〉も時間がかかるんですか(笑)?」
南「〈ほしいも小僧※〉ね(笑)。ほんっとに天才だと思っているけど、でもやっぱり……みんなそれぞれ癖はあるよね」