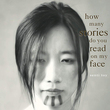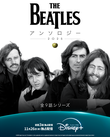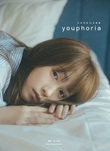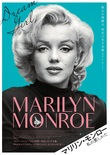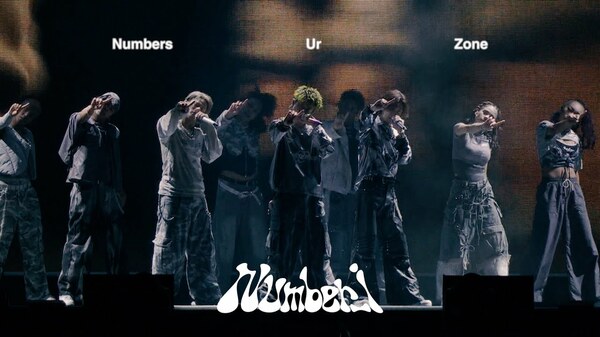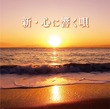イゾラドのマッシュルーム・カット頭からすると、お前の髪型はおかしいという意味ならまだしも、女性の表情はそんな牧歌性からはほど遠い。その後、フナイの職員が「冗談ですよ」と説明するのだが、まかりまちがえば一触即発の危機だ。言葉が通じない状態でそんな冗談を言われても困りますがな、と思わず関西弁が出てしまう。
その女性の言葉には、他の会話のときとは明らかに異なる、演劇的、呪術的な抑揚とリズムがある。そこからあと一歩踏み出せば、歌になるように思える。ラップならそのままでもいける。
もうひとつ印象に残るのは、事情があって別れて暮らしていたその家族が別の家族と再会した後の場面だ。移動には家族の希望でフナイのモーターボートが使われたのだが、ボートに乗っていた少女が川面や岸を眺めながら歌を口ずさむのだ。字幕によるとこんな歌詞だ。
「お父さん、お母さん、さようなら」
「わたしはタパチンガ、マナウスに行くの」
〈隔絶された〉先住民の少女がなぜタパチンガやマナウスのような町の名前を知っているのか。フナイの職員との接触の過程で、名前を覚えたのだろうか。少女の歌には、能楽師や歌舞伎役者の子供が幼児のころ舞台で演じるせりふに通じるような抑揚がある。イゾラドの言葉の子音と母音の組み合わせは、われわれの言葉と共通点を持っているのだろうか、それとも表面的に似ているだけなのだろうか。いずれにせよ、その言葉も日常会話とは明らかにちがう抑揚をこめて唱えられていて、歌の原初的なはじまりの形を想像させる。
労働起源の音楽のはじまりを示唆する興味深い例は、3枚組CD『ナガ族の調べ、山々に宿る言霊の記録』や映画/DVD「ナガのドラム」に見られる。こちらはインドとの国境地帯に住むミャンマー北西部のナガ自治区の少数民族の音楽や巨大ドラム作りを井口寛が記録したものだ。
ごく短い時間しか撮影を許されなかったイゾラドの映像とちがって、井口の映像や音楽の記録にはたっぷり時間がかけられている。ハイライトは10メートルを超える太鼓作りだ。占い師のお告げにしたがって森の中の大木を切り、それをくりぬいて太鼓を作り、1キロほどの道なき道を村人総出で運び下ろし、宴を催すまでの過程が記録されている。この太鼓は「楽器としてより、重大な村の伝達事項を伝える手段として使われるもの」(土橋泰子「ナガと呼ばれる人たち」)だという。