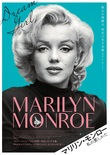ナガの人々は中国やチベットなどから追われてミャンマーの険しい山岳地帯にたどり着き、長年にわたって狩猟と焼き畑農業による自給自足に近い暮らしを送ってきたと言われる。隔絶しているといっても、インド側のナガランドの住民との交流はもちろん、植民地時代や第二次世界大戦ではイギリス軍や日本軍との接触もあったから、アマゾンのイゾラドとは孤立の度合いが全く異なる。20世紀後半以降、村にはキリスト教と仏教が広がり、伝統的な精霊信仰と習合している。映画に出てくる人たちも普段はTシャツやズボン姿で、見た目には日本人や中国人とも区別がつきにくい。なお、アメリカで活動しているシンガー・ソングライター、センティ・トイはインド側のナガランドにルーツを持つ人だ。
巨木をくり抜き、山道を運び下ろすには、力を合わせる必要があるが、その作業は歌によって統御される。音頭とりがいて、他の者がコーラスで応じる。斧で木を叩くときの音まで音楽のように聞こえる。村の人口は約300人。かなり組織化された社会を確認する意味もある音楽なので、原初の歌とは形は違うだろうが、労働と歌の関わりの深さが伝わってくる。同様の音楽はアメリカの囚人の歌から日本の民謡や儀式の音楽にまで、世界各地でフィールドワークされている。中にはコールドカットがアマゾンの森林伐採の映像や音とエレクトロニックなビートを同期させて環境問題を訴えた“ティンバー”を思い出す人もいるだろう。
ナショナル・ジオグラフィック社刊行の写真文集「世界の少数民族」の帯には「世界が急速に均質化するなか、なおも伝統を保つ少数民族の貴重な記録」という言葉がある。前出のインド側のナガランドの人たちをはじめ、珍しい写真に登場する世界各地の少数民族は、好き好んで〈辺境〉を選んだわけではなく、〈文明社会〉に押し出されてそこにたどり着き、厳しい環境の中で驚くべき数々の文化を作り上げてきた。はじめて見るのに郷愁をおぼえる写真もある。泥の仮面をつけて舞い、竹笛を持つニューギニアのアサロ人は、いったいどんな音楽を奏でているのだろう。

〈隔絶された〉〈秘境〉の文化を記録に残すのは、〈文明社会〉のまなざしを背負った行為だ。写真から〈文明社会〉の痕跡が注意深く遠ざけられている中で、エチオピアのスリ人の青年が裸の肩に乗せるカラシニコフ銃が、〈均質化〉を推し進めてきた〈文明社会〉の暴力性を端的に物語っている。逆境にあって伝統を保持する誇り高さを評価するにせよ、滅びの危険性に心を痛めるにせよ、問われているのはわれわれのまなざしの置き方だという気がする。
寄稿者プロフィール
北中正和(Masakazu Kitanaka)
音楽評論家。東京音楽大学講師。1946年、奈良県生まれ。京都大学理学部卒業後、69年に上京。中村とうようの編集する「ニューミュージック・マガジン」編集部を経てフリーに。その後世界のポピュラー音楽について研究、紹介、評論活動を行っている。NHKFM「ワールド・ミュージック・タイム」のDJも務めた。著書に「ロック史」「ギターは日本の歌をどう変えたか」「増補・にほんのうた」「毎日ワールド・ミュージック」、編著書に「細野晴臣インタビュー THE ENDLESS TALKING」「風都市伝説―1970年代の街とロックの記憶から」「事典 世界音楽の本」、訳書に「イマジン/ジョン・レノン」などがある。