仏ディスコの巨匠、セローンのDNAと『DNA』が伝えるもの
ジョルジオ・モロダーと並ぶユーロ・ディスコの巨匠。一般的にそう認識されているセローンは、実際にジョルジオが歩んだ道を誰よりも早く忠実に追いながら、ドラマーとしての才を発揮して独自のグルーヴを追求してきた。2010年代にも、ジョルジオが30年ぶりのアルバム『Deja Vu』を出した翌年(2016年)、ナイル・ロジャースらを招いたディスコ回帰的なアルバム『Red Lips』を発表。もっともセローンは、ディスコ再評価云々とは別にコンスタントにアルバムを出し続けてきたし、フレンチ・ディスコの親玉として、ダフト・パンクやボブ・サンクラー、ディミトリ・フロム・パリといった母国の後進からも常に慕われている。持続性のあるダンス・ビート、シンフォニックな響き、淫靡で猥雑なムード、アンビエントで実験なセンス、それらの合体がクールに表現される彼の音楽は、いつだって刺激的だったのだ。
ディスコの世界へ
作曲家、プロデューサー、アレンジャー、ドラマー、DJといった肩書きを持つセローンことジャン・マーク・セローンは、1952年、イタリアからの移民だった両親のもと、パリ近郊のヴィトリ・シュル・セーヌで生まれた。オーティス・レディングなどアメリカのソウルに親しんでいたという彼は12歳でドラムを開始。18歳でフランスのリゾート開発会社〈クラブ・メッド〉が運営するクラブにてオーケストラのリーダーを務め、20歳になる頃にはアフロ・ファンク系バンド、コンガスの一員としてフランスのバークレイからデビューしている。
コンガスには、78年にセローンの制作でダンス・ポップなアルバム『The Garden Of Love』を出すドン・レイことレイモンド・ドネスも在籍。バンドはセローンのソロ・デビュー後も活動を続け、とりわけサルソウルから米国発売された78年作『Anikana-O』は高評を獲得している。その表題曲を共作したのが、セローンの出世に貢献した、エジプト出身のアレック・R・コスタンディノスだった。
自身が主宰するマリゲイターから発表したデビュー作『Love In C Minor』(76年)では、この後セローン作品の常連となるドン・レイ(キーボード)やモー・フォスター(ベース)らが演奏にあたり、ディスコ・ビートとオーケストラ・サウンドの合体でダンス・ミュージックの世界に華々しく参入。特にアレックと共作した16分に及ぶ長尺の表題曲は、乱交をテーマにしたパーカッシヴで絢爛なディスコ・ソングで、これは60年代後半にジミ・ヘンドリックスやサンタナに心酔し、西海岸のヒッピー・カルチャーに憧れていた彼のフリー・セックス感も反映されているのだろう。同時に、ジョルジオ・モロダーがオーガズムに至る16分間の恍惚を音にしたドナ・サマーの“Love To Love You Baby”(75年)も意識していたに違いない。
ドラマーとしてのグルーヴ
70年代にセローンが出した作品はミュンヘン・ディスコへの返答とも言われるが、“Love In C Minor”はそれを象徴する曲だった。ちなみに、アトランティックが配給したセローンの作品は、北米ではしばらくコティリオンから出されていくが、脱ぎ捨てられた服やヌードの女性を写した『Love In C Minor』のジャケットは、冷蔵庫に素っ裸の女性が寝そべる次作ともども、国によっては差し替えに。80年作『Cerrone VI』にいたっては、フェアライトCMIを駆使した意欲作ながら、女性のヌードを写したジャケが問題になったのか、はたまたディスコ排斥運動の影響なのか、初めてUSリリースが見送られている。
なかでも、800万枚を売る大ヒットとなり、世界的な名声を得た3作目『Supernature』(77年)はジョルジオの向こうを張るアルバムだった。特にアラン・ウィスニアックと共作した表題曲はシーケンス・ベースが脈打つエレクトロニックなダンス・ナンバーで、ジョルジオの作法を踏襲。後にTOTOのメンバーを含む米西海岸の名手と録音した79年作『Cerrone V』においても“Rock Me”のギター・リフがドナ・サマーの“Hot Stuff”そっくりだったりと、臆面なくジョルジオを真似ている。とはいえ、例えば『Supernature』に収録されたドラム叩きまくりの“Sweet Drum”では、シンセ奏者として電子音楽を追求したジョルジオとは違ったファンキーなドラマーとしてのグルーヴ・マスターぶりを発揮。これがセローンの流儀であり、ディスコ低迷期も評価されてきた所以だろう。
環境への眼差し
“Supernature”でブレイクした後は、ミュージカルや映画のサントラ制作にも着手。常にライヴでのパフォーマンスを意識して曲を作っているという彼らしく、79年にはライヴ盤も出している。さらにプロデューサーとして音楽仲間のリーダー作にも関与し、マリゲイターおよび傘下のクロコスから、コンガス、ドン・レイ、モー・フォスター、一派のスタジオ・プロジェクトであるリヴェラクションなどの作品をリリース。自身のアルバムではブラコン、ニューウェイヴ、ハイ・エナジーなどに反応し、86年に発表したラトーヤ・ジャクソンとの共演曲“Oops, Oh No”では、ジャネット・ジャクソン『Control』に刺激を受けたのか、ミネアポリス・サウンドを即座に取り入れている。また、ローラ・ブラニガンとの“Heart Of Me”を収めた89年作『Way In』ではAORやブラコンを通過したポップ~ロックなサウンドで当時のメインストリームに接近。一方、91年8月には東京湾の花火大会にちなんだイヴェントにて“Harmony”という組曲を披露したが、ジュリアナ東京がオープンし、イタロ・ハウスなどの消費が激しかったこの時期の日本でパフォーマンスしたことで、改めてセローンの立ち位置が明確になった気もした。2000年代以降は、『Hysteria』(2002年)や『Celebrate!』(2007年)といったハウス寄りのダンス・アルバムで70年代のディスコ・グルーヴをアップデート。2016年の『Red Lips』も、そんな流れを汲んでいた。
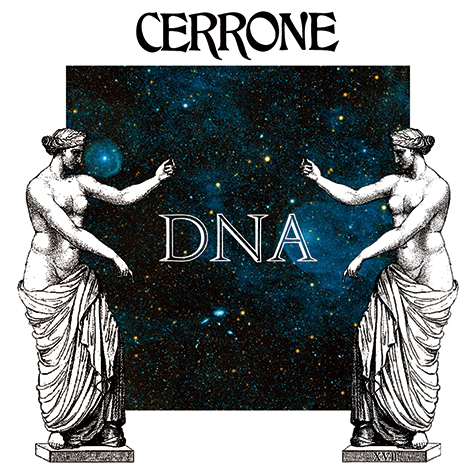
約3年ぶりに届いた新作『DNA』も同路線かと思いきや、今回はキャリア初となる全編インストゥルメンタルのアルバムに。コズミックなサウンドは、2010年にセローン・シンフォニー名義で発表した壮大でトランシーなアルバム『Variations Of Supernature』にも通じているが、新作では、40年前の『Supernature』と同じく改めて環境(破壊)問題にテーマにしたという。「ここ5年間、自分の過去作を中心にDJをしていたら、自分の音楽キャリアのDNAを探求すると同時に制作意欲が増したんだ」と。シングル“The Impact”のMVからも伝わってくるように、イギリスの動物行動学者ジェーン・グドールにもインスパイアされ、人類が傷をつけた惑星(地球)を癒すべきだと訴える、文字通りの環境音楽。これまでも歌詞のない音で清濁あらゆる情景を描写し、メッセージを投げかけてきたセローンの新作には、半世紀近くに及ぶキャリアの重みが詰まっている。 *林 剛
セローンの楽曲を収めた作品。



































