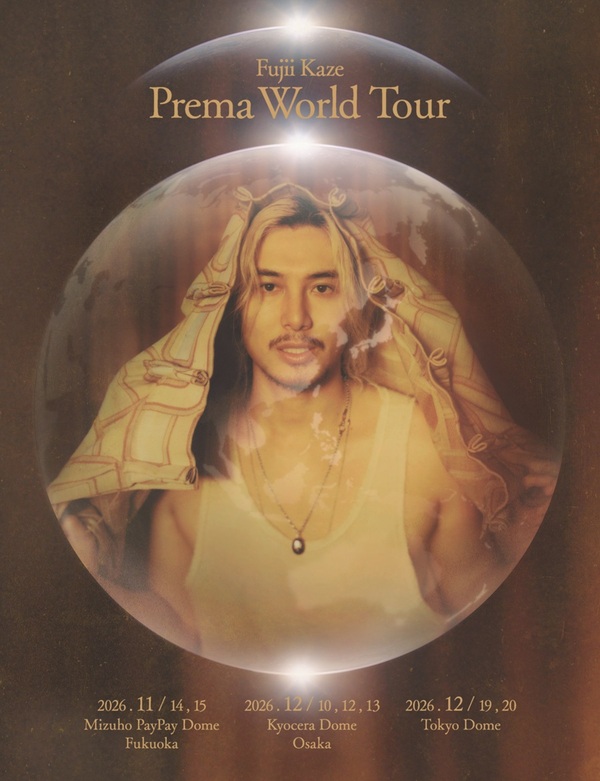裸のラリーズ・水谷孝からの着信
――う~む、なるほど。しかし、今回の3枚に共通しているのは演者たちがどこまでも自由気ままに音を紡いでいるおもしろさで、こういう空気って最近の作品にとんと見かけないものだよな、ってつくづく感じた次第で。
「自由気ままさもだけど、音楽的テイストはしっかりとあるね。誰にもできることではないが、それもパブリック・ディマンド次第だから」
――ええ。
「例えば裸のラリーズ※は、ずっと長いことアンダーグラウンドな存在であるにも関わらず、外国では驚くほど有名な存在になっていて、アメリカでも大きなコンサートができるような状況なんです。向こうの若い子たちは自分が生まれる前のラリーズの音楽について、とても熱心に質問してくるんだよ、50年後に。ラリーズの音楽もやはりあの時代にしか生まれえないもので、長い間潜伏していた音楽だよね。実は最近、水谷(孝)と話をしたんですよ(電話やショート・メッセージでのやりとりは、2019年の8~9月にかけて数回以上行われた)」
――えっ、そうなんですか!?
「生きているか死んでいるかも知らなかったんだけど、ある日いきなり電話があってね。いまアメリカではこんな状況だよ、って話をしたんだけど、本人もモニタリングしていて結構わかっていたみたい。その際、けっこう具体的な話まで進んだんだけどね。ラスト・ツアーってことで大ホール一本やればいいじゃない?とかさ」
――想像するだけで震えが来ますね、そのプラン。
「それが最後になるのか、あるいは終わりの始まりになるのかはわからないけども。そんな話で盛り上がって、けっして本人も悪い感じじゃなかったんだけど、やっぱり違うと思ったんだろうね、以後連絡が取れなくなってしまって。また霞の向こうに行ってしまった。そもそもラリーズは水谷そのもので、私たちはあくまでヘルプする立場なのでね」
――実現したら大事件でしたね。
「そうだよ、世界がひっくり返るかも」
夕焼け楽団ができるまで
――でもほんとお元気で何よりです。ところでラリーズに参加していた頃から、夕焼け楽団は始動しているんですよね?
「ラリーズと並行して、ドラムスの正田俊一郎と組み、ギターの洋ちゃん(藤田洋麻)、ベースのキンちゃん(恩蔵隆)と出会い、近場にいた4人でスタートしたの」
――麻琴さんが京都から上京後に拠点としていたのが、吉祥寺のライブハウス〈OZ〉。そこでライブを重ねながら音楽性を固めていったと思うのですが、当時やっていたレパートリーとかは?
「京都と東京をいつもヒッチハイクで移動していたね。その頃は知っている曲を手当たり次第にやっていた感じ。『まちぼうけ』※(73年)に入っていた曲に加えて、カヴァーも多かった。パブ・ロック・スタイルというか、ブルースだけでなくハンク・ウィリアムスのようなカントリーも多かったし、あとビートルズや(ローリング・)ストーンズの曲もやってたな。でも大したコンセプトを持っていたわけではなかったね」
――当時はどういうバンドやアーティストを好んで聴いてらっしゃったのか。グレイトフル・デッドはお好きだったと思うんですが。
「60年代のサンフランシスコ・バンドは好きだったね。いつ頃に何を聴いていたのかは正確に言えないけど、10代後半にはリッチー・ヘヴンスが好きだったってことを最近思い出してたり。そのほか、ティム・バックリィ、ジョニ・ミッチェル、ジュディ・コリンズとか、60年代は彼らの音楽が好みだった」
――けっこうフォーキーな音楽が趣味だったと。
「そうそう。で、70年代、ロックに向かってからは、ジェファーソン・エアプレインやカントリー・ジョー・マクドナルドなどサンフランシスコ系ばっか聴くようになる。ヤングブラッズみたいなバンドにも親近感を抱いていたっけ。あと、ラヴィン・スプーンフルもずっとファンなんですよ。ロック・バンドだけどすごくフォーキーで、ジャグ・バンドのような曲もやったりするあの感じがすごく好きで、初期の夕焼け楽団が手本にした」
――77年の〈ローリング・ココナッツ・レビュー〉※では、フロントマンのジョン・セバスチャンと共演されていましたね。
「OZっておもしろいところで、アンダーグラウンドなバンドに限らず、カルメン・マキやりりィといったメジャーなアーティストも出演していたんだよ。メジャーだけどちょっとヒッピーな匂いがする人達が。りりィがダルシマーを持ってステージに出ている写真とか残ってるよ。で、あるとき、ブルース・シンガーの大木トオルさんがOZでの私らの演奏を観たあとに楽屋に来て、君らのやっていることはとても良い、僕も本当はラヴィン・スプーンフルみたいな音楽がやりたかったんだ、って言われたんだよ」
――あの大木トオルさんが。
「そうなんだよ(笑)。いちばん最初に日比谷野音に出たときって大木さんの前座だったからね。まだバンド名が決まってなかったような頃」
――最初は久保田麻琴バンド、とか名乗っていたんですか?
「OZの最初の頃はそんなふうで、そのうち夕焼けバンドになり、サンセット・ギャングになり、やがて夕焼け楽団になり……って変化していった。あるとき、レパートリーを増やそうと4人で石川県の山奥の廃屋で合宿をしたんだけど、近くに学校があって、夕方になると運動場にすごく綺麗な景色が広がる。その時間帯にはもう練習なんてやってられない。みんなそこでフラ~っと遊びはじめるわけだよ。それから間もなくだよね、名前が夕焼け楽団に決まるのは」
――青春だなぁ(笑)。
「夕焼けが何よりも好きだね。ま、ザ・バンドみたいなものだ。村の人たちがそう呼んでいたからザ・バンドになったっていうさ。で、1週間ぐらい合宿して曲を作って、OZとか京都の拾得でやるようになった」