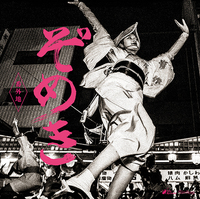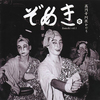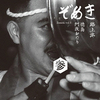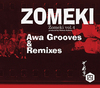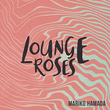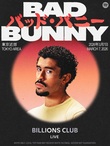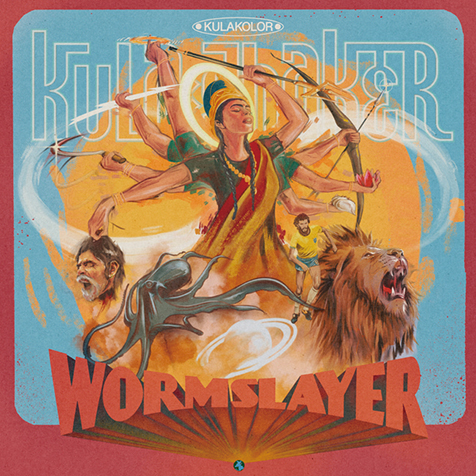久保田麻琴が探求するリズムの本質、阿波おどりを録音した〈ぞめき〉を語る!!
音楽家/プロデューサーの久保田麻琴の活動は多岐にわたる。近年だけでも裸のラリーズなどの幻の音源の発掘・復刻や、多種多様な音源のリマスタリング、金延幸子や浜田真理子などシンガー・ソングライターとのコラボなど、ジャンルや時代を飛び越えた活動を続けている。2010年代以降の彼の活動において軸のひとつとなってきたのが、日本各地の民謡や祭りのリズムに対するアプローチだ。なかでも徳島や東京・高円寺で活動する阿波おどり団体(連)の演奏を収めた〈ぞめき〉シリーズは、リズムをめぐる久保田の長い旅のひとつの到達点ともいえるだろう。2010年夏に第1弾がリリースされ、現在まで複数のタイトルが発表されてきたこのシリーズの番外編がこのたびアナログ盤で登場。それが『ぞめき 番外地』だ。久保田は制作の経緯をこう話す。
「10年ぐらい前までは(屋内で録音された〈ぞめき〉シリーズとは別に)祭り当日のフィールドレコーディングをよくやってたんですよ。ただ、当時はあくまでも記録として録っていただけで、後から形にしようとは考えていなかった。でも、ここ数年、裸のラリーズのリイシューなどでラフなカセット音源をマスタリングすることに慣れてきたこともあって、ひょっとしたら(阿波おどりの音源も)化けるかなと。デジタルのプラグインやAI技術が充実してきたこともあって、10年前に録ったラフな音が独特の迫力をもって蘇るようになったんです」。
過去のフィールドレコーディング音源を整理するなかで、久保田は〈苔作〉および〈新町橋よいよい囃子〉というふたつの連の音源を12インチ化するアイデアを思いつく。どちらも阿波おどりの一般的なイメージを覆すほどのオリジナリティーを持ち、県外でも熱狂的な支持を得ている連だ。
苔作は〈一拍子系〉とも例えられるハードコア的な連の元祖。星の数ほど存在する徳島の連のなかでも異質な存在であり、まさにカリスマ的な連である。
「苔作を初めて観たとき、別格だと思いました。練習量と信念が違う。アスリート的ともいえるぐらい規律が厳しくて、どれぐらいマジかが音から伝わってくる。1960年代に苔作が始まった当初は、太鼓の代わりにフライパンとスネア(ドラム)を叩いていたそうなんですよ。パンク・バンドみたいなものですよね」。
一方の新町橋よいよい囃子は、徳島市でスタジオを経営し、長く地元の音楽シーンを支えてきた柳町春雨が率いていた連。特徴的なのは普段ロックなどを演奏しているメンバーが集まっている点で、他の連にはないファンク的なグルーヴが持ち味だ。今回の録音ではボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ“Get Up, Stand Up”を模したコール&レスポンスまで飛び出す。
「春雨さんももともと徳島でロック・バンドをやっていたそうなんだけど、昔の仲間がもう一度集まる場として新町橋よいよい囃子を始めたようですね。春雨さんのロック人脈の仲間が中心になっていて、ミュージシャンが多いから腕はいいんです」。
ここに収められているのは、その新町橋よいよい囃子と同じく徳島を拠点とする眉月連との路上セッションだ。このセッションも久保田の発案により実現したのだという。
「眉月連もおもしろい連ですね。リトル・リチャードの曲は(ニューオーリンズ出身のドラマーである)アール・パーマーが叩いていたわけですけど、眉月連にはそれに近いリズムの真髄みたいなものがある。普通の連は観光客に対する見せ方を意識しているけど、眉月連はそういうことをしないんです。ストイックにグルーヴを追求しているんですよ」。
どちらの音源も10年ほど前、祭りの現場でレコーディングされたものであり、祭りの熱狂的な空気もパッケージングされている。苔作は高円寺阿波おどりに招待連として出演した際のもの。新町橋よいよい囃子はホームである徳島でのパフォーマンスだ。
「高円寺は道が狭いぶん、音が反響するんです。沿道で見ている観客との距離もちょうどよくて、歓声もいい形で入るんです。この頃の苔作はまだ東京だといまほど熱狂的なファンがついてなかったと思うけど、音から伝わるものがあったんだろうね。反応がロック・コンサートみたいですよね」。
今回の2曲は過去の〈ぞめき〉シリーズでは感じ取ることのできなかった久保田の身体性が表現されている点にも特徴がある。阿波おどりの強烈なリズムに揺れる久保田の姿が目に浮かぶような音になっているのだ。
「ああ、確かに。ステレオマイク1本で録っているので、自分の身体が動いている気配もそのまま入ってるんですよ。音に引き寄せられている感じというかね。いまの技術によってその感覚すら作品化できるようになった。自分でも驚きましたね」。
久保田は「エッセンシャル(本質的)なものを見つめたのが〈ぞめき〉シリーズだったのかな」と話す。そうした〈リズムの本質〉を探求する旅の一方で、あいかわらず未知の音楽を探り続けている。「まだまだ知りたい音楽がいっぱいあるんですよ。そういえば、アルバニアのほうにすごいヴォイス・ポリフォニーがあってね」――そう切り出すと、アルバニアの音楽について熱を込めて語りはじめた。音を巡る久保田の旅はまだまだ続きそうだ。
〈ぞめき〉シリーズ。
左から、2010年作『ぞめき壱 高円寺阿波おどり』、2011年作『ぞめき弐 徳島阿波おどり 正調連』『ぞめき参 徳島阿波おどり 路上派』『ぞめき四 Awa Grooves & Remixes』、2014年作『ぞめき伍 個性派 徳島 高円寺 阿波おどり個性派』、2016年作『ぞめき六 徳島阿波おどり 粋』、2019年作『ぞめき七 徳島阿波おどり 純情派』『ぞめき八 Re-mixes Stupendous!』(すべてAby)