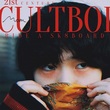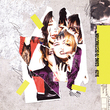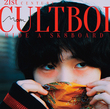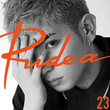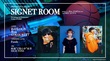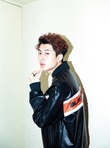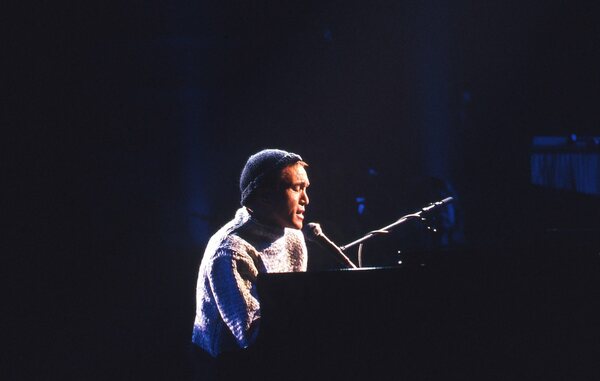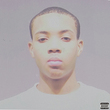ハッとする驚きを
アップデートされたプロダクションは、しかし、特定のジャンルや既存のフォーマットに小綺麗にまとめられる方向には向かわず、クラフトなポップセンスを活かしたまま、遊び心溢れる逸脱や脱線を重ねたことで風通しの良い自由なムードを纏っている。
「曲作りもシンプルなビートのループから、音響的にも緻密に作り込んで、展開を付けていくアプローチへと意識的に変えていったんです。それから、これは僕がヒップホップで一番好きな部分なんですけど、例えば、LAメタルの大味なギターにラップを乗せてもLAメタルにはならないし、ハウス・トラックにラップを乗せてもオーソドックスなハウスにはならないですよね。ヒップホップのサンプリングやレイヤーがもたらす超越的な、メタ的な性質を現代でどう表現するか。今回はたくさん作った曲をセルフ・サンプリングして他の曲で用いることで、1曲のなかで異なる質感を同居させたりもしています」。
ベース・ミュージックやインダストリアルのエッジーなトラックとメランコリックなメロディーが共存した“マスク”や音響の変化とリリックが呼応し合う“アンチタイムトラベル”。ビートルズの遺伝子を継承したかのようなカラフルなトラックとシニカルなリリックがコントラストを成す“ゴーストワーク”、アグレッシヴなトラップ・チューンがメロウな転調を果たす“カルトボーイ”など、自由奔放な楽曲の数々は、オープニングの“胎内回帰”から近未来のディストピアが描かれた“2040”へと至る作品の大きな流れ、現実の閉塞感をデフォルメしたSF的な世界観でまとめられている。
「昨今の音楽はリスナーとの関係にあまりに縛られていて、作家性が希薄になっているというか、ハッとさせるような驚きがないような気がするし、それは音楽に限らず、SNSを含めた社会全体に感じられる想像力の欠如とも繋がっている気がするんです。それだったら、リスナーがそれぞれ考えたり、想像力を刺激されるような、ハッとさせる音楽を自分で作ろう、と。そこでサウンドだけでなく、リリックに関しても昔から大好きな星新一さんや筒井康隆さんの『笑うな』といったショートショート、藤子不二雄さんのSF短編漫画からインスピレーションを得て、シニカルな視点や驚きが感じられるストーリー性や表現を意識しました」。
SNSのタグのように、簡単にはラベリングできない人間の感情や日々の営み。頭ではわかっていても、真偽の定かではない膨大な情報や思念が押し寄せる混沌とした日々にあっては、耳触りのいい言葉や声の大きい意見に流され、安易に白黒つけてしまうことが多かったりする。そんな現代社会に対して、Momは想像力を増幅させる音楽によって、目の覚めるようなカウンターを提示する。
「この作品には自分なりのステートメントを込めたつもりではあるんですけど、何かが良い悪いということが言いたいわけではなく、音楽として楽しんでもらえる瞬間もたくさん用意して、そのバランスを大切にしました。例えば、シングル曲の“ハッピーニュースペーパー”は〈楽しい曲〉という感想がめちゃくちゃ多くて、ヒップホップ好きの方からはポップすぎると言われたりもしたんですけど、よくよくリリックを聴けば、実はシニカルだったりする。つまり、自分としてはただ楽しいだけ、後味が悪いだけでは終わらせたくはないし、その絶妙なバランスのなかで自分なりに戦っていきたいんですよね」。