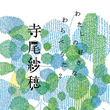生まれては死んでいった彼らの、生まれては死んでいく誰かの、忘れられたたましいたちの、聞こえにくいけれど確かにそこここに彷徨う声の、たまたま私の耳に届いたざわめき。――寺尾紗穂「取り戻せないことの上に」
『余白のメロディ』の購入特典として頒布された、寺尾紗穂によるエッセイ「取り戻せないことの上に」のこの一節を読みながら、果たして、〈ざわめき〉というのは〈たまたま〉耳に入るものなのだろうか、ということを考える。まして、寺尾紗穂という人は、この世の中で、時の流れの中で、忘れられそうな、見過ごされそうな、無視されそうな、ともすれば疎んじられ、軽んじられそうな、有形無形の〈ざわめき〉に能動的に耳をすましてきた人ではなかっただろうか、と。
2007年にフルアルバム『御身 onmi』でメジャーデビューして以来、彼女は15年という月日をかけて、数々の作品を世に送り出してきた。その楽曲群に記録された〈ざわめき〉の数々は言うに及ばず。文筆家として寺尾が著した「原発作業員」(講談社現代新書)や「南洋と私」(リトルモア)など、アクチュアルなイシューの当事者に話を訊き、丹念に調べ上げた書籍を読めば、彼女がいかに真摯に〈ざわめき〉と向き合ってきたかがわかるはずだ。
『余白のメロディ』の9曲目、“歌の生まれる場所”は〈歌の彼方 耳に届くざわめき/気づかぬふりはしない〉という決意にも似た力強い言葉で締め括られる。自らが〈歌〉を紡ぎ・歌うその理由をあらためて宣言するかのような、この楽曲を語る時に〈余計なお世話〉という言葉を寺尾は使った。
〈ざわめき〉が〈たまたま〉聞こえてくる、その理由。それは寺尾紗穂にとって、〈ざわめき〉を聞くことは、生きることそのものだからなのではないだろうか。冗談めかして(でも、半ば本気で)自らが〈歌〉を作ることは〈余計なお世話〉で〈衝動的〉なものだと言う彼女にとって、〈ざわめき〉は聴き取ろうとするものではない。それは、柔らかに降り注ぐ雨のように、苛烈に辺りを照らす太陽のように、当たり前にそこにあるもので、あくまでもごくごく自然に、たまたま届くものなのだ。
誰かの〈ざわめき〉があなたの耳に届く時、あなたの〈ざわめき〉もまた誰かの耳に届く――今、この鬱屈とした息苦しい時代においては、奇跡のようにも思える、どこまでも真っ直ぐな〈希望〉を、寺尾紗穂の10枚目のアルバム『余白のメロディ』は、てらいなくリアルなものとして描き出す。
河童と香害――目に見えないものを受け入れる〈余白〉
――『余白のメロディ』は〈音楽にできること〉を明確に宣言している作品だと思ったんです。いかにもロックジャーナリズムっぽいインタビューの始まり方で恐縮なんですが。
「ははは(笑)。それは“歌の生まれる場所”のことですか?」
――そうですね。でも、アルバム全体がそういう作りになっていると思ったんです。各曲で描かれる物語や風景が最後の“歌の生まれる場所”と“Glory Hallelujah”に収斂していく感じがある。
「なるほど。“歌の生まれる場所”が出来たきっかけっていうのは、毎回MCで喋っているので知っている人もいると思いますけど、河童なんですよ」
――妖怪の河童ですか。
「そう。結構な数の河童が福岡のライブに来てくれたことがあって。筑後川の近くの会場だったんですね。その日一緒に演奏した歌島昌智さん(音楽家、民族楽器奏者。寺尾のアルバム『わたしの好きなわらべうた2』に参加)と、もう一人お客さんとして来てくれてた人が、視えないものが視える人で。その二人の言うことを総合すると〈今日のライブに河童が来てたかも!〉ってことになって」
――河童は何をしに来てたんですか?
「普通に音楽を聴きに来てたみたい。せっかく来てくれてるんならと思って、MCで河童について話したら、かれらは〈ひゃ~!〉ってすごく喜んでくれたみたいで(笑)。河童もいないものと思われてるから、寂しかったんでしょうね。〈俺たちまだいるのに……〉みたいな感じかも」
――そりゃ、河童もステージで歌っているアーティストからマイクを通してメンションされたらテンション上がりますよね。普段いないものにされてるわけだし。
「確かにね(笑)。でも、その話を東京に帰って色んな人に話したんですけど、面白がってくれる人と〈えっ?〉みたいな反応をする人がいて」
――確かに突飛な話かもしれないけど、信じられなくても〈ふーん〉ぐらいに聞いておけばいいのに。
「でも〈それって結局どういうことかな?〉って考えてみたんですよ。つまり見えないものは〈いない〉ってその人たちは思ってるわけですよね。目の前の現実はもちろん、自分の想像を超えるものはいないだろうって思っている。そういう人たちと、自分には見えないけど〈いる〉のかもって思う人の現実の捉え方には、結構な距離があるって気づいて」
――なるほど。
「それって、妖怪や幽霊の話だけじゃなくて。例えば、最近気になってるのは、〈香害〉のことなんです。柔軟剤や化学物質の匂いに敏感に反応してしまって、体調が悪くなる人がいる。そういう人たちって行ける場所も限られちゃうんです。子どもの場合、他の子が使ってる柔軟剤のせいで、教室に入れなかったりとか。決して、マジョリティーではないですけど、少なからず困っている人たちがいる。
でも、ほとんどの人は問題なく暮らせてるじゃないですか。そういう人たちが、自分は感じないことで苦しむ人たちを〈気にしすぎ〉とか〈神経質〉だとみなす、そういう視線ってあるなと思って」
――自分にはわからない、他者がリアルに感じているものに共感できないってことですよね。
「〈そんなのないでしょ〉って言い切れてしまうのは自分の想像を超えた部分を認められないってことじゃないですか。〈自分にはわからないし、理解を超えているけど、あるかもしれない〉ということを受け入れられるのが〈余白〉だと思うんですよね。そういう心のあり方と、現実の捉え方をやっぱり大切にしなきゃいけないんじゃないかって思ったんです」
――“歌の生まれる場所”の〈この世界の何も信じられない/そう言うあなたに 一番綺麗な夕焼けをあげよう〉という歌詞はそういう部分とリンクしていますね。〈視えている人〉たちを歌ってきた寺尾さんが、この曲で〈視えない人たち〉に向けて意思を表明したところに〈音楽にできること〉を今、言おうとしていると感じたんです。
「『天使日記』(スタンド・ブックス/2021年)にも書いたんですが、この世は目に見えるものがすべてで、今あるシステムを熟知して、その中でうまく生き残れた人たちが勝ち組だっていうのは〈おかしくない?〉って思うんです。もっといい、みんなが幸せになれるシステムだってあるんじゃないの、今はないけど作り出せるかも、とか。現状を容認するだけじゃなくて、夢を見ることだって、本当はできるわけで。
見えないものを信じることって、音楽や愛や夢と繋がってると思うんです。そのどれもが実際には目に見えないものですし」