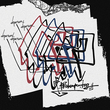Helsinki Lambda ClubとTENDOUJI。2組はともに2010年代中頃から活動をスタートし、オルタナティヴ・ロックやギター・ポップを筆頭に海外のインディー・ミュージックからの影響が色濃いサウンドでリスナーを魅了してきた。フェスでの共演やイベントでの対バンなども多い両者は、盟友と言えるだろう。
今回はHelsinki Lambda Club(以下、ヘルシンキ)の新作『Eleven plus two / Twelve plus one』を機に、ヘルシンキの橋本薫、TENDOUJIのモリタナオヒコという両フロントマンの対談を実施した。
記事をはじめる前に、まず『Eleven plus two / Twelve plus one』のコンセプトを共有しておきたい。このアルバムはAB面構成になっていて、まず前半はこれまでのヘルシンキがやってきたロックにフォーカスした〈過去・現在盤〉として6曲を収録。そして、後半は未来のヘルシンキが鳴らしているであろうサウンドを想像した〈未来盤〉として同じく6曲を収録。その結果、ヘルシンキの作品のなかで、もっとも多様な音楽性を収めたアルバムになった。
そんな進化の一枚『Eleven plus two / Twelve plus one』を、モリタはどう聴いたのか? まずは彼らの出会いから尋ねた。

Helsinki Lambda Club 『Eleven plus two / Twelve plus one』 Hamsterdam/UKプロジェクト(2020)
最初に仲良くなったバンド
――おふたりは年齢も同じくらいですか?
橋本薫(Helsinki Lambda Club)「僕はいま30歳ですね」
モリタナオヒコ(TENDOUJI)「俺は34になったところ。でもバンド歴で言うと、ヘルシンキがちょっと先輩かな。俺らにとっては最初に仲良くなったバンドかも」
橋本「初めて会ったのは2014年だよね」
モリタ「2組とも同じオーディション・ライブに出ていたんですよ。そのとき俺らは結成2か月めぐらいで、何も知らなさすぎて、会場にシールドも持っていってなかった(笑)。〈上位何組かはCDデビューを考えます〉みたいな企画だったけど、結局TENDOUJIは落ちて、ヘルシンキは3位だったのかな。他の出ていたバンド、ほんとにクソだったよね(笑)?」
橋本「うん、まぁ(苦笑)」
モリタ「ゴミバンドが集まっていたんだけど、ヘルシンキを観たとき〈こいつらは絶対にいいバンドだろう〉と思って声をかけたんですよね」
――モリタさんはヘルシンキのどこに魅力を感じたんですか?
モリタ「いや、もうすべてですね。まず曲がいいし、演奏力も音圧も違うし、良い意味で適当なところもあって。MCがないところもよかったな」
橋本「僕からしても、その日はTENDOUJIがいちばん印象的だった」
モリタ「褒めてくれたのはヘルシンキだけだった。審査員に言われた言葉は『ボイトレ行け』でしたからね(笑)」
橋本「優勝者発表のときのTENDOUJIの姿が忘れられない。いちばん前で手を組みながら拝んでいて(笑)」
モリタ「あれはギャグでやっていたけど、心のどこかではもしかしたら……と思ってた」
橋本「でも、音楽はかっこよかった。すでに“HAPPY MAN”を演奏していたんだけど、あの曲の衝撃はいまでも忘れられないです」
インディー・バンドのロール・モデル、TENDOUJI
ギターの音をブランドにできている、ヘルシンキ
――そのあとの各バンドはそれぞれ歩みを進めていったわけですね。
橋本「僕にとってTENDOUJIはいまの時代のインディー・バンドのロール・モデルみたいなところがあります。身近なところで仲間を作って、いろんな小さいコミュニティーを巻き込みながら、上り詰めていくみたいな感じがすごくいいなと思う。そういうところを勝手に勉強させてもらっていたというか、それが大事だよなぁって。後は小さなコミュニティー発信のものでありつつ、当初から〈売れたい〉と言い続けていたし、それがちゃんと結果になっているのは、ほかのバンドにとっても希望なんじゃないかな」
――ちなみにヘルシンキはTENDOUJIの仲間ですか?
橋本「えーと……仲間だと思っています(笑)」
モリタ「そこ、難しいよね。お互い刺激し合っていて、いいバンドだというのはもう無意識のなかにあるけど、別に群れているとかじゃない。自分たちのイベントにはめちゃめちゃ出てもらっているけど」
橋本「俺らはどこのシーンにも入れないバンドだったから」
モリタ「あー、そうかもね。それが羨ましかったけどね」

――モリタさんはヘルシンキをどう見ていますか?
モリタ「ほんとに漫画みたいなバンドだと思っています。自分がバンドをやっていなかった時代にずっと〈バンドやるならこういうのがいいよな〉と憧れていた人たち――SPARTA LOCALSや髭がそうなんですけど、ヘルシンキってそういったバンドを一身に引き継いでいる感じがする。引き継いだけどもうそこには自分たちしかいなかった……みたいな(笑)」
――出会って以降、ヘルシンキはメンバーの脱退や加入を何度か経験※してきましたね。
モリタ「めんどくせーなーと思ってました(笑)。出会ったときのメンバーがすごく好きだったし、もったいないなって。でもメンバー変わっても楽しいですね。それはすごいと思う。太起とかバンドにとってむっちゃいい刺激になっているし。ヘルシンキはギターの音が自分たちのブランドになっていると思う。いまギター・バンドは衰退していると俺は思っているんですけど、ヘルシンキを聴くとやっぱギターいいなと思う。その意味でTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTみたいなバンドかも」
橋本「おお……!」
――モリタさんが特に好きなヘルシンキの曲と言えば?
モリタ「“シンセミア”ですね」
橋本「即答……」
モリタ「薫くんはああいう曲を書くとほんとにすごいと思う。ちょっとミドルテンポで切なくて景色が見えるというか」
橋本「自分でもそっちに本質はあるのかなと思ったりもします」
――逆に橋本さんが好きなTENDOUJIの曲は?
橋本「なんだろうな……やっぱり“Killing Heads”とかアッパーな曲はめっちゃいいなと思うし、最初の衝撃という点では“HAPPY MAN”。あと“GROUPEEEEE”を聴くと2016年頃のフロアの熱狂をめちゃくちゃ思い出します。あの時代のアンセムでしたよね。
でも、最近の曲もすごく好き。片寄(明人、GREAT3)さんがプロデューサーとして入って以降、曲の構成やアレンジのちょっとしたところに、より気が利くようになりましたよね」
モリタ「おっしゃるとおりです(笑)」