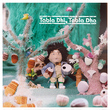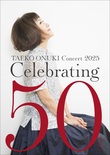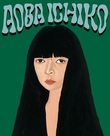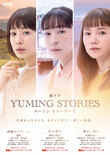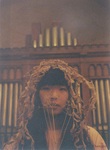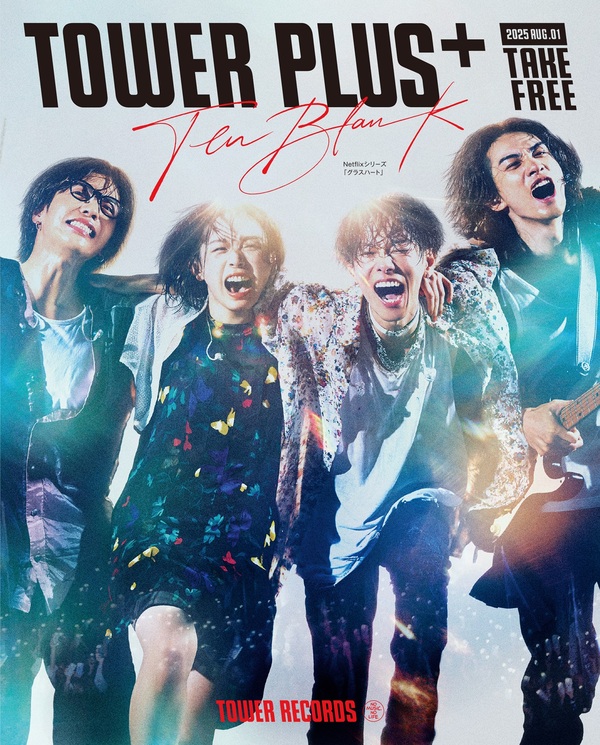“血の風”に込められたおまじない
――プロットと歌詞の関係性はどんなふうに考えられていたんですか?
「とても密接ですね。プロットは読むためのものというよりは、伝わりやすくするための……」
――あらすじのような?
「そうですね。もし、この映画にパンフレットが存在するとしたら、そこに載せたい文章というようなイメージで綴りました。それに対して歌詞は、読んで理解するものというより、感じ取る領域の言葉を使っています」
――“血の風”の歌詞は沖縄の言葉のようですが……?
「はい。ミュージック・ビデオ(“Porcelain”)の撮影で奄美に行く前日、資料を見直していたときにはっと目に留まったのが、この歌詞のもとになった〈おまじない〉でした。資料をたくさん読みこんで見つけたというよりも、本当にたまたま開いたところに載っていたもので。
その資料というのは、1925年に佐喜真興英さんという方が書かれた『シマの話』という本です。ユタさんやノロさんが唱えていたおまじないを研究された本で、その〈沖永良部島の言葉〉というカテゴリーに、子どもに発疹が出来てしまったときに唱えるものとして載っていたんですね――〈チヨ チヨ 〇〇 ヤラワン 〇〇 ヤラワン ナー ミチ ミチ ンカイイキ〉というおまじないが。〈ヤラワン〉は〈〇〇であったとしても〉という意味で、〈〇〇〉の部分には発疹や病気の種類が入ります。それを現代でも伝わるようにアレンジをして、“血の風”の歌詞にしました。

プロットにおいて“血の風”は、クリーチャーたちが朝日の昇る浜からひとりひとり小さな炎となって舞い上がり、その姿であることを辞めることをみずから選んでいくシーンです。
“血の風”の歌詞の〈フーヤメ〉は、〈疫病〉〈流行っている病気〉。〈ウトゥルシャ〉は〈とても激しい〉で、〈ハミドゥル〉は〈神様が鳴る=雷〉。〈ヤミユ〉は〈暗い夜〉。〈ナー ミチ ミチ ンカイイキ〉は〈それでもおまえの道を行きなさい〉という意味です※。もちろん島によっても表現がちがうでしょうし、独学なので私の解釈が混ざっていると思いますが、でもこれは2020年のいまもきっとおまじないとして響くんじゃないかなと思って書きました」
血よ、血よ、
疫病あれど
激雷あれど
闇夜あれど
己の道をゆけ
愛しき夢、愛しき夢
光る花の宿借りよ
――いまの時代にぴったりのおまじないですね。青葉さんが歌うことで言霊が宿りそうです。
「葛西さんは、この曲に関してとてもいいアイデアをくださって。ヴォーカルにリヴァーブをかけないことによって、まるですぐ横で歌っているかのような音の作り込み方をしています。梅先生は、島で朝焼けのなかに立っているときに、ぬるい潮風がゆっくり肌を撫でていくような感覚をコーラスで出したいと言っていました。そういうふうにどんどんアイデアが重なって、ひとつの歌が生まれています」
――“Easter Lily”や“Parfum d’étoiles”では島唄風の旋律が聴こえてきました。
「そうですね。微かに香るくらいの感じで沖縄の音階を入れられたらいいよね、という話を梅先生としていました。
沖縄だけでなく、インドネシア・バリのガムランの音階やブルガリアン・ヴォイスの響きなど、いろいろな土地のハーモニーをすこしずつ差し込んでいます。梅先生の素晴らしいアイデアによって、思い描いている像により近づくことができたのです」
――〈思い描いている像〉というと?
「〈島〉といっても、実在する島のことを表現したものではないんです。本当の〈島〉は、どこかにあって、私たちが足を延ばして行くようなものではなくて、もうすでに心のなかに存在しているんです。
それをわかりやすい形で表現するために『アダンの風』という南の島をコンセプトにしたものを作りましたが、これは入り口に過ぎなくて、そこから自分のなかにある島へ戻るように、旅をするように、アクセスするように――『アダンの風』という物語がそこへ導く舟になれたらいいな、という願いがあります」
誰にでも、どんなものにも等しく吹く風
――青葉さんが思い描いている〈島〉はどんな場所ですか?
「(考えこんで)……言葉や、歴史や、文化みたいなものよりも、もっと前からある〈風〉の気配――それがある場所が〈島〉ですね」
――〈風〉が吹く場所?
「はい。目を閉じて〈島〉を思い浮かべると、必ず〈風〉が舞っている感覚になります。〈風〉って、常にお便りのようなものを運んでいて、私たちの気持ちをとっても鮮明に、まるでクジラたちが海中でエコロケーション(反響定位)するように、よくよく伝えてくれるものだと思っています。
太陽に近い南の島の風は、暖かくて柔らかい。温度が体温に近いので、その風に吹かれると、撫でられているような気持ちになります。目には見えないけど、〈風さん〉みたいな。小さい頃に母親に撫でてもらったことを思い出すような、他人の皮膚の感覚と島の風は近い気がする。それがなによりも、言葉よりも、言ってみれば音楽よりも、ずっとずっとダイレクトに入ってきて、根源に流れている大切なことを伝えてくれるんです」

――たしかに風を感じると、誰かに語りかけられている気がします。
「2020年は疫病のことだけではなくて、たとえば人種差別の問題などが取り上げられて、なにかが渦巻いているようでした。そんななかで、風や風通しのよさの重要性をとても感じていたんです。人と人、生き物と生き物、建物と建物が密集してしまったところに、風が通るだけでそれらを守ってくれて、居心地のよい状態へと導いてくれます。
風って、誰にでも、どんなものに対しても等しく吹いている大きいものだから、たとえ〈個〉同士がちがうことを考えていたとしても、風はすべてを包みこんで吹いていますよね。風が吹いているだけで、こんなにも人々は穏やかになれるんだって。その風が、北風よりは、暖かくて穏やかな、人肌のような風であるといいかなと思うんです。そういうことを2月頃から、4月に緊急事態宣言が出たときも、ずっと考えていました」