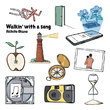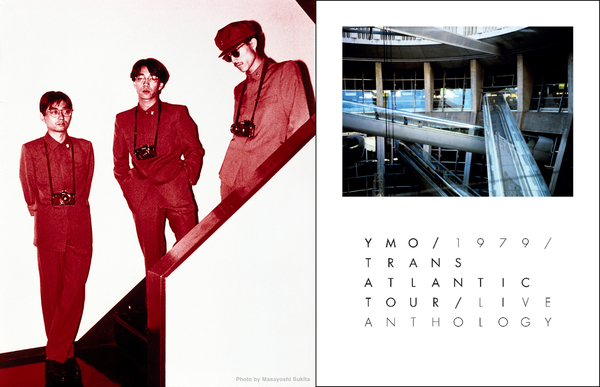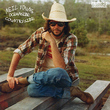BREIMENと赤い公園とTempalayに共通する姿勢
――欠片を散りばめてるんですね。ジャンルに囚われないコラージュ・ポップである一方で、しっかりと肉体性を落し込んでいることも伝わってきますね。
「1枚目では〈ミクスチャー・ファンク・バンド〉と言っていましたが、その時点で、いわゆる〈ファンク・バンド〉ではなかったんです。もちろん俺らはもともとファンクやR&Bのセッションをしてきたからファンキーにはなるんですけど、〈俺たちのジャンルってなんなんだろう?〉と思ってました。でも、総合的には〈BREIMENらしさ〉ってあると思う。俺らが意図してなくても、一個一個の選択にはそれがあって」
――音色とかアレンジとかの選択にね。
「そうです。たとえばポップスによくある安パイ的なフレーズは、別にBREIMENでやる必要ないよね、みたいな。いまは、俺がやりたいこととバンド・メンバーのみんながやりたいことがぶつかって混ざりあったら、何をやってもBREIMENっぽくなるようになってて。だから、〈BREIMENっぽさ〉の理由をジャンル感には置いてないんです」
――それこそが、最高のポップスを作れる条件なんじゃないかなと思いますね。米咲は、BREIMENのそこに惹かれてたんだと思う。彼女もロックがベースにあったうえで、祥太くんに近い発想で音楽を作っていたと思うし。
「たしかに、そこは近いのかもしれません。俺も根本にファンクやR&Bがあるけど、〈そのうえで〉っていうことをやっているわけだし。音楽をジャンルで分けてないから、そこは大きいかもしれないですね」
――その姿勢は、Tempalayにも感じるんですよね。
「Tempalayは、BREIMENのことをめっちゃ好きでいてくれるんですよ。(小原)綾斗はツアー中、1日に1回BREIMENを褒める時間があって(笑)。それは、三宅さんが言ってくれたようなことを感じてくれてるからかもしれません。
絶対に、ロジックからスタートしないようにはしてます。BREIMENはわかりやすく〈業界最前線プレイヤーが集まってる〉と書かれますし、それにはなんの異議も唱えません。事実、そうなんです。ただ、〈プレイヤー〉ってオーダーを受けてそれに対して自分の演奏をするイメージだけど、俺らは〈これしかやりませんよ〉みたいなスタンスじゃないんですよね」
――スタジオ・ミュージシャン的な発想ではないってことだよね。
「そうです。〈業界最前線プレイヤーが集まったバンド〉として聴いたら、たぶん〈なんじゃこりゃ〉って思われるんですよ(笑)。それもいいかなって、最近は思ってますね」
自作プリズマイザーの“noise”、ミスも愛す完全一発録り“色眼鏡”
――ただ、トレンドには敏感でいたいというニュアンスは感じました。同時代性は、やっぱり意識していますか?
「そうですね。2021年に出すことの意味は考えてます。ねらったわけじゃないんですけど、歌詞も含めてリアルな音楽だなって思いますし、音選びにもいまの自分たちがハマってる音が自然と入ってますし。ほんとに無理なくやってるんですよ。邪念があんまりない感じというか」
――では、デジタル・クワイアっぽいヴォーカル・エフェクトが使われた“noise”も、自然とああなったんですか?
「そうですね。あれはプリズマイザー※っぽいんですけど、俺はプリズマイザーを持ってなくて、デモのときはLogicで無理やりヴォーカルのデータを分けて貼って作ったんです(笑)。
制作当時はSNSが大荒れで、ヘイト地獄で。あの曲に関しては、そこから来た〈noise〉が大きいですね。その歌詞が、プリズマイザーっぽいデジタルな感じに合うなって思ったんです」
――“色眼鏡”は異彩を放ってますね。怒気を感じますが、どうやって出来たんですか?
「この曲の怒気って、ギターの(サトウ)カツシロのラップによるものな気がしてて(笑)。俺は〈提示〉タイプだから〈色眼鏡を壊したらハッピーだぜ〉くらいのニュアンスなんだけど、カツシロはマイクを持つとちょっと大きくなるところがあって、物申す〈提案〉タイプなんですよ(笑)。それがよくって、すごく好きなんです。
去年お金がなくなりすぎて、仲間がやってる中古楽器屋さんでバイトを始めたんですね。そこに、レッチリ(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)のフリーが使ってるミュージックマン・スティングレイっていう、俺が人生で初めて弾いてたベースが入ってきて。俺のは数年前に売っちゃったから、バイト先の人に〈お金が入ったら代金を払うから、持って帰って弾いてもいいですか?〉って訊いて譲ってもらって、ひさしぶりにスティングレイを弾くタイミングがあったんです。あのベース、ほんとにレッチリみたいなバッキバキの音が鳴るんですよ」
――まさにそういう音だね(笑)。
「それでうれしくなっちゃって、いろんなしがらみは全部置いといて、〈令和のレッチリみたいなグルーヴ作ろうよ!〉っていうノリで、〈せーの〉で完全一発録りをしました。
バンド陣の演奏は、一個も直してないんです。なんなら俺はBメロでミスってるんですけど、それもそのまま残してて。たとえば、昔のソウルの音源を聴くと〈これ、ミスってね?〉って部分があるんですけど、あれ、めちゃくちゃ愛せますよね。いまの時代、レコーディングしたものを直すなんて当たり前だから、そうじゃないものをやろうという思いもあって、一発録りの直しなしでいこうと」