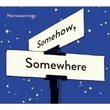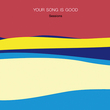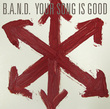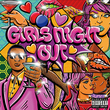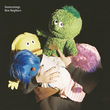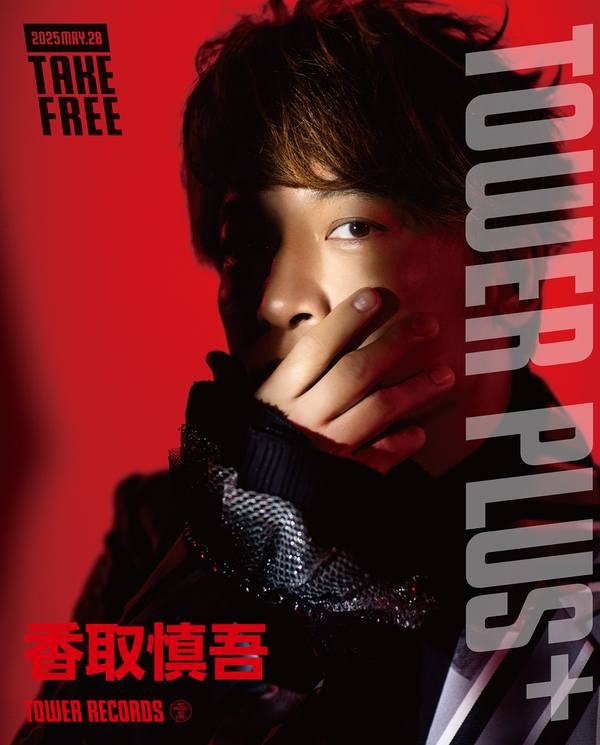ここにHomecomingsのインディー・ロックがちゃんとあります
――サイトウさんは“Moving Day Pt. 2”のデモを聴いたときどんな印象でした?
サイトウ「デモの時点で、メロディーも歌詞も歌い方もほぼ出来上がっていたから、すでにすごく良かったんです。なので、そこはあまりいじらないほうがいいなと思いました。今回は〈とにかくいい曲をめざす〉――そういうプロデュースがいいんじゃないかな、と。だから、僕は最初に〈これ、場合によっては僕がオルガンを弾かないかもしれないよ〉と伝えました。福富くんは〈うーん……〉と言ってたけど(笑)」
――福富さん的にはサイトウさんに弾いてほしいでしょうからね(笑)。
サイトウ「デモを聴かせてもらう前に、福富くんから〈ソウル〉というキーワードを教えてもらっていたんです。バンドのメンバーみんながソウルを聴いてて、これまでのインディー・ロックをやめるわけじゃないけれど、バンドとしてもちょっと新しいことをしたいと思っている、と。それなら自分のやってきたことを活かして、手伝えそうだなと思ったし、まず〈どのソウル?〉と探りました。ソウルといっても様々だから、そこがズレると大変なことになるので(笑)」
――〈ソウル感〉はどう擦り合わせていったんですか?
サイトウ「最初の時点でさっき言っていたキャロル・キングという名前も出ていたような気がするし、ひとつ〈SSW的な感覚としてのソウル〉というイメージを共有してもらっていはいたんです。ただ初めての共同作業だったので、もっとホムカミのことを知りたいと思って、僕から〈福富くんがこの曲に求めるソウル感を持った音楽は?〉〈いまHomecomingsが聴いているものは?〉、そして〈Homecomings内クラシックスといえば?〉という3つの質問を出しました。回答をまとめたファイルが戻ってきたんだけど、それがまたすごかった。画像もテキストもいっぱいで、ホントに雑誌みたいなやつ(笑)。〈福富くん、またやってくれたな〉と心を奪われましたね」
――さすが(笑)。そのなかで特に印象的な回答は?
サイトウ「まず〈バンド内クラシック〉では、いわゆるインディー・ロックの名盤みたいなものが並んでいて、ぺイヴメント、エリオット・スミス、ダニエル・ジョンストン、ジェイムズ・イハなどなど。ロケットシップも入っていたかな。なかにはサントラの作品も入っていて、すごく納得できました。
で、〈ソウル感〉と〈いま聴いているもの〉への回答としては、レックス・オレンジ・カウンティの“Loving Is Easy”が挙がっていて、これはデモの楽曲の構造的な部分で近いなと感じました。で、“Loving Is Easy”についてリサーチしたんですが、個人的には、バンド生演奏のシンプルなアレンジが素晴らしかった〈Tiny Desk Concert〉のヴァージョンがヒントになりそうだな、と思ったりして。
ただポイントだったのは、レックス・オレンジ・カウンティをそのままやるのではなくて、インスパイアさせてもらいつつ、バンドのいちばん大事な部分をなくさないように、ということでした。自分のバンドの話で恐縮ですが、僕らはそのときどきで好きなものにガーッと行っちゃいがちで、その結果いろんなスタイルの変遷をたどることになるんですけど、経験者として反省込みで言うと、やっぱり新しい部分と既存の魅力のバランスがとっても大事なんですよね。なので、そのさじ加減を大切にしながら、進めてあげたいなと。そうなるとHomecomingsの根っこにあるインディー・ロック的な部分が大事だし、その面でも〈Homecomings内クラシック〉を共有できたのは良かったです」
――インディー・ロック的な部分を活かすうえで工夫したところは?
サイトウ「デモのなかに、福富くんがギターのフレーズをいろいろと試しているテイクがあったんです。きっとギターで表現できるソウルっぽさを試していたんだと思うんですが、その断片にひときわ光っているフレーズがあったんですよね。完成したヴァージョンではイントロとアウトロに使っているギター・リフなんですけど、〈お! これめちゃくちゃいいフレーズじゃない?〉と思ったんです。ソウルというより、まさにインディー・ロック的な、ギター・リフで一気にもっていくみたいなかっこよさがあった。
なので、ソウル的なアプローチをめざしつつも、〈ここにちゃんとHomecomingsのインディー・ロックがあります〉という感じが大事だし、新しい部分と既存の魅力のバランスをとる秘訣は、そのあたりにありそうだと感じました。ベースやドラムにもそういう部分があったから、ホムカミ流のソウルをめざしつつ、これまでのインディー・ロックのいい部分も確認していったのかな」

福富「いままではメンバー以外の人に参加してもらうこと自体がほとんどなかったので、そういうことを言ってもらえるのはすごく楽しかったです。ジュンさんからのアドヴァイスは4人それぞれが〈おー!〉って感じだったと思います。照れくさいけど嬉しかったな。プレイヤーっぽくない4人なんで、〈自分のこれが魅力です〉とか言えない感じなんですよ。ほなちゃん(福田穂那美、ベース)とかも〈ベースについてのインタビューはNGです、なんも喋れません〉という感じで(笑)」
サイトウ「僕らもバンドとして、ほぼ同じ。やっぱりプレイヤー志向ではないので何かその感覚がわかります。だからこそ客観的に見えてきたというか〈おーい! ここ光っているよー!〉とピンときたような気がしますね。
そんな感じで、バンド・アンサンブル的には福富くんが弾いたギターのフレージングの妙を活かしつつ、なるちゃん(石田成美)のドラムとほなちゃんのベースがシンプルながらすごくいい感じにグルーヴしていたので、そこを軸に組み立てていきました。僕からは、ソウルっぽい響きを出すためのコード変更や、構成の見直し、テンポの調整、なんかを提案させてもらって。プリプロで、メンバーのアイデアが入って、さらに曲が良い感じに化けました。
で、メロディー、畳野さんの歌ですよね。これがもうデモの段階からお世辞抜きに素晴らしかったです。なんだろう……日本語を歌ったときのグルーヴ感、言葉をメロディーにする際の発音とか、ホントににすごくてかなり衝撃的でした。〈とにかくこの素晴らしい歌を最大限に活かさないと!〉と強く思いましたね。制作の最初の頃はソウルとかインディー・ロックとか言ってましたけど、最終的には、そういうジャンル云々ではなく、〈サビで風を吹かす〉みたいなワードに変わっていた(笑)。そんな感じで、とにかく畳野さんの歌が最高だったんです」
福富「それは、彩加さんの声がやっぱり特別な声だというのが大きいと思う。やっぱりソウルってリズムであり歌でもあると思うし、ポップスとして提示するものとしても彩加さんの歌はいちばん聴かせたいものでした。それこそ彼女が参加したくるりの“コトコトことでん”(2021年)なんかを聴いても、この人の歌ってすごいな……と思ったし」
サイトウ「インディー・ロック的な味わいを大事にしつつ、畳野さんの歌をどんどん伸ばしていったら、Homecomingsはさらにすごいことになるんじゃないか……なんていう興奮が、このレコーディング中にはありましたね。で、こうなると大事なのは福富くんの歌詞ですが、畳野さんの歌と福富くんの言葉というコンビネーションこそがもう最高なんですよ」