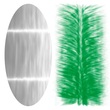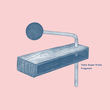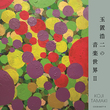作品に〈手触り〉があってほしい
――『ありあけ』は、カセットMTRにメンバーが自身のパートを録音して、それを次の人に送る、というおもしろい制作方法でしたね。
伊藤「僕はひねくれているので、ただリモートで制作したら、普通だなと思ったんです。ただし問題も発生して、ミックスなどがちゃんとできなかったんですね。聴いてもらったらわかりますけど、ノイズが乗ってしまって、使える素材に制限があった。でも、それもドキュメントだと思いました」
――『ありあけ』のジャケットには、レーベルも品番もバーコードもない。タイトルとバンド名以外の表記は〈Made in USA〉だけ。知らない人には日本のバンドなのかさえわからない、という(笑)。
こばやし「そういえばそうですね(笑)。いま言われて気づきました」
伊藤「のぞみん(こばやし)が言っていたのは、タイコのディスコグラフィーとはちがうラインの作品なんだと。配信もしないし、品番もなにもないっていうのは、そういう意識がはたらいていたのかもしれない」
――そのラフな感じが、逆に新鮮でしたよ。いま〈DIY〉という言葉は、〈Do It Yourself〉という本来の意味合いを再確認したほうがいいと思うほど、消費社会への対抗手段だった原点が忘れられているように感じますが、『ありあけ』には文字どおりのDIYで生まれた結晶を聴いているという実感があります。カセットというフォーマットがまたぴったりで、丁寧に作った愛を感じますね。
伊藤「〈手触り〉みたいなものが作品にあってほしいなと思っていました。(バンド・メンバー/リスナーの)顔が見えないから、そこで伝えられたらいいなと。
そうしたら、『ありあけ』の制作の終盤に、〈TETRAからアルバムをリリースしませんか〉と藤村(頼正)さんから連絡があって」
こばやし「バンドの側でも〈TETRAと一緒になにかやれたらいいね〉って話していたんです」
伊藤「そう。何年か前に、夏目(知幸)さんにもちょっと話をしていたんですよね」
――『Fragment』のときのレーベルとマネジメントからは離れたんですね。
伊藤「そのときの体制からは変わりました。『Fragment』のときにお世話になったところは母体が大きかったので、いろいろな縛りがあって難しいことが多く、うまくやれなくて、最後のほうは疲弊してしまった。
シングル(『感性の網目/bones』)は完全にインディペンデントで作って、それはそれで大変だったので、〈やっぱりアルバムはどこかのレーベルから出したいね〉という話をバンド内でしていたんです」
こばやし「『Fragment』のときはあまり噛み合っていないなと感じていたので、対等に話せる人たちと一緒にやりたい、という気持ちがあったんですよね」
伊藤「そこがいちばん大きかった。TETRAは、シャムキャッツというバンドをやっていた人たちのレーベルだから話をしやすいんじゃないかなと。それは今回、ぜんぶそうなんです。〈大人〉が関わっていないという。プロデュースとミックスをお願いした岡田拓郎くんは僕とおない年だし、レコーディング・エンジニアはKlan Aileenというバンドをやっている澁谷(亮)さん。そういう体制でやりたかったんですね」
岡田拓郎に〈プロデュースしてもらう〉ではなくて〈一緒に音楽を作る〉
――セルフ・プロデュースでやってきたバンドがプロデューサーを立てようと考えるのは、変化を求めているときだと思うのですが、タイコの場合は?
こばやし「〈プロデューサーを立てたい〉というよりは、〈岡田さんと一緒に音楽を作ったら楽しそうだよね〉と思ったんです」
伊藤「僕個人としては、〈変化したい〉という気持ちはあったと思います。
『霊感』(2014年)、『Many Shapes』(2015年)、『Fragment』の3作には、通底する世界や流れがあったと思うんですね。ざっくり言うと、僕が頑張って生きていくための、自分への励ましというか。
それは『Fragment』でいったん完結したので、ちがうものを作りたかった。その意味で、他人に関わってほしかったという思いはあります。第三者の目線から意見を言ってくれそうな、しかもおなじ立場で話せる人たちと一緒にやりたかったんです」
こばやし「全体的に、開いた感じで作りたかったんですね。風通しをよくしたほうがいいなって」
――風通しのよさは感じました。すごく開けた作品だし、タイコというバンドに期待しているものもしっかりと入ったうえで進化している。僕が最初にタイコの音楽を聴いたとき、これが完成形ではなくて、なにかがうごめいていて、どんどん細胞分裂しているようなバンドだと思った。『波』はそれが如実に感じられる作品だな、と。
伊藤「タイコらしい部分が残っていると感じてもらえるかな、っていうのはちょっと心配だったんです」
――以前からよかった部分が磨かれて、さらによくなっていますね。バンドの持ち味であり、目指す方向性としての〈ミニマル〉というのは変わらずに追求していると思うのですが、曲の尺を短くしたことで暁里くんのメロディーメイカーとしての才能が凝縮されて、長所が浮き彫りになっている。あと、やっぱり歌詞があきらかに変わっています。岡田さんとの最初のミーティングではどんな話をしたんですか?
伊藤「一度、2人で飲みにいって、そのときにアルバムのことをすこし話しました。〈お願いしたいかも〉くらいのニュアンスだったのですが、〈やりたい〉と言ってくれたんですね。
岡田くんのソロ作『Morning Sun』(2020年)は全体的にフォーキーで、ピアノをフィーチャーしていて、僕はそれがすごく好きだったんです。最近の音楽でいうとフォックスウォーレンのような、フォーキーでソフト・サイケの要素がある音楽に通じるものを感じて。あとは、フランク・オーシャンの『Blonde』(2016年)のこととか。そんな話をしましたね。それが去年の3月ごろです。
その後、実際にプロデュースをお願いして、その時点で手元にあった曲のデモを送ったんです。反応はすごくよかった。曲について具体的な感想が長文で返ってきて、〈特に“えんえい”が新作のキーになりそう〉という話をしました。最初の打ち合わせでも、〈“えんえい”を自分なりにエディットしてもいい?〉と訊かれて。それで岡田くんが編集してくれたものが最終形にほぼ近いもので、僕らは驚いたんです」
こばやし「私たちが〈こういうふうにやりたい〉と考えていても、技術がないとか、やり方が分からなくてできなかったことを、岡田さんがすごく上手に汲み取って、すくい上げてくれたんですね。感動しました」
伊藤「それで〈岡田くん、すごい! 全曲、どうなるか楽しみだね〉という高いテンションで制作することができたんです。早い段階でそう思えたのは、大きかったですね」