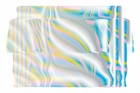繊細な音楽だと思う。それには、レイドバックしているようで緊張感をみなぎらせたバンド・アンサンブルはもちろんのこと、岡田拓郎のヴォーカルから受ける印象もある。特に今回は岡田が「ちゃんと歌を聴かせられるメロディーのいい曲を作りたい」と考え、「歌が中心となる〈いい曲〉を目指し」た作品であるだけに、なお一層のことそうだ。
岡田がシンプルに〈いい曲〉へと回帰した背景には、ヴァンパイア・ウィークエンドやディアハンター、アンディ・シャウフ、キャス・マコームズといった、カナディアン/アメリカン・インディーのバンド/シンガー・ソングライターの近作からの影響があるという。
たしかにマコームズの現在のところの最新作である『Tip Of The Sphere』(2019年)における、SSWとしてのソング・オリエンテッドな志向と音響へのこだわりの共存は、この『Morning Sun』に近いものがあるかもしれない。あるいは、ブレイク・ミルズの仕事や彼のソロ・アルバム『Mutable Set』(2020年)に通じるものもある。
そしてその繊細さは、ソングライティングやヴォーカルのみならず、最初に書いたとおりに演奏やアンサンブルそのものと、それをとらえた独特の音響、音像にも由来する。
今回、岡田が目指したのは、安易で安直なシンセサイザーやDAWのプリセット音に頼らない、「生演奏ならではの緊張感」だ。バンド、森は生きている時代からの気心が知れた仲間であり理解者である谷口雄(キーボード)と増村和彦(ドラムス)と共に岡田は、徹底的に、緻密に演奏を作り込んだ(ヴォイシングやフレージングなどを事細かに決めていったという)。さらにスネア・ドラムの録音に5本以上、キック(バス・ドラム)の録音に3本以上のマイクを立てるなど、音へのこだわりは徹底している。常軌を逸している、と表現してもいいかもしれない。
この穏やかで温かなフォーク・ロック・レコードをリラックスして聴き流しているうちは、そんなことは微塵も感じられないかもしれない。だが、岡田の偏執狂的なこだわりや、ある種の〈狂気〉は、ヘッドホンでアルバムとひっそり対峙し、深く耳を傾けることで、音と音の間隙や音像そのものから、じわりじわりと滲み出してくる。
たとえば、“Morning Sun”の〈コツコツ〉というドラムの音。あるいは、岡田が〈はっ〉とブレスするとき、小さなノイズが一閃、ひらめくように鳴り、他の音が消え去る瞬間。“New Morning”の後半における、張り詰めたドローン。“No Way”ではピアノとドラムがユニゾンし、シンコペーションするリズムによって躍動感よりもミニマリズムが生まれている。他にも“Shades”のドラムの音や“Stay”の歪んだ生々しいギターの響きなど、聴けば聴くほどに発見がある。レコーディングやミックスの〈わざ〉による『Morning Sun』の音のありようはあまりにも特殊で、他のどんなレコードにもない唯一の響きを持っていると言える。
この原稿を書くために参照した柴崎祐二によるインタビューでは、J-Popやこの国の音楽産業への違和感、疑問、問題意識が岡田の口から語られている。これはバンド時代からのアティテュードとして一貫したもので、たとえば『森は生きている』(2013年)を聴き返した後に『Morning Sun』を聴いてみれば、音への態度の成熟ぶりと音楽家としての整合性に強い感動を覚える。年月を経たぶん、深く、鋭く研ぎ澄まされているのだ。
そういった意味で『Morning Sun』は、一聴して穏やかなフォーク・ソング集ではあるものの、現在の〈ポップ〉や〈ソング〉がどうあるべきかに向き合った結果の、確実で誠実な成果である。透徹した強い意志を真摯かつ寡黙な口ぶりで伝える、静かで饒舌なレコード。『Morning Sun』は、そんな力強い作品だ。