世界的なシティポップブームの中で再評価著しいのが、カルロス・トシキ&オメガトライブの諸作だ。そんな彼らのオリジナルアルバム4作――『DOWN TOWN MYSTERY “NIGHT TIME” VERSION』(88年)、『be yourself』(89年)、『BAD GIRL』(89年)、『natsuko』(90年)とカルロス・トシキのソロ作『Emotional -右側のハートたちへ-』(91年)が、ボーナストラックの追加収録&最新リマスター仕様で、タワーレコード限定で再発された。これを機に、2022年の今この5作を聴くことやリイシューの意義について、編著書「シティポップとは何か」の刊行を控える音楽ディレクター/評論家の柴崎祐二が綴る。 *Mikiki編集部
ポップス工房としてのカルロス・トシキ&オメガトライブ
今、オメガトライブの諸作品を聴くことは、猛烈な勢いで世を席巻してきたシティポップリバイバルの先端に触れる意味を持つのはもちろん、日本のポップス制作体制内部に巻き起こってきた様々なダイナミズムに触れ直してみる行為でもある。
80年、第19回〈ヤマハポピュラーソングコンテスト〉に入選し注目を浴びたバンド・きゅうてぃいぱんちょすが杉山清貴&オメガトライブと名を改めてデビューして以来、彼らの音楽面の決定権は、メンバー達自身ではなく、所属事務所トライアングル・プロダクションの代表、藤田浩一が握っていた。林哲司、売野雅勇、新川博といった強力な裏方陣を迎えて作り出されたその楽曲は、多くの詞曲の制作はもちろん、レコーディング時の演奏もボーカルの杉山以外は基本的にプロのミュージシャンが行うというものであった(ライブではメンバー自身も演奏した)。
この活動スタイルは、往年のポップスファンならきっと、60年代に世界的な人気を博した〈バンド〉、モンキーズのありようを思い起こすのではないだろうか。プロデューサーから優れた楽曲をあてがわれ、プロフェッショナル(ときにはアイドル)としてそれを歌う。そこでは、ヒットが絶対的な条件としてあらかじめ運命づけられ、プロジェクトはある種の〈工房〉となる。だが、メンバーがキャリアを重ねていくに従い、徐々に自らの与えられた役割に苦悩しはじめ、プロデューサーとの間に緊張関係を生じさせる。これもまた〈工房〉の進化にはつきももの出来事であった。
ブギー志向の全面開花、そしてシティポップ冬の時代の模索
杉山時代のそういった変遷を経て、メンバーの脱退/交代によって誕生したのが、1986オメガトライブであり、更なる変遷の後に再スタートしたのが、ここに紹介するカルロス・トシキ&オメガトライブだ。
金看板である爽やかで弾けるようなサマーポップを深化させ、時のブラックコンテンポラリーミュージックに通じるエレクトロニックな要素を大幅に導入した〈1986〉および〈カルロス・トシキ&〉期のオメガトライブは、ここ最近のシティポップリバイバルを方向づけてきたブギー志向が全面的に開花した楽曲が数多く、にわかに再評価の対象として浮上してきた。特に、忍び寄る〈シティポップ冬の時代〉においてそれでもなお奮闘するように先鋭化した電化サウンドなど、様々な模索ぶりを味わえる〈カルロス・トシキ&〉時代の諸作は、今最も傾聴すべき存在といえる。
傑作『DOWN TOWN MYSTERY』『be yourself』と音楽的自我の目覚め
中でも、『DOWN TOWN MYSTERY “NIGHT TIME” VERSION』と、続く『be yourself』は、そうした傾向が顕著に表れた2作品だ。

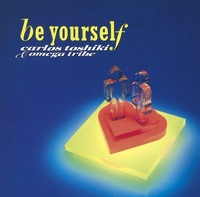
全曲で、作曲:和泉常寛、編曲:新川博という盤石の体制を敷いた前者は、サウンドの統一感という点からも堂々たる名盤と呼ぶにふさわしい。同作でコーラスを担当していた米国人ジョーイ・マッコイが正式加入しツインボーカル体制となった後者も甲乙つけがたい傑作だ。
〈カルロス・トシキ&〉期最大のヒット“アクアマリンのままでいて”の清涼感溢れる都会派歌謡ぶりにまず心を掴まれるが、ここで注目すべきは、カルロスが複数曲(“失恋するための500のマニュアル”“1000 Love Songs”)において西原俊次、高島信二との共作という形で作曲作業への参加をしていることだろう。アーティストとしての自我に目覚め、徐々に〈工房〉での存在感を増しつつある姿が確認できる。内沼映二によるデジタルフィーリング満点のミックスも非常に〈今〉向けだ(全作に通じていえることだが、最新リマスタリングの効果も抜群で、俄然迫力あるサウンドを味わえる)。






































