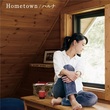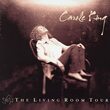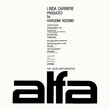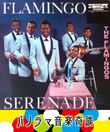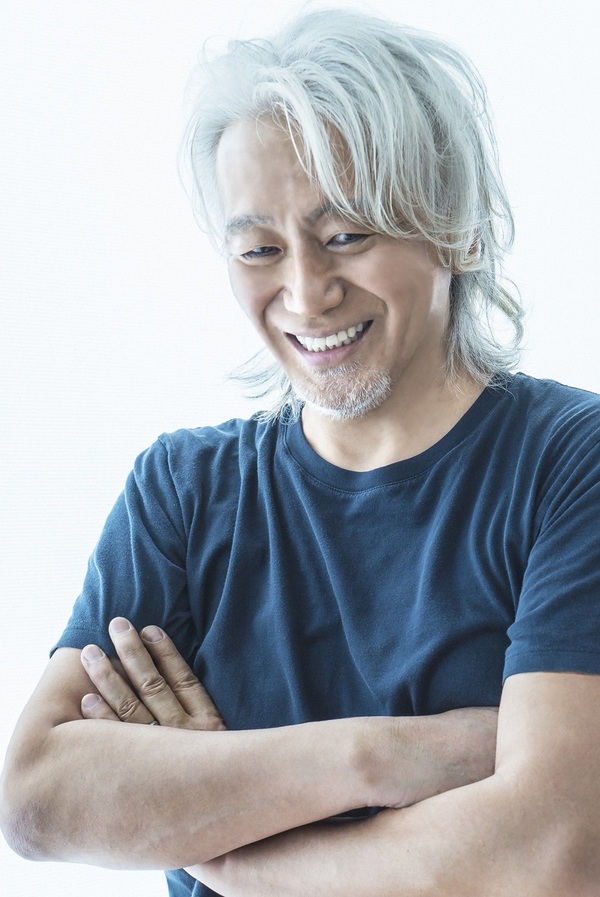PPMから渡辺美里まで、ハルナのルーツミュージック
――人間性と趣味性がちゃんとつながっている音楽だという印象が本作から感じられる。そんなハルナさんの音楽世界の良き理解者である佐橋佳幸さんがプロデュースを務めたことも大きいですよね。
「はい。佐橋さんもそうだし、柴田さんも好きな音楽が完全に合致したんですね。若い頃からブラックミュージックばかり聴いていて、それからキャロル・キングもジェイムズ・テイラーも大好きだった。このふたりの世界観に通じる音楽をやっている人がいないか知りたくなり、いろいろ掘り下げようとしたものの、まだまだインターネットも普及していなかったし、あと貧乏バンドマンだったんでCDを好きに買えなかったからなかなか難しくて。でも佐橋さんたちと出会い、いろんなことを教えてもらって世界がすごく広がったんです」
――60~70年代の音楽に興味を持つきっかけは何だったんですか?
「私の両親がピーター・ポール&マリーのカバーバンドをやっていて、アコースティックギターのシンプルなサウンドとボーカルハーモニーのみで構築されたPPMの曲が小さい頃からずっと流れていたんです」
――そこが出発点になっていると。それって80年代のお話ですよね? 当時の主流とはかけ離れたサウンドだし、周りと比べてかなり違和感があったと思うんですけど。
「もちろんありましたし、友人たちにPPMの話はさすがにできなかった(笑)。
ただ、ヒット曲も聴いていましたよ。TM NETWORKや渡辺美里さんは好きでした。今回アルバムを作るにあたって過去の音楽遍歴を振り返りながら、どういったテイストの曲が好きだったのかを書き出してみたんです。そしたら、ブルーステイストのものとか、ルーツミュージック的方向性の曲が好きだったことに気づいて」
――曲名で言うと?
「例えば、渡辺美里さんの“Lovin’ you”とか。渡辺美里さんのアルバムでは『Ribbon』が好きでした。で、そのアルバムに佐橋さんと柴田さんが参加しているんですよ。もちろん当時は知らなかったんですけど。そうか、ブルージーな感じで、アレンジもアコースティックサウンドが基調となっているものを昔から好んで聴いていたんだな、とわかって、ルーツはそこだと確信できたんです」
佐橋佳幸やバンドメンバーと作り上げたポップ × ルーツなサウンド
――アルバムの制作過程で佐橋さんと重要なキーワードを見つける作業もあったんですよね?
「楽曲を構築するうえで、どういう方向をめざすのかビジョンを明確に持っておこう、と決めまして。例えばリズムは、キャロル・キングのこのアルバムに入っているこの曲のああいう感じにしたい、といった会話を重ねながらお互いが見ているものにズレがないかを確認していったところはありました。
ただ、そういう作業をビジネスライクに行っていたわけじゃなく、〈あの曲のあそこがイイよね~〉みたいにサークルのノリでやってましたけどね。それを佐橋さんが楽しんでくれたこともあり、まったく気負いなく作業できたんです」
――とにかく和気藹々としたムードで進んでいったんですね。参加プレイヤーの方々の貢献ぶりも素晴らしいですね。ベースの鹿島達也さん、ドラムスの坂田学さんは木の匂いがする香ばしいサウンドを提供していて、ハルナさんの世界をガッチリ支えている。それからバンジョーとフィドルで参加した有田純弘さんの役割も見逃せない。
「昔から、レコーディングする曲にフィドルを入れたい、って夢があって、佐橋さんに話したところ、有田さんをお迎えしましょう、ということになったんです。有田さんはブルーグラスの本場で演奏されていた方ですから。最初にスタジオに入ってこられたとき、素晴らしい曲ですね、って言ってくださったのが、涙が出るぐらい嬉しかった」
――なんでフィドルを入れる夢が芽生えたんですか?
「なにしろジェイムズ・テイラー好きなんで。ジェイムズ・テイラーのアルバムにはけっこうフィドルがフィーチャーされた曲あるんです。私が作る曲はポップミュージックですけど、カントリーミュージックやブルーグラスのフレイバーはぜひ入れたかった。でも、夢がこんな早く叶うとは夢にも思わなかった」
――同じく達郎バンドのコーラス隊のENA☆さん、三谷泰弘さんといった気心知れた面々も参加されていらっしゃる。彼らとの作業はどうでしたか?
「楽しくて仕方なかったです。ENA☆ちゃんも三谷さんも、前から私が作品を出したい気持ちがあることを知っていたし、ずっと応援してくれていたんです。ご自身もシンガーソングライターである三谷さんにいろいろと相談させていただいたことも大きかった。ハルナさんのように歌うことと楽曲を書くことがセットになったところからスタートした人は、絶対に曲を書き続けていかないとダメだよ、って背中を押してくださった。とにかくバンドの皆さん全員から励ましてもらっていたんです」