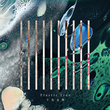自分たち〈らしい〉どころか〈そのもの〉と言える楽曲を含め、あらゆる方向から〈やってそうでやってないこと〉に挑戦したニュー・シングル!
結成20周年イヤーの第1弾リリースとして今年3月に届けられたPlastic Treeのミニ・アルバム『echo』は、ある種メンバー個々のソロ曲の集合体のような――それぞれのミュージシャンシップを可能な限り薄めることなく〈バンド自身のサウンド〉として落とし込んだ作品だったが、そこに続くニュー・シングル“マイム”は、彼らにしては珍しくバウンシーなビートが前面に出た楽曲に。リズミカルなギター・リフにリードされながらも、幻想的なディレイによって時空がソフトに歪んでいくような感覚に襲われるこのナンバーについて、〈バンドそのもののような曲〉だと有村竜太朗(ヴォーカル/ギター)と長谷川正(ベース)のふたりは言う。
「今回のシングルを作る前に〈次はどんな曲がいいのかね?〉っていうところで結構メンバーでミーティングして、いくつか案が出て。で、自分たちが過去に出した曲も含めていろいろ聴いてみて、まあ、あくまで目安としてですけど、例えば自分たちが前に作ったものだと“ムーンライト────。”みたいな(深夜を思わせる密やかな印象の曲だが、中盤からさりげなく4つ打ちが挿入されたりと楽曲のフォルムが徐々に変容していく)、そっち寄りではあるんだけどもう少し、初めてプラを聴いた人でも身体がダイレクトに反応できるような、ライヴ映えする曲を作りたいなあと思って。最初はギターのループするフレーズとメロディーラインとざっくりしたビートがあって、そこからみんなで具体的にアレンジを進めていったんです。そこで出たアイデアもそうなんですけど、今回はいまのPlastic Treeが持ってるスキルを全部活かせる曲にできたんでよかったなって思いますね。歌詞の世界観も、20周年っていうタイミングだからかもしれないですけど、最初にこのバンドを作ったときに表現しようとしてたものに近いのかも。それは“マイム”っていう単語にも集約されてるような気がします」(長谷川)。
「個人個人がバンドを通して追求したいことが見えた『echo』を踏まえて、〈じゃあ次のステップは?〉って考えたときに、ありきたりな言葉になってしまうんですけど、やってそうでやってない曲で、かつ自分たちらしい……〈らしい〉というか〈そのもの〉的な曲を作れるといいなあっていうのがあったんですよね。それで歌詞も直球なものというか、〈書いてないけど、書いてそう〉みたいな(笑)、そういう世界観を持ち込めたら……バンドの心構えみたいなものを書けたらいいなっていう気持ちがあって。それが曲のイメージにしっくりハマったっていうか。タイトルから先に決めたんですけど、身振り手振りで感覚的に物事を伝えるイメージっていうのはありましたね」(有村)。

カップリングには、作曲者の佐藤ケンケン(ドラムス)のイメージを音で表現するのに苦労したという甘くロマンティックなミディアム“トゥインクル”と、「だんだん壊れていくところがナカちゃん(ナカヤマアキラ、ギター)らしいと思った」(長谷川)という、ループを基調とするメランコリックな音世界がノイズのなかへと儚く呑み込まれていく“リコール”を収録。かつ、初回限定盤のうちの2種には『echo』のツアーの模様を収めたDVDもセットアップされる。
「『echo』のツアーはバンドにとって初か2回目ぐらいの長いツアーで、アキラの地元(釧路)とか、初めて行く土地もあって思い出深いものになったので、DVDで残せるのが嬉しいなって。曲も個々に成長していったというか、原曲のテンションに比べると完全にタガが外れてるぐらいになってる曲もあるんですよね」(有村)。
「ツアーで何度も演奏することで、曲の輪郭がよりはっきりしていった感じでしたね」(長谷川)。
そして今作には、長谷川が大ファンだというアニメーション作家ユニット、劇団イヌカレーの泥犬がアートワークを担当しているというトピックも。ファンタスティックでありながらどこか得体の知れないムードを宿した作風は、Plastic Treeそのものを表したという本作にピッタリだと言えるだろう。
「そうですね。PVにしてもジャケットにしても、Plastic Treeというバンドのキャラクターを使ってバンド自身が遊ぶというか、いろんな可能性を見てみることができたので、制作が楽しかったです。いろんな意味で、〈やってそうでやってなかったこと〉にチャレンジできた作品ですね」(有村)。
▼Plastic Treeの近作
左から、2011年作『アンモナイト』(徳間ジャパン)、2012年作『インク』、2014年のミニ・アルバム『echo』(共にFlyingStar)
※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ