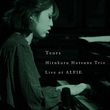バークリーで学んだジャズの伝統とグルーヴ
――バークリー音大に留学したのは、同校の卒業生である大西さんの影響ですか?
「順子さんのアドバイスもありましたし、高校3年生の頃にバークリーの5週間のサマープログラム※に参加したことも大きいですね」
――バークリーの日々で得たものは?
「どこの国でも同じだと思いますが、若い人は最近のミュージシャンばかりを追いがちだと思うんです。ロバート・グラスパーとかブラッド・メルドーとか、みんなそういうミュージシャンが好きなんですよね。だけど、ジャズをもっと深く演奏するにはもっと前にさかのぼらないとダメだ、ということを学びました。
トランペッターのダレン・バレットのアンサンブルの授業を受けた時、彼が言っていたのは〈ビバップや、いわゆるスタンダードナンバーをちゃんと弾ける人が少なすぎる。なんでもっと深掘りしないんだ〉と。それはラルフ・ピーターソンも、ビリー・キルソンも言っていました。ピアノはジョアン・ブラッキーンに師事しましたが、彼女にしてもアート・ブレイキーのようなレジェンドたちと共演してきた世代です。
私はもっと若い人にもジャズを聴いてほしいですし、伝統的なジャズの良さを伝えられたらいいなと思って演奏しています」
――ラルフ・ピーターソンやビリー・キルソンはドラマーですが、リズム面でのアドバイスも受けたのですか?
「はい。ビリーからは〈君はスウィング感やタイム感がまだまだだから、ひたすら名ドラマーが叩いているレコードを聴きなさい。フィリー・ジョー・ジョーンズやジミー・コブ等が参加したレコードに合わせて弾くように。ピアニストのコピーはしなくていいから〉と強く言われました。
ラルフからはアンサンブルの指導を受けたのですが、絶対的なグルーヴが存在するんです。〈なんであのタイム感になるんやろ? どうすればあのフィールに追いつけるのかな?〉とすごく悩みましたし、勉強になりましたね」

記憶力と体力、瞬発力――かるたの壮絶な世界
――ということは、小中高大とジャズ以外の物事にはわき目もふらず、という感じだったのでしょうか?
「いえ、日本の古い文化も好きなので、中学では茶道部に入っていました。進学した高校には、英語科と日本語や日本の文化について深く学べる国語科もありました。私は英語科だったんですが、お琴や茶道、かるたの部活もあり、その時ちょうどかるたが流行っていたので、私はかるた部に入りました」
――映画「ちはやふる」を観た時に、参加者が猛烈な勢いで、白目をむいたりしながら、ものすごいテンションで札をとっていたので、〈かるたって過激なんだな〉とびっくりした覚えがあります。実際の現場も、パワフルなんですか?
「壮絶ですね。15分で50枚の札を暗記しないといけないですし、めちゃめちゃ体力を使います。
札をとる時に大事なのは、読み手の息の入れ方ですね。これから何を読むかで、発音する前の口の形が変わるんです。1文字目がその1枚しかない札もあります。例えば、〈む〉から始まる札は〈むらさめの〉しかないので、〈む〉の前、〈m〉を聞いた瞬間にその札をとる。本当に0.01秒で差がつく世界なんです。そこも面白いなと思いました」