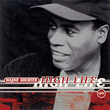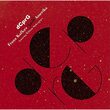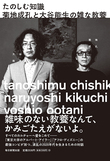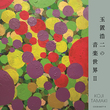菊地「圧倒的と言ってよいお言葉です。さて今、クラシックの作曲家の名前が挙がりましたし、クラシックの楽曲をとりあげることも多いのですが、あなたの曲はいわゆる〈バークリー・メソッド〉で書き表せない作風が多いと思っています。ご自身の楽曲を、クラシックの作曲家のようにスコアとして出版したいというお気持ちはありますか?」
ウェイン「ああ、そうしたいね。もうずいぶんあるんだよ、家には。深夜1時くらいに起きて、その日の夕方6時までスコアを書いていた、ということもよくあるよ。まだ誰も聴いたことのないような曲もたくさんある。17~18歳の時から書き続けている曲もある。クラシックとも、なんとも呼びようがない音楽なんだ。私がしたいこと。それは冒険する精神を絶やさないこと。すべてを知っている人間なんてどこにもいない。だから永遠に冒険は続く。そのことを音楽で表したいんだよ。私のアルバムに“Adventures Aboard the Golden Mean”という曲がある。辞書でひいたgolden mean(黄金分割、黄金比、人が物事を美しいと感じる比率)の定義がとても気に入ってね。自分の音楽には、どんな経験にも、どんなレベルにもしばられないものであってほしいんだ。つまり、golden meanは旅なんだ。golden meanという宇宙船に乗って出かける旅。何者にも捕らえられることなく、銀河系から銀河系まで飛んでいく。すべての生き物に自由であれ、と気づかるために。ジャズという言葉も“自由であれ”ということさ。頭で考え、構造でとらえてしまうのではなくてね。このアルバムを捧げた人々の名前がここに(アルバムに)書かれている。彼らはみな、バリアに挑み、バリアを越えようとした人々だ。ヴィヴィアン・トーマスというワシントンにあるジョンズ・ホプキンス大学で配管工として働いていた男。彼は心臓の弁を開いて、青色児病(先天性心疾患によるチアノーゼを呈して生まれた子どものこと)を治療する方法をみつけた。のちに医大に進みドククーになった。もう一人はヘンリエッタ・ブラッドべリーという主婦だ。彼女は台所のシンクで何かをしている時に、偶然、水面化から魚雷を発射できる空気圧式の装置を発明した。二人ともアフロ・アメリカンだ。大学で勉強したわけではなく、自分で学んだんだ。世界中の交通信号灯、ガスマスクを発明したのもギャレット・モーガンというアフロ・アメリカンの男だ。あと、スティーヴン・ホーキンス博士、DNA権威、ライナス・ポーリング博士、スーパーマンのクリストファー・リーヴ。彼は幹細胞の唱道者だった。バリアを越える……音楽もそういうことなんだ。君も、僕も! マディソン街(アメリカ広告業界の中心地)のマーケティング・マシンから飛び出すことは、チャレンジなんだよ!」
菊地「よくわかりました」
村井「今のバンドはアコースティックでフリーな部分が多いバンドだと思いますが、そういう時の楽譜というのは、コード進行とメロディが書いてある楽譜なのですか?」
ウェイン「ノー」
村井「ではどういう楽譜なんですか?」
ウェイン「自分達でもそれを探しているんだ。たとえば“Zero Gravity”という曲があるが、これを演奏する時は毎回が違うんだ。“Zero Gravity 1”、“Zero Gravity 2”、“Zero Gravity 100万”というぐあいだから、よぼよぼのおじいちゃんになっても“Zero Gravity 何千万”と言っているよ、きっと!著作権の管理は大変だろうね。ワシントンのライブラリー・オブ・コングレスと今度、話をしたいと思っているんだ。そういった新しい音楽の作曲方法に関する著作権はどうなっているのか……」
菊地「バンドのメンバーが変わっても“Zero Gravity”ですか?」
ウェイン「ああ。それにしても!著作権というのは個人をコントロールする手段なんだよ、よくよく考えてみると! 著作権の逆があってもいいはずだ。個々がどんどん増えていって“Zero Gravity 3”、“Zero Gravity 4”……と増えていけば、weはwe、us、theyのすべてになり、youはyou、more you、more you……になっていき、やがては一つの光の流れになる! どこまでやれるかやってみる、という感じだね」
村井「今、曲が毎回変わっていくとおっしゃったのは、あなたがいらっしゃった頃のマイルス・デイヴィス・グループでもそうだったんじゃないかと思うのですが、そうでしたか?」
ウェイン「それに近いものはあったね。もちろん“Green Dolphin’s Street”、“Fore”、“Round Midnight”のようなDNAに組み込まれているというか、つい自制してしまうというか、誰も手を出そうとしない曲もあったが。マイルスと演奏しているときというのは、100%自分になれる。ただしフォーマットはあるので、そのフォーマットの中でどれだけ違うことができるかというのが大きなチャレンジであり、エキサイティングな部分だった。でも嘘ではダメだ。嘘はつけない。嘘でないときにこそ、自分でも予想外の、それまでと違うことができるんだ」
村井「ミュージシャンじゃない者には〈嘘をついてはならない〉というのは、ちょっとわかりにくいのですが」
菊地「一種の啓発、ということだと思うんです。やっている間に完全なトランスというか、ゼロの状態になり、ふだんは出ない力が出て〈それはもう検証するまでもなく真実だ〉という事が実惑できる時間は、演奏にかかわらずいろんな局面でありますが、ただ演奏では特に多いですね」
ウェイン「環境の囚われにならない、ということさ。自分自身の影の犠牲になってはならない。それでは自分が客体(object)となり、歴史上初めて、環境が主体(subject)となってしまうじゃないか!」