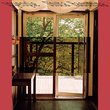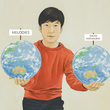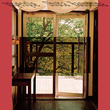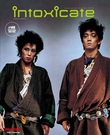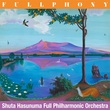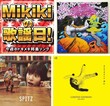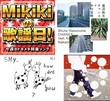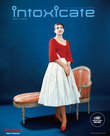〈電子音を使っている〉ではなく〈音そのものから作っている〉
――長い期間をかけて作られているので音楽性も様々ですが、アナログシンセが全面的に使われていて、〈電子音楽家としての蓮沼執太〉という側面が強く感じられる作品にはなっていると思うのですが、そのあたりはどの程度意識的でしたか?
「僕、30代になってからアナログシンセサイザーを買うようになって、それまではほとんどソフトウェア上で作ってたんです。なので、HEADZなどで作品を出してたときの作り方と今とでは全然違くて。
まあ、ソフトウェアで作ってたときもプリセットではなく、音をゼロから生成して、それを無理やり12音階にして演奏するみたいな感じでした。今はハードウェアになったけど、やっぱり自分で音を作っているので、そこは同じと言えば同じかも。
でも〈電子音を使ってる〉というより〈音そのものから作ってる〉っていう認識の方が強いかもしれない。ただ電子音やシンセを使ってるというよりは、音そのものが持ってるフォルムとか、どこからそれが作られているかとか、そういうところにこだわりを持って作ってるっていうのはありますね」
――資料には〈15年ぶりのインストアルバム〉とも書いてあって、これは『POP OOGA』から15年ということですよね?
「そうです。あのアルバムはちょっと歌ってるんですけどね。
同じPro Toolsを使ってますけど、『POP OOGA』のときとは曲の中に含まれる時間や空間の考え方が完全に違うと思います。それはやっぱり展示での経験とか、フィルでの合奏からたくさんのフィードバックを受けてそうなっています。それはロジカルに考えてそうしてるわけでもなく、感覚として染みついちゃってる感じかもしれません」
――6月に行われた蓮沼執太フィルのビルボード公演では5人編成でトータスの“Seneca”を9年ぶりにカバーしたそうですね。もともと『POP OOGA』の楽曲をライブ演奏するために4人編成の〈蓮沼執太チーム〉が生まれて、それが〈蓮沼執太フィル〉に発展したことを思うと、『POP OOGA』からの歴史を一旦振り返ったうえで、今回のソロアルバムが出るという流れにも見えます。
「時間の流れって早いので、自分自身で振り返らないといけないというか、今では僕が過去にやってきたことを知らない人も多いと思うんですね。〈トータスのカバーとかやってたんですね?〉というように。
たとえば、知人が言っていたことで、現代美術の世界でも美大は4年制だから、ある作家が4年間個展をしてないと、その作家のことが知られずに過ぎ去ってしまう。別に〈忘れられたくない〉と思ってやってるわけじゃないですけど(笑)、事実としてそういうこともあると思ったときに、自分がやってきたことを反芻して噛みしめる必要もあるのかなって。もちろん、安易に昔やったことをもう一回やるのではなくてね。
実際に演奏した音を聴くと、やっぱり当時とは全然違うから。メンバーそれぞれが全然違う音を出してくるし、そうやって今の音になるよさを感じたかったのかもしれないです」
音楽的なものとノイズ的なものを等価に扱う
――それこそ“Weather”という曲名は『POP OOGA』をリリースしたレーベルの名前でもあるわけですが、その曲を配信の1曲目にしたのは意識的でしたか?
「いや、直接的にHEADZのWEATHERというレーベルを意味しているわけではありませんが、素晴らしいレーベルですし、リスペクトをしてます。当時できてた楽曲の中で一番完成度が高かったから1曲目に配信したと言ったらそれまでなんですけど。
こういうビートものはこれまでも作ってきたし、あとエレクトロニカとかアンビエントの人みたいに思われてるんだろうなっていうのはわかりつつ、でも本人的にはそういうわけでもなくて。音楽的にはこれまで培ってきた音作りとかリズム感みたいなものを素直に吐き出している感じではあります」
――HEADZよりもさらに前にはエレクトロニカのイメージが強いPROGRESSIVE FOrMからも作品をリリースしていましたし、ポストロック、エレクトロニカ、IDMのようなルーツの部分は今にも受け継がれてると思うんですけど、ソフトウェアとハードウェアの違いだったり、空間の捉え方の違いによって、やはり昔の楽曲とは別物になっているなと。
「たとえば“Weather”は、ダンスミュージックという形式で作っているものの、クラブでかけてみんなで踊ってくださいって曲ではないんですね。90年代のダンスミュージックはクラブでかけるための音楽だったけど、ダンスミュージックの形式も徐々に変わってきて、みんなこの(ヘッドフォンの)中で楽しむようになったことなど、音空間のいろいろな変化があって、そういう自分のリスナーとしての感覚も楽曲に含まれてるんじゃないかな。
あとはノイズの扱いですね。コンピュータで生まれたノイズとか、シンセシスを使って作るノイズも同じように扱ってるっていうのは、いつも通り行なっています。逆に言うと昔からずっと意識してたというか、音楽的なものとノイズ的なものを自分は本当に等価に扱ってきてるなっていうのは、このアルバムで改めて思いました」